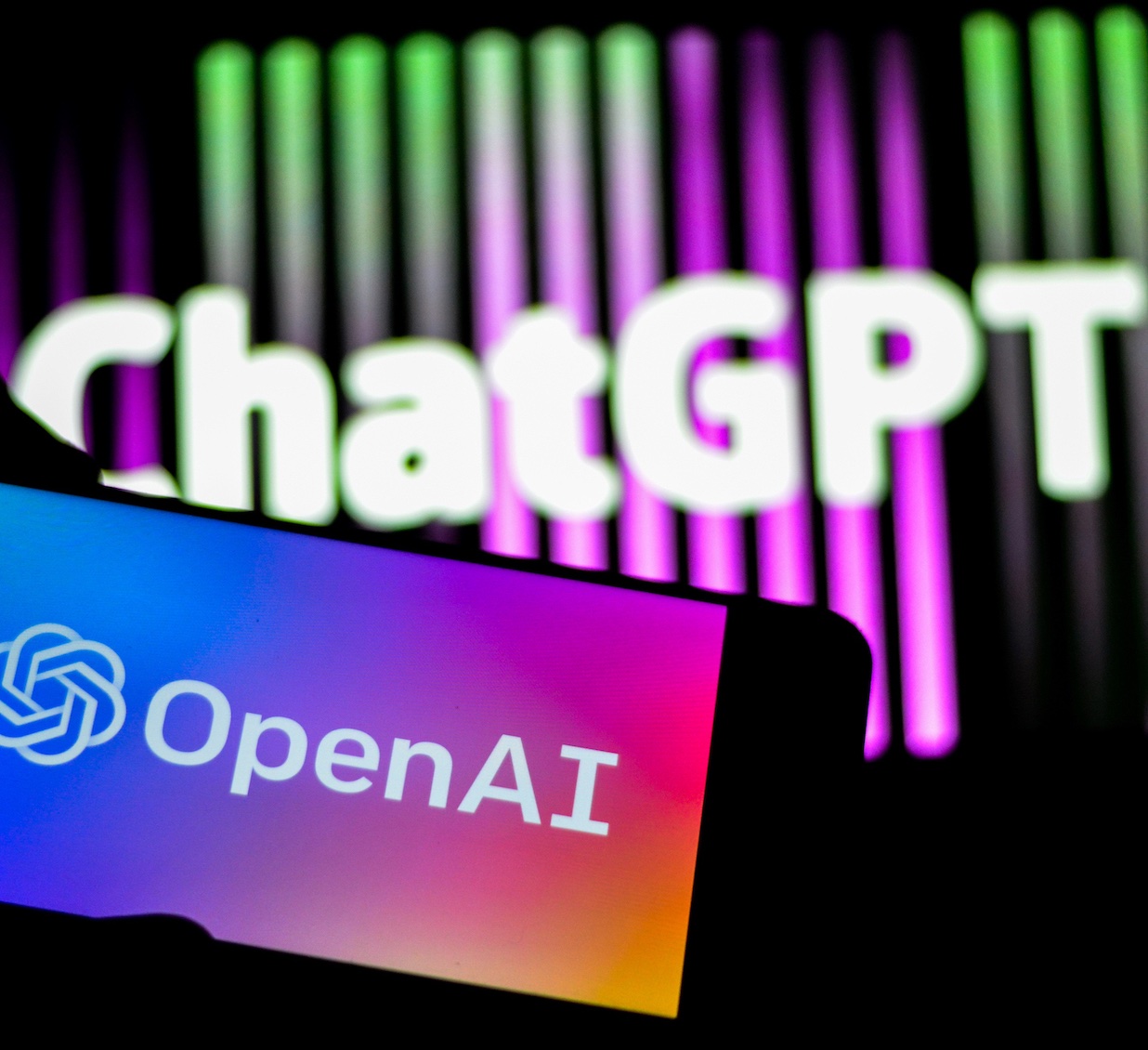「エロス」と「聖なるもの」で蕩尽するのが人間ではないのか 〜「ホスト問題」と「統一教会問題」の三つ目の共通点【仲正昌樹】

「統一教会問題」と「ホスト問題」の三つ目の共通点は、「蕩尽」だ。これは、フランスの思想家・作家で、サディズムの再評価や、[エロス-宗教-芸術]の根源的な還元を指摘したので知られるジョルジョ・バタイユ(一八九七-一九六二)のキーワードだ。
バタイユという名も蕩尽という概念も、現在では、フランスの現代思想・文芸批評好きの限られた人にしか関心を持たれていないが、一九八〇年代には、経済人類学者の栗本慎一郎(一九四一〜)のベストセラーになった『パンツをはいたサル』(一九八一)を通して、一般的にもかなり認知されていた。当時栗本は、受験地獄で追い込まれた青年が両親を金属バットで撲殺した事件など、不可解な事件や風潮を、経済人類学の理論を用いて、意外な角度から分析してみせていた。栗本の分析の道具立てとして、最も重要なのがバタイユの「蕩尽」論である。

「蕩尽 consumation」というのは、無駄に、つまり自分にとって何の得にもならないやり方で、消費することである。マルクス主義を含む近代経済思想は、「経済」を「生産」を中心に考え、「消費 consumption」も、「生産 production」のサイクルの一部と考える傾向がある。衣食住のために「消費」することで、労働者自身の生存が可能になり、かつ、生殖=再生産(reproduction)によって子孫を増やし、新たな労働力を生み出すことが可能になる。
二〇世紀に入って、レジャー、ファッション、スポーツ、ゲーム等の文化消費が資本主義発展の原動力になったと言われているが、それは従来と異なった形で、種類の商品(非物質的商品)の生産にすぎない。更に言えば、そうしたより快適に消費するためのサービスや、家事やケアまで商品化されるということは、私たちの生活全体が資本主義の生産体制に組み込まれたことを意味する。生活全体が資本主義的生産体制に組み込まれた社会では、生産と消費が一体化しており、各人は、生産(の可能性)を増大させるために消費するよう仕向けられている、と言える。
バタイユによると、食物であれ、性行為の相手であれ、欲求の対象を手に入れると、すぐに消費する動物と違って、人間は将来の消費のために現在の欲求を抑えて、備蓄する。文明とは、欲求を一定の枠内に収め、効率的な生産機構を構築することで、備蓄を増やしていくシステムだ。「パンツを穿く」という行為は、自らの欲求を抑制するために身に付けていることの象徴である。文明が発達するというのは、欲求充足の先延ばしによる蓄積傾向がどんどん強まっていく、ということだ。
バタイユは、欲求の抑制による蓄積はどこかで限界が来て、抑えこまれてきた欲求が爆発する。爆発で社会全体が崩壊しないように、定期的なガス抜きが必要になると指摘する。それが、共同体を挙げて行われる各種の祝祭(カーニヴァル)だ。