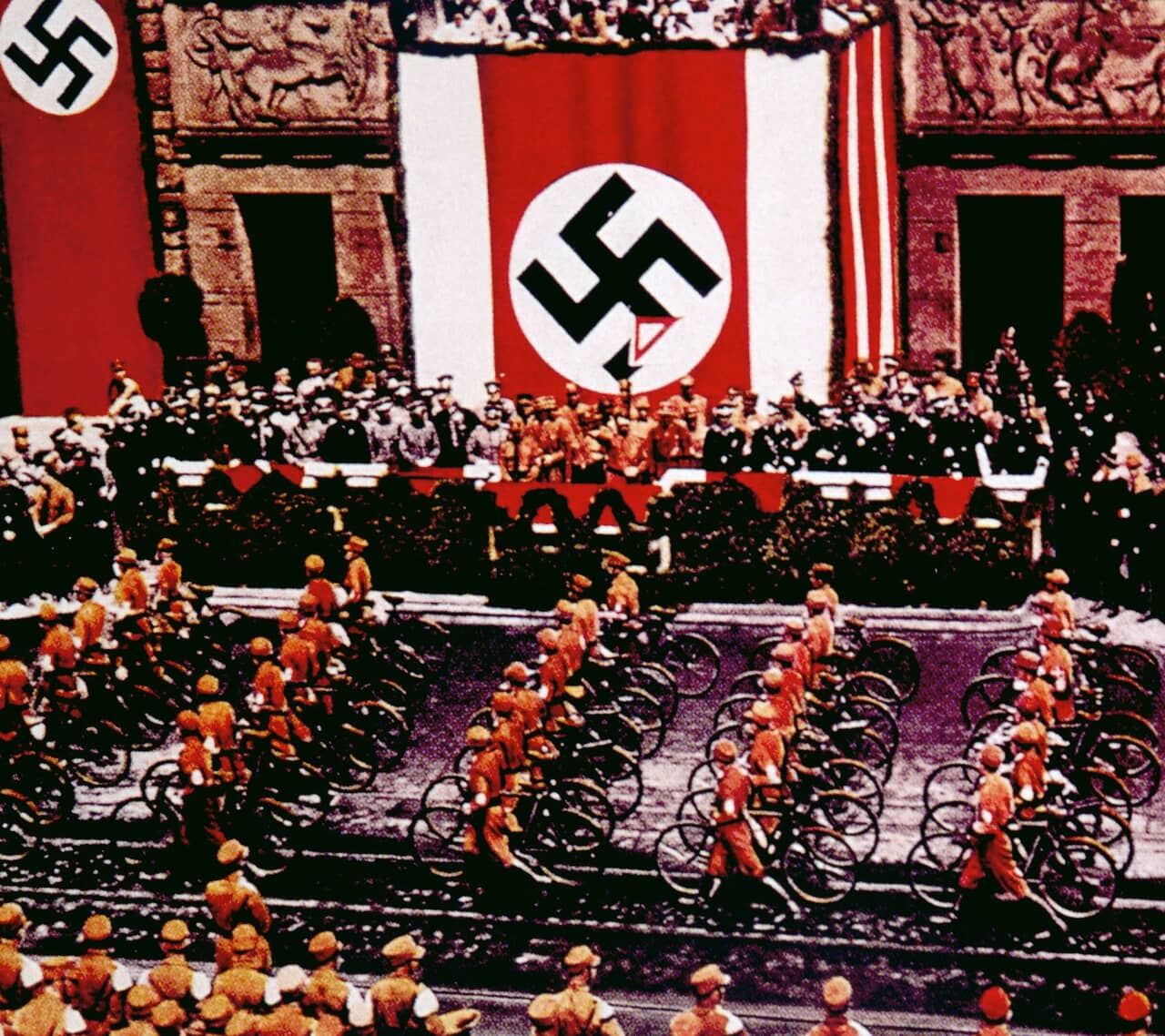アーレントが指摘し、カフカが予見した現代人の恐るべき変容とは? ネットを介して人間はますます動物化する【仲正昌樹】
カフカ没後100年 アーレントとカフカが語った「公/私」境界線の溶解

『人間の条件』(一九五八)でハンナ・アーレントは、最も人間らしい営みである「活動 action」、言語や身振りによるコミュニケーションは、古代のポリスのように、「公/私」の境界線がしっかり引かれていることによって可能になったと指摘した。「公的領域」が、自分と対等の他者たちから成る「公衆the public」の前に姿を現し、自らの意見の真実性を伝えるべく立派な市民として活動する=演じる(act)場であるのに対し、「家 oikos」を中心とする「私的領域」は、家長(=市民権保持者)による暴力を伴った支配が行われ、(主としての家長の)生物的欲求が充足される場でもある。動物的な欲求、暴力的な衝動が「私的領域」の中に抑え込まれ、処理・制御されていることで、市民は「公的領域」で立派な人物としての人格=仮面(persona)をかぶって、他者の前で活動する=演じることができる。

アーレントは、「経済」――〈economy〉の原義は〈oikos〉の運営術――を中心に動く近代市民社会では、「公/私」の境界線を厳格に守ることが困難であり、ヒトの暗い欲求が表の領域に表出しがちであること、生活上のニーズに煩わされることなく、良き市民として演技=活動する余裕がない人ばかりになっていることを指摘している。生々しい動物的な欲望が白日の下にさらされるようになると、「公的領域」を保つことが難しくなる。
カフカ(一八八三-一九二四)の作品の多くは、こうした「公/私」の境界線の侵犯という視点から読み解くことができる。カフカの分身のように思える主人公たちは、プライベートな空間に拘りを持っている。『変身』(一九一五)のグレゴール・ザムザが、虫に「変身」するのは、自分の部屋のベッドの上だ。起き出して部屋から出、周囲のリアクションから自分の身体の変化を知ることになる。この姿ではもはや会社勤めを続け、一家を養うことはできない。彼は自分の部屋に閉じこもり、次第に人間性を失っていく。一家の者たちは、彼の部屋に入っていろいろ世話をするが、その醜く変身した姿と行動に耐えられなくなり、父親は林檎を投げつけ、彼を殺そうとする。虫になった彼に絶望した一家は、新たに下宿人を家に招き入れる。ザムザが生息できる場は次第に少なくなっていく。
グレゴールの「変身」は、彼が社会で生きるためそれまで隠していた欲望、動物性が身体的な振る舞い、症状として現れ、公的領域から退去せざるを得ない状況が生じたことを寓意していると解釈できる。動物的な自己を露出することが許される私的空間であるはずの部屋に辛うじて引きこもったものの、動物化が進んでいくなかで、家族が部屋の中に入ってくる。虫になった“彼”にはそれを拒否する意思を表明することができない。というより、意思そのものが依然としてあるかどうかさえ定かでない。家族や他人の眼に始終晒されることになる。「人間」らしい外観はどんどん崩れていく。
- 1
- 2