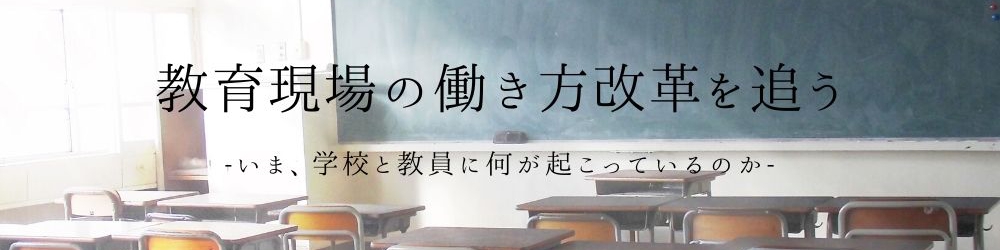「給特法」改正がもたらすもの
第1回 学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-
それらを引き起こす様々な原因は複雑に絡み合い、とても一言で片付けられるものではないだろう。しかし、一つだけ確実に言えるのは「教員の働きすぎ」が問題の中心にあることだ。
「働き方改革」という言葉が聞かれるようになった昨今、教員の現場はどうなっているのか。
先日、閣議決定された「給特法」の改正は、その解決の第一歩となるのか。
教育現場への取材を続けるジャーナリスト・前屋毅氏が考察する。
■教員の残業代はどうなっているのか
「給特法を知っていますか?」と訊ねると、学校関係者以外からは、ほぼ間違いなく「なに、それ?」という返事が戻ってくる。そんな人たちも、「教員の働き過ぎ」が社会問題化していることは知っている。
「教員だけじゃなくて、オレたちだって働き過ぎだよ」という反応も少なくない。自分たちも働き過ぎているのだから、教員だって働きすぎで当然じゃないか、ということらしい。働き過ぎを正当化する、おかしな理屈である。
しかし、「教員には残業手当がつかない」と説明すると、それに対する反応は、これまた間違いなく「エーッ!」である。会社員である自分たちの残業には手当がつくように、教員にも残業代が支払われていると思っているのだ。
一般の会社員にすれば、残業に対して残業手当がつくのは普通のことでしかない。働き過ぎも残業手当も普通なのが、普通の会社員の「常識」なのだ。残業手当もなしに過労死寸前まで働くなど、世の会社員からすれば「常識外」でしかない。
その「常識外」が、教員の働き方の実態である。残業手当なしで労働時間だけがうなぎ登りに増えている教員の働き方は、「定額働かせ放題」とまで呼ばれたりもしている。
そして、その根拠になっているのが「給特法」である。給特法は正式名称を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という。
この給特法の改正案が10月4日に招集された臨時国会で審議テーマのひとつとしてあがっており、改正案は10月18日には閣議決定されている。「いよいよ教員にも残業代が支払われる時代到来か」と思うかもしれない。
しかし結論から言ってしまえば、改正案が国会で成立しても、一般の会社員と同じように教員に残業代が支払われるようにはならない。教員の待遇は、普通のビジネスマンとは同じにはならないのだ。
なぜなのか。
それを知るためには、給特法が制定された経緯を振り返ってみる必要がある。
■当事者不在だった給特法の成立
戦後、教員にも労働者の一員として労働基準法(労基法)が適用され、32条によって8時間労働制となった。36条と37条も適用され、残業には超過勤務手当(残業手当)が支払われることにもなっていた。
しかし、実際には残業手当は支払われていなかった。文部省、労働省、人事院も各自治体に対して支払の指導を繰り返したが、支払われない事態が続いた。
これに対して日本教職員組合(日教組)は1960年代に、各地で超過勤務手当の支給を求める訴訟、いわゆる「超勤訴訟」を展開していった。教員にも労基法が適用され、それによって超過勤務手当の支払いは法的にも認められていたのだから、当然ながら訴訟では教員側の勝利が続く。
そのため文部省(2001年の中央省庁再編で文部科学省となる)は、1967年8月に教員給与改善措置費の予算要求を行う。残業手当を支払うための予算要求である。そのままいけば、教員にも会社員と同様に残業手当が支払われるようになっていたかもしれない。
しかし、この事態に当時の自民党文教部会は黙っていなかった。超勤訴訟で日教組が次々と勝利し、それに屈するように超勤手当を支払うことは、日教組の「勝利」を認めるものでしかなかったからだ。日教組と対立関係にある自民党文教部会としては、この事態は放っておくわけにはいかなかったのだ。
そして自民党文教部会が文部省に働きかけて提出させたのが給特法案であり、1971年5月に自民党の強行採決によって国会で成立し、翌年1月に施行された。これによって、一般のビジネスマンとは違う、残業しても超過勤務手当(残業手当)が支払われない「異常」な状態が始まっていく。
- 1
- 2