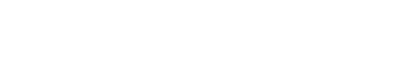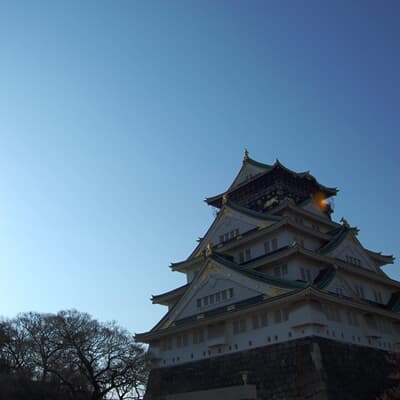東西きれいごと合戦
季節と時節でつづる戦国おりおり第449回
新型コロナウイルス感染拡大第3波。GO TOキャンペーンがそのきっかけになっているとの指摘に政府与党側は「利用する方々がマナーを守ってもらえると信じる」と、国民側の良識に頼るというきれいごとを並べ、野党側は「具体的な感染拡大防止策を」とこれもお題目を繰り返すのみでなんら自前の経済・感染拡大防止両立の名案を提示するでもなく。双方きれいごとで終始している間に、事態はどんどん悪化の一途をたどっております。これぞまさに現代の「小田原評定」。後世「永田町評定」と呼ばれることになるのは間違いないところでしょう。
さて、今から439年前の天正9年10月25日(現在の1581年11月21日)、毛利氏に属する鳥取城が羽柴秀吉の兵糧攻めに耐え切れず、鳥取城将吉川経家が自刃しました。4ヶ月前の6月25日から羽柴秀吉軍によって包囲されていた毛利方の鳥取城は、秀吉による米の買い占め作戦によって極度の兵糧不足に陥り、その上細川忠興配下の松井康之が毛利軍の兵糧入れ特攻部隊を撃退するなど徹底的に孤立化させられていたため、1,000人あまりの兵は戦闘能力を失い、ついに天正9年(1581)10月25日(旧暦)、降伏となったのです。
自分ら首脳陣3人の首と引き替えに城兵たちの命を助けてくれと頼んだ経家は未明寅の刻(午前4時頃)に切腹し、「信長の実検に入るる首なれば、よく打て(我が首は信長の首実検に供されるのだから、しっかりと打ち落とせ)」(『安西軍策』)と首を切らせたそうですが、彼が自害の前に家族に書き送った手紙には「日本二つの御弓矢境において忰腹に及び候事、末代の名誉たるべく存じ候」(日本の二強、毛利と織田の戦いで自分が切腹するのは、末代までの名誉だ)とありましたが、立派な申し状ながら、毛利としては外様の鳥取城の守備に派遣した一族の経家に自害でもして貰わなければ、ただの開城退却では武威も衰え、他の外様たちの向背も定かではなくなるところですから、表向きはどうあれ嫌でも切腹しなければならなかったのではないでしょうか。
彼の遺書は、そういう意味で建て前の哀しさの様なものが感じられます。
一方、城を落とした側の秀吉ですが、彼は2年後に小早川隆景へこの鳥取城攻めなどを指して「秀吉、人を切りぬき申し候事嫌い申し候」と書き送っているものの、これも見事な「建て前」です。
彼が人を殺す事を嫌っていたかどうか、天正5年の上月城攻めで敵の婦女子200人あまりを串刺し・磔にして晒した事を自慢した書状が残っている事や、天正10年10月に信孝の家臣に出した書状でも過去の戦功について「ことごとく首を刎ね」「首を刎ね」「首を切り」と連呼している事など、威を張り敵の動揺を促すためとは言え、彼が決して聖人君子の類ではなかった事を証明しています。
そもそも、『信長公記』に「餓鬼のごとく痩せ衰えたる男女、柵際へより、もだえこがれ、引き出し助け給へと叫び、叫喚の悲しみ、哀れなるありさま、目もあてられず」 とあるような飢餓状況を出現させ、『毛利家日記』が「牛馬を食べ人肉を用い」、『信長公記』が負傷者に皆が寄ってたかって襲いかかり、刃物で手足を関節から切り落として食べたと記録するような地獄を目の前にして包囲を続けた秀吉にそんな殊勝な神経などある筈もありません。
彼が強攻策を採らず包囲戦術を採ったのは、それが協働する戦争商人たちの利益に叶う事だったから(米の相場操作など)というだけに過ぎないと思いますね。
ちなみに、経家切腹の際の秀吉側の検使は堀尾吉晴。彼は、備中高松城の水攻めの際も最後に検使を務めました。秀吉家中で一番もっともらしい顔つきだったんでしょうか(笑)。