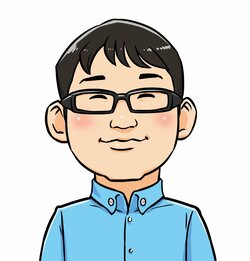人生を変えた闘病、会見、死……逸見政孝とたけし、小林麻央と海老蔵
昭和から平成へと移りゆく「時代」の風景が見えてくる「平成の死」を振り返る。
と語るのは、この度『平成の死 ~追悼は生きる糧~』(KKベストセラーズ)を上梓し、話題となっている著述家・宝泉薫氏だ。
今回は、「人の生き方」を変えたともいえる平成時代の有名人の死を取り上げ、「追悼は生きる糧」になることを示した宝泉氏の特別寄稿を公開。

「私の中で『ガン』という言葉は、イコール死に繋がるもの」
と切実な不安を語ったが、無事生還。それから75歳まで生き、同じ病気の人たちに勇気を与えることになる。
しかし、ガンはもちろん甘い病気ではない。平成8年に咽頭ガンを公表した勝新太郎は、その会見ですでに始まっていた入院治療に触れ、
「ガス麻酔はマリファナ以上。『モルヒネも打ってくれえ~』って、先生に頼んじゃったよ」
と笑わせたり「酒もたばこもやる気がしないのでやめた」と言いながら、たばこをふかしたりと、独演会を繰り広げた。が、その7ヶ月後の翌年6月に亡くなってしまう(享年65)。ちなみに、会見でのたばこはあくまでパフォーマンスで、実際の療養生活は禁煙禁酒で真面目な患者だったという。それくらい復帰して仕事をしたい思いが強かったにもかかわらず、稀代の豪傑もガンには勝てなかった。
そして、平成初期に誰よりもガンの怖さを世に伝えたのが逸見政孝だ。フジの局アナからフリーになり、人気番組をいくつも持って「平成の視聴率男」と呼ばれていた平成5年9月、彼は歴史的な会見に臨んだ。
「私が今、侵されている病気の名前、病名は……ガンです」
胃ガンであることを告白。10日後、13時間にも及ぶ大手術を受け、3キロ分もの臓器が摘出された。しかし、じつは8ヶ月前に最初の診断が下された時点で、助かる見込みのない状態だったという。クリスマスに48歳で帰らぬ人となり、葬儀ではヘアメークを担当していた豊田一幸(のちのIKKO)が死化粧を施した。
その闘病をめぐっては、激しい論争も起き、ベストセラー『患者よ、がんと闘うな』などで知られる医師の近藤誠は「手術せずにいたら、しばらくは普通の生活ができたはずだ」と指摘。未亡人の逸見晴恵も、
「最後は言葉も出ないくらい苦しんでいましたから、別の選択もあることを知っていたら、と非常に残念です」
と、後悔をにじませた。
また、家族以外で深い喪失感にさいなまれたのがビートたけしだ。『たけし・逸見の平成教育委員会』などで共演、おたがい大親友と認め合う仲だった。翌年、北野武として映画『ソナチネ』を発表するが、その撮影中、こんなことを口にしていたという。
「もう未練はない。死ぬことも怖くない」「伝説化される事故死がいい」
そんな意識が作用したのか、映画公開の翌々月、バイクで事故を起こし、生死の境をさまようことに。ただ、これを乗り越えたことで、カリスマ的なオーラはさらに増すこととなった。逸見の死は、たけしの人生を変えたのである。
KEYWORDS:
『平成の死: 追悼は生きる糧』

鈴木涼美さん(作家・社会学者)推薦!
世界で唯一の「死で読み解く平成史」であり、
「平成に亡くなった著名人への追悼を生きる糧にした奇書」である。
「この本を手にとったあなたは、人一倍、死に関心があるはずだ。そんな本を作った自分は、なおさらである。ではなぜ、死に関心があるかといえば、自分の場合はまず、死によって見えてくるものがあるということが大きい。たとえば、人は誰かの死によって時代を感じる。有名人であれ、身近な人であれ、その死から世の中や自分自身のうつろいを見てとるわけだ。
これが誰かの誕生だとそうもいかない。人が知ることができる誕生はせいぜい、皇族のような超有名人やごく身近な人の子供に限られるからだ。また、そういう人たちがこれから何をなすかもわからない。それよりは、すでに何かをなした人の死のほうが、より多くの時代の風景を見せてくれるのである。
したがって、平成という時代を見たいなら、その時代の死を見つめればいい、と考えた。大活躍した有名人だったり、大騒ぎになった事件だったり。その死を振り返ることで、平成という時代が何だったのか、その本質が浮き彫りにできるはずなのだ。
そして、もうひとつ、死そのものを知りたいというのもある。死が怖かったり、逆に憧れたりするのも、死がよくわからないからでもあるだろう。ただ、人は自分の死を認識することはできず、誰かの死から想像するしかない。それが死を学ぶということだ。
さらにいえば、誰かの死を思うことは自分の生き方をも変える。その人の分まで生きようと決意したり、自分も早く逝きたくなってしまったり、その病気や災害の実態に接して予防策を考えたり。いずれにせよ、死を意識することで、覚悟や準備ができる。死は生のゴールでもあるから、自分が本当はどう生きたいのかという発見にもつながるだろう。それはかけがえのない「糧」ともなるにちがいない。
また、死を思うことで死者との「再会」もできる。在りし日が懐かしく甦ったり、新たな魅力を発見したり。死は終わりではなく、思うことで死者も生き続ける。この本は、そんな愉しさにもあふれているはずだ。それをぜひ、ともに味わってほしい。
死とは何か、平成とは何だったのか。そして、自分とは――。それを探るための旅が、ここから始まる。」(「はじめに」より抜粋)