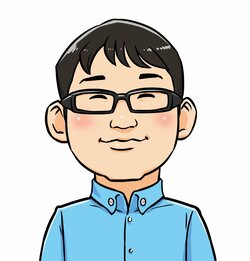樹木希林、大杉蓮、西部邁、さくらももこ……平成の終わりに示されたさまざまな死生観
昭和から平成へと移りゆく「時代」の風景が見えてくる「平成の死」を振り返る。
平成の終わりに亡くなった著名人たちの死は、令和の時代を生きるにあたって私たちが考える
死生観に大きな影響を与えているのではないだろうか?
■常に世間を驚かせ続けた奇妙な夫婦
令和が始まって、1ヶ月以上が過ぎた。平成はすでにひと時代前となったが、その終盤に亡くなった人たちはまだ鮮烈な印象を残している。そのいくつかを振り返ってみよう。
まずは、樹木希林。平成25年、日本アカデミー賞の授賞式で、
「冗談じゃなく全身ガンなので、来年の仕事、約束できないんですよ」
と語り、衝撃を与えた。しかし、そこから5年半生きて映画『万引き家族』をはじめとする、いくつもの作品に出演。これが遺作になるかもしれないという、本人及びスタッフの思いによってそれらは充実度を増した。さらにドラマやCMのほか、亡くなる4ヶ月前にはテレビ番組『直撃!シンソウ坂上』の西城秀樹追悼回でナレーションを務め、前年6月からNHKの長期密着取材にも応じていた。
その密着は、死の11日後に『”樹木希林”を生きる』として放送されたが、なるべく赤裸々に撮りたいということなのか、制作側の意図が見えづらく、樹木が苛立つ場面も。仕上がりに不安を感じた彼女は自分のPET(陽電子放射断層撮影)検査の画像を使うよう、サービスしたりもする。ネット上ではディレクターへの批判も出た。とはいえ、結果として、ガンに苦しみながらも作品に情熱を燃やす75歳の老女優の業や底力といったものはしっかりと刻印されていたように思う。こうして彼女は「ギリギリまで働く幸せ」を極めたのだ。
半年後の平成31年3月には、彼女のあとを追うように、夫だった内田裕也が他界。その11日後には、萩原健一が世を去った。この3者の訃報は、昭和から受け継がれてきた豪放で無頼なものの黄昏を感じさせるようでもあった。
樹木以上に、ギリギリまで仕事をしていたのが大杉漣だ。主役のひとりを務めていた『バイプレイヤーズ ~もしも名脇役がテレ東朝ドラで無人島生活したら~』のロケ後、共演者たちと食事をとり、ホテルの部屋に戻ったあと、心不全で急死した。
収録済みだった番組はテロップつきで放送され、なかでも『アナザースカイ』はしみじみとする内容だった。来し方行く末に思いを馳せ「死にたくないとも思わないし、と言って死にたいとも思わない。死ぬっていうことがわかってるってだけであって、死ぬまでの間に俳優としてどれだけできるかっていうことはわからない」としたうえで、
「申し訳ないけど、もうちょっと生きたいなって思ってます。っていうか、僕はもうちょっとやりたいこともあるので、66歳でも希望がいっぱいありますよ」
と、明るく語っていたのである。それでいて糟糠の妻について「私の子供をふたりも生んでくださって」と感謝を示すなど、死の予感もどことなく漂っていた。
KEYWORDS:
『平成の死: 追悼は生きる糧』

鈴木涼美さん(作家・社会学者)推薦!
世界で唯一の「死で読み解く平成史」であり、
「平成に亡くなった著名人への追悼を生きる糧にした奇書」である。
「この本を手にとったあなたは、人一倍、死に関心があるはずだ。そんな本を作った自分は、なおさらである。ではなぜ、死に関心があるかといえば、自分の場合はまず、死によって見えてくるものがあるということが大きい。たとえば、人は誰かの死によって時代を感じる。有名人であれ、身近な人であれ、その死から世の中や自分自身のうつろいを見てとるわけだ。
これが誰かの誕生だとそうもいかない。人が知ることができる誕生はせいぜい、皇族のような超有名人やごく身近な人の子供に限られるからだ。また、そういう人たちがこれから何をなすかもわからない。それよりは、すでに何かをなした人の死のほうが、より多くの時代の風景を見せてくれるのである。
したがって、平成という時代を見たいなら、その時代の死を見つめればいい、と考えた。大活躍した有名人だったり、大騒ぎになった事件だったり。その死を振り返ることで、平成という時代が何だったのか、その本質が浮き彫りにできるはずなのだ。
そして、もうひとつ、死そのものを知りたいというのもある。死が怖かったり、逆に憧れたりするのも、死がよくわからないからでもあるだろう。ただ、人は自分の死を認識することはできず、誰かの死から想像するしかない。それが死を学ぶということだ。
さらにいえば、誰かの死を思うことは自分の生き方をも変える。その人の分まで生きようと決意したり、自分も早く逝きたくなってしまったり、その病気や災害の実態に接して予防策を考えたり。いずれにせよ、死を意識することで、覚悟や準備ができる。死は生のゴールでもあるから、自分が本当はどう生きたいのかという発見にもつながるだろう。それはかけがえのない「糧」ともなるにちがいない。
また、死を思うことで死者との「再会」もできる。在りし日が懐かしく甦ったり、新たな魅力を発見したり。死は終わりではなく、思うことで死者も生き続ける。この本は、そんな愉しさにもあふれているはずだ。それをぜひ、ともに味わってほしい。
死とは何か、平成とは何だったのか。そして、自分とは――。それを探るための旅が、ここから始まる。」(「はじめに」より抜粋)