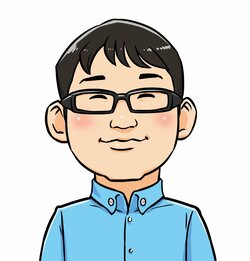樹木希林、大杉蓮、西部邁、さくらももこ……平成の終わりに示されたさまざまな死生観
昭和から平成へと移りゆく「時代」の風景が見えてくる「平成の死」を振り返る。
■新世代の人気者も去る
女子アナ同様、平成の人気職業であるユーチューバーのエイジが亡くなったのは、31年の元日。休暇滞在先のサイパンで高波にさらわれた。4月には「空ハート」の名で動画投稿をしていた女性が、撮影中のハプニングで窒息死。赤飯おにぎりの一気食いに失敗してしまった。同じく4月には、ボカロのミュージシャン・WOWAKAが心不全で急死。ツイッターでの最後のツイートは、新元号が発表された直後の「令和きれいだー。」だった。
筆者の個人的なところでは、壮健だった義父が4月1日に突然倒れ、そのまま亡くなった。また、4月30日にはSNSで交流していた女子大生が「平成も終わりなんて嫌ね、もう一緒に心中でもしちゃおうかしら」とツイッターでつぶやき、命を絶った。時代の変わり目に訪れた永訣として、忘れることはないだろう。
ほかにも「団塊の世代」の命名者で大阪万博などの実現に寄与した堺屋太一や『噂の真相』の編集長だった岡留安則、元・横綱双羽黒の北尾光司らが死去。『子連れ狼』の原作者・小池一夫と『ルパン3世』の漫画家、モンキー・パンチが相次いで亡くなったのにも驚かされた。あたかも、時代の電車に駆け込み乗車するような旅立ちだった。
そんななか、痛ましかったのが元・演歌歌手の紫艶だ。平成28年、桂文枝との20年にもわたる愛人関係を告白して、真偽をめぐり対立したが、文枝が上方落語協会会長を退任するかわりに、彼女は引退。31年3月、風呂あがりに心不全を起こし、41年の生涯を閉じた。
ただ、その訃報が伝えられたのは令和になってからだ。『週刊文春』で母親が語ったところによれば、娘は生前、
「苦しいこともあったけど、楽しいこともあったんだよ。でも一言、本当のことを言ってほしかった。お母さん、悔しい」
と、話していたという。

最後に、対照的な死生観をうかがわせる言葉をふたつ紹介しよう。まずは、平成30年1月に自殺した評論家の西部邁が、亡くなる4ヶ月前の講演で語ったものだ。
「人間、生きてりゃいいってもんじゃないし、自分がこれ以上生きていたら、社会になんの貢献もできない。(略)死に方ぐらい自分で選ぶ」
もうひとつは、同年8月、乳ガンで亡くなった漫画家のさくらももこが、死の13年前に出したエッセイ集のなかの一節だ。
「死は、誰にでもいつか訪れます。でも、死ぬまでの間は生きています。生きている間は生きている事を満喫しようじゃありませんか。生きていると、細かくちょこちょこ楽しい事や面白い事があります」
対照的な死生観と書いたが、よりよく生き、よりよく死にたいという思いは共通するのではないか。平成から令和へ、人々の営みは変わることなく続いていく。せめて自分なりの死生観を見つけ、そこに誇りを持って、限りある日々をすごしていきたいものである。
KEYWORDS:
『平成の死: 追悼は生きる糧』

鈴木涼美さん(作家・社会学者)推薦!
世界で唯一の「死で読み解く平成史」であり、
「平成に亡くなった著名人への追悼を生きる糧にした奇書」である。
「この本を手にとったあなたは、人一倍、死に関心があるはずだ。そんな本を作った自分は、なおさらである。ではなぜ、死に関心があるかといえば、自分の場合はまず、死によって見えてくるものがあるということが大きい。たとえば、人は誰かの死によって時代を感じる。有名人であれ、身近な人であれ、その死から世の中や自分自身のうつろいを見てとるわけだ。
これが誰かの誕生だとそうもいかない。人が知ることができる誕生はせいぜい、皇族のような超有名人やごく身近な人の子供に限られるからだ。また、そういう人たちがこれから何をなすかもわからない。それよりは、すでに何かをなした人の死のほうが、より多くの時代の風景を見せてくれるのである。
したがって、平成という時代を見たいなら、その時代の死を見つめればいい、と考えた。大活躍した有名人だったり、大騒ぎになった事件だったり。その死を振り返ることで、平成という時代が何だったのか、その本質が浮き彫りにできるはずなのだ。
そして、もうひとつ、死そのものを知りたいというのもある。死が怖かったり、逆に憧れたりするのも、死がよくわからないからでもあるだろう。ただ、人は自分の死を認識することはできず、誰かの死から想像するしかない。それが死を学ぶということだ。
さらにいえば、誰かの死を思うことは自分の生き方をも変える。その人の分まで生きようと決意したり、自分も早く逝きたくなってしまったり、その病気や災害の実態に接して予防策を考えたり。いずれにせよ、死を意識することで、覚悟や準備ができる。死は生のゴールでもあるから、自分が本当はどう生きたいのかという発見にもつながるだろう。それはかけがえのない「糧」ともなるにちがいない。
また、死を思うことで死者との「再会」もできる。在りし日が懐かしく甦ったり、新たな魅力を発見したり。死は終わりではなく、思うことで死者も生き続ける。この本は、そんな愉しさにもあふれているはずだ。それをぜひ、ともに味わってほしい。
死とは何か、平成とは何だったのか。そして、自分とは――。それを探るための旅が、ここから始まる。」(「はじめに」より抜粋)