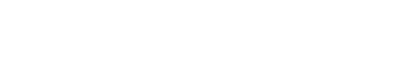城跡に廃線 ~古城を貫いた線路~
外川淳の「城の搦め手」第115回
筑波鉄道筑波線(土浦―岩瀬)が開業したのは、大正7年(1918)のことだった。
建設工事にあたっては、小田城のまんなかを斜めに突っ切る形で線路が敷設された。

小田城を貫く筑波鉄道の線路跡
1997年12月21日撮影。前世紀には、当時の城内は人跡未踏のブッシュに覆われていた。
1997年12月21日撮影。前世紀には、当時の城内は人跡未踏のブッシュに覆われていた。
小田城が国指定史跡となるのは昭和10年(1935)のことであり、大正年間には中世の城を保存しようという意識は低かった。
なお、小田城が国指定史跡となったのは、南朝関連の史跡だったことによる。
以下、主催する歴史探偵倶楽部の探査で利用したレジメを元に小田城の歴史を追ってみる。
・平安時代末期、八田知家は、源頼朝方に属して富士川合戦で武功を立てた功績などにより、常陸守護の座を与えられ、小田の地に本拠を構える。
・暦応元年(1338)、北畠親房は、小田氏を頼って東国へ下向。以後、小田城は関東南朝の中心拠点としての役割をはたす。
・康正元年(1455)、小田持家は、古河公方の足利成氏に属し、関東管領方の上杉顕房を破り、常陸南部を支配下におさめ、最盛期を迎える。
・永禄元年(1558)、上杉謙信は関東へ進出すると、佐竹氏に小田城攻略を下命。小田氏は土浦城へ逃亡。またも、ほどなく奪還。以後、佐竹氏・結城氏らと、戦っては和睦を繰り返す。
・永禄12年、佐竹氏は小田城を攻略。以後、小田城は佐竹氏の属城として機能。
・慶長7年(1602)、佐竹氏の秋田転封にともない、廃城処分となる。
昭和62年、小田城内を貫く筑波鉄道が廃止となり、城跡に廃線という時代を超えた二つの旧跡が重なり合うことになる。
平成になると、小田城では発掘調査が実施され、戦国時代の畝堀の存在が明らかになるなど、そのありし日の姿が明らかになりつつある。

発掘調査中の小田城
2006年2月25日撮影。現在は復元工事が進展しているもよう。
2006年2月25日撮影。現在は復元工事が進展しているもよう。
現在、筑波鉄道の廃線ルートは、「つくばりんロード」というサイクリングロードに姿を変えているが、小田城内は迂回するルートとなっている。

放置状態の常陸小田駅
サイクリングロードの建設とともに、廃線巡りのポイントとして整備された。
サイクリングロードの建設とともに、廃線巡りのポイントとして整備された。
なぜだか急に廃線の話がしたくなり、城と鉄道の話をからめてみた。