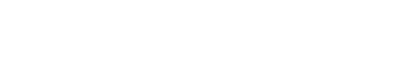白人美女天国を揺るがし始めたエキゾチックな南洋・東洋美女たち
【第2回】美女ジャケはかく語りき 1950年代のアメリカを象徴するヴィーナスたち
■収集してみて分かった! 1950年代の美女ジャケは白人美女が99%

演奏者や作曲家ではなく、ただのモデルがLPレコードのジャケットを飾ったのが「美女ジャケ」。この美女が歌っているのか? と思って買うと歌無しの器楽演奏で、美女はなにも関係なくがっかりした、なんていうのはレコ好き界隈ではよくあった話だ。
そもそも30センチのLPレコードが開発される前、(蓄音機で聴くような)78回転のSPレコードの時代には、ジャケットというものが存在しなかった。レコードはただ専用紙袋に入れて売られていたのだ。レコードの真ん中に貼られたレーベルと、そこに書かれたデータがレコードの「顔」だった。
SPレコードは片面再生が約3分。1曲聴いたら裏返さなければならなかった。LPレコードは片面で、20分程度再生できるようになったから両面聴いて40分程度。これはひとりのアーティストの音楽を体験するには心地良い時間だった。
こうしてジャケットがデザインされるようになると、アーティストの写真以外に「もっと売れそうなジャケット」が模索されるようになる。
アーティスト写真が多かったのはクラシック音楽の世界だ。指揮者や演奏家など。でも見栄えが良い顔ばかりではないのは、CD時代になってからも同様のこと。
クラシックのCDジャケットをたくさんデザインしてきた筆者としては、ほんとうにアーティストの顔出したがりには辟易するけれど、これはひたすら耐えるしかない。
「ライト・クラシック」と呼ばれる、軽く聴き心地の良いイージーなクラシック風のレコードが出始めたのも戦後のこと。
さらにムード・ミュージック(あるいはイージーリスニング)という軽音楽が大きな市場をつくりつつあった。恋人と一緒にいるとき…家でくつろいでいるとき…バックグラウンドで流れる、薬にはなっても毒にはならない音楽。そう、PUNKなんて必要なかった時代の話なのだから。
急成長するムード・ミュージックのレコード・ジャケットには、やはり薬にはなっても、ときどきしか毒にならない美女のモデルが起用されるようになる。そっちのほうがアーティスト写真よりも売れたのだから。
その美女たち、収集してみればわかるのだが、99%と言ってよいくらい白人美女。まあ、50年代とはそんな時代だったのだ。
いまではハリウッド映画も人種の人口比に対応して、6人のチームが主役になるなら白人3人、黒人2人、東洋人1人とかで配役する。マーケティングとしてもそれがベストなのだ。あるいは、刑事ものだったら現場の白人警官に対して黒人の上司とか。あざとい配役だ。
東洋人はほぼ3番手だったのがヒスパニックの台頭でいまや4番手になりつつある。これもしょうがないね。
そんな白人美女全盛の1950年代後半、エキゾチック・ミュージックというものが台頭してくる。マーティン・デニーが代表的だが、これはまた別の回で。南洋風、東洋風、アフリカ風(あくまでなんちゃって、である)に聞こえる、でも、洗練された都会的エキゾ・ミュージックには、それに合うジャケットが必要だった。
こうしてマイナーな存在でしかなかったオリエント顔が、美女ジャケ界隈で流通し始める。肉食的な白人美女の世界に飽いていた向きには、これは清涼剤でもあり、あらたな刺激でもあった。
そもそも第二次世界大戦で、南洋や極東に配属された兵士たちは異郷の女性にとりこになって帰って来たのだ。
だから戦後のサバービア(郊外)の住宅には、南洋やオリエントのグッズが溢れた。ゴージャスなウッド調のレコード・プレーヤーのそばにティキ(ハワイやポリネシアの)像が飾られたり、モアイ像のミニチュアが置かれた。フィフティーズのアメリカでは驚くほど「南洋」や「東洋」、「アフリカ」ものが流行する。それはみんな戦場に行った兵士が持ち帰った新しい文化だった。