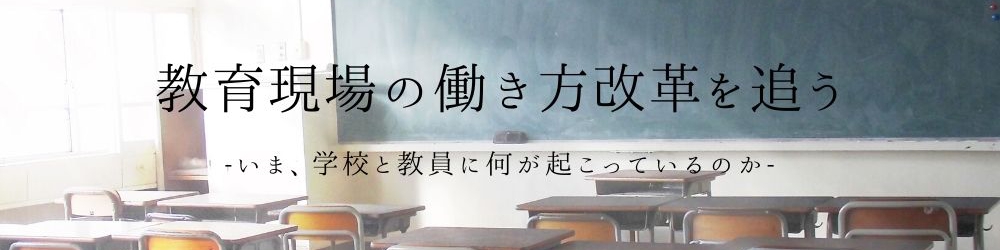『教員定額働かせ放題』の根は深かった
【第2回】学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-
|文科省の対応はどうか
当時は週6日制で土曜日は半日が休みなので、月曜から金曜日は8時間勤務、土曜日は4時間、そして残業が4時間で週48時間勤務という計算になる。
さらに通達には、「原則として超過勤務は命じないこと」とし、「1日において実働8時間以上勤務する必要がある場合にはその勤務を命ずることはできるが、その勤務は原則として1週48時間の勤務に含まれるものとして勤務する如く命ずるものとする」と記されている。残業しても勤務時間は週48時間に収めること、と念を押しているのだ。
その通達が出されて約1カ月後の3月19日には、新たな「文部事務次官通達」が出されている。「教員の超過勤務について」というタイトルで、先に残業は原則として命じない旨の通知をしたけれど、次については例外として残業を命じることができる、という内容だ。
その例外とは次の4つである。
(2) 日直
(3) 入学試験事務
(4) 学位論文審査
(1)と(2)については、48年施行の法律でも例外とされているので、あとの2つを文部省として付け加えたことになる。それでも日常的な業務ではないので、週48時間の勤務時間を守るのには、さほどの支障があるとは思えない。
実は、現在の給特法の下でも、例外的に校長が教員に残業を命じることのできる「超過勤務4項目(超勤4項目)」というものがある。これについては今後詳しく触れていくので、今回は触れないでおきたい。ともかく「例外」をつくることも、この当時から前例があったことになる。
話を戻そう。
通達では、4つについては例外として残業を命じることができるとした後に、次のような文章が続いている。
「超過勤務手当を支給してさしつかえありませんから運用要領をお含みの上、しかるべくお取り計らいを願います」
校長が命じることのできる残業について例外は認めるけれども、それにはちゃんと残業代を支払え、というわけである。まっとうな方針に思えるが、文部省の方針が徹底していたわけではない。
1948年の法律で教員の給与面での優位性が確保されたものの、1951年以降に給与法の改正が繰り返され、優位性は失われていく。教員給与の優位性が失われることに、結果的に文部省はまったく対処できていない。
さらに、「残業は命じない」という方針を掲げながら、学校現場で残業が強制されている実態に対して有効な手段を講じようともしていない。それは、現在の文科省の姿勢そのままでもある。
そんな状況が続いたため1967年11月6日、
1949年の文部事務次官通達で教員の勤務時間を48時間と確認したものの、その枠内では処理できない仕事が学校現場では山積みになっているが、この実態を文部省は無視してきたことになる。
強制されないはずの残業が強制され、しかも残業代も支払われず、文部省も実態から目を背ける状況のなかで、超勤訴訟が相次いだわけだ。当然の事態である。
超勤訴訟では教員側の優勢が続いていくのだが、その流れに強権をもって棹を差してくるのが自民党文教族というわけだ。
次回はそこについて、もう少し詳しく触れていきたい。
- 1
- 2