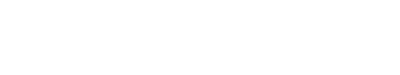独自の道を歩んだイギリスの水道事業 ~完全民営化の黄信号~
日本の水が危ない⑭
■イギリス――完全民営化の黄信号

イギリスはPPPやPFIの本家とも呼べる。1980年代のサッチャー政権の改革は、「水道民営化」を含む各国での規制緩和と「小さな政府」を基調とする改革の呼び水となった。
しかし、水道事業に関しては、イギリスは独自の道を歩んできた。イギリスでは1989年、全国の上下水道が地域ごとに分割され、当初、30社以上が水道事業に参入したが、経営統合や吸収合併が繰り返された結果、2018年現在で19社がシェアのほとんどを握っている。さらにその民間企業に経営権だけでなく設備などの所有権も譲渡された。フランスやアメリカなど多くの国ではコンセッション方式が中心だが、完全に民営化されたイギリスのスタイルは、世界的にも珍しいものだ。
水道事業が100%民営化されたイギリスでは、再公営化は一件も発生していない。その意味で、イギリスの方がフランスやアメリカより安定している。
ただし、それはコンセッション方式より完全民営化の方がパフォーマンスがよいから、というより、イギリスでは公的機関による監督がフランスなどより発達しているから、とみた方がよい。イギリスの場合、水道各社はそれぞれの区画で設備まで独占するだけに、政府も強い監督権をもっているのだ。
イギリスでは水道が民営化された1989年、料金を監督する水道事業規制局、上水道の水質検査に責任を負う飲料水検査局、河川などの汚染を監視する環境局が、それぞれの管轄省からエージェンシーとして独立し、水道事業を監督する法的権限を与えられた。フランスの地域河川流域委員会が民間事業者の決定に介入する法的権限が与えられなかったのと対照的に、イギリスのこれらの機関は問題ある事業者に改善命令を出せる。
一例をあげよう。1998年から1999年にかけて全国の水道事業者が「EUの新基準に合わせるため」という理由で一斉に水道料金を平均46%引き上げた際、水道事業規制局は価格引き上げが行き過ぎと判断し、12・3%までに抑えるよう命令した。イギリスとフランスを比較調査したブロック大学のモハメド・ドレ教授らのグループは、こうした実質的な監督が可能な独立機関の有無が両国の「水道民営化」のパフォーマンスの差になり、ひいては利用者の満足度の差を生んだと結論している。
- 1
- 2
KEYWORDS:
『日本の「水」が危ない』
著者:六辻彰二
昨年12月に水道事業を民営化する「水道法改正案」が成立した。
ところが、すでに、世界各国では水道事業を民営化し、水道水が安全に飲めなくなったり、水道料金の高騰が問題になり、再び公営化に戻す潮流となっているのも事実。
なのになぜ、逆流する法改正が行われるのか。
水道事業民営化後に起こった世界各国の事例から、日本が水道法改正する真意、さらにその後、待ち受ける日本の水に起こることをシミュレート。