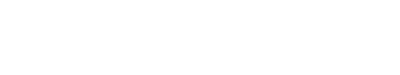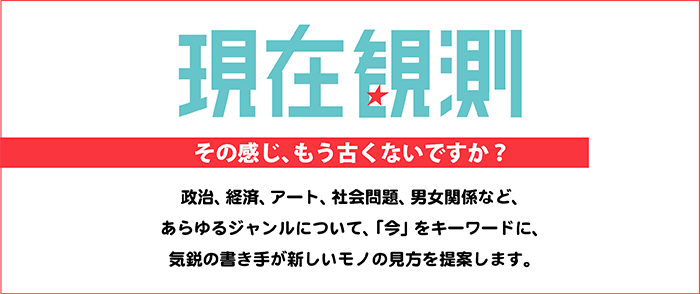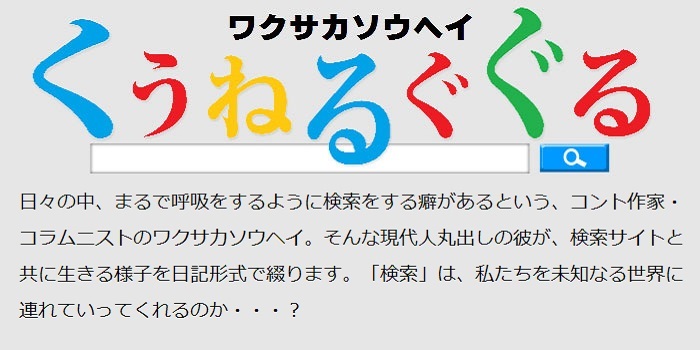Scene.2 伝説を作るんだぜ!
高円寺文庫センター物語②
こんな有り様だから、彼ら自体が高円寺のマーケットを探るリサーチ対象にもなりえると踏んだ。
つまり、彼らが面白がることで店づくりをすれば受け入れられるはずだ! 商品管理のノウハウを教えたら、各分野の担当を任せればいい。
バイトの条件はまず高円寺在住。儲けの少ない本屋のネックは人件費、時給はサービス業でも最下位レベルなので交通費まで出せないというのが本音だった。
本屋の備品は一にも二にも節約が大原則。袋やブックカバーも円より下の銭の単位で考えざるを得なかった。ケチではなくて、本屋稼業には大切なことと教えるしかない。
バイト先でありながら、高円寺文庫センターは彼らの学校でもあったと思う。自分の子供たちと変わらぬ年代と付き合うのだから、親代わりのつもりで彼らと接していた。
本や雑誌の流通の仕組み、出版社や取次という問屋が介在する意味など、本屋の現状をことあるごとに語って聞かせた。本屋の環境を理解してもらわないと、と考えた。なかには将来は出版社で働きたい子もいるわけだから、書店・出版業界の基礎知識は教えておかないとならない。
新店舗に並べる本のセレクトの基本はサブカルチャー。これまでの実験店舗で確証を得ていたからそこは揺るがない。
実験店舗的に、あずま通りから早稲田通りに出る手前に7坪の店を出していた。

ここに出店の際には、帰宅通行人の動向を注視して市場を確認したものだ。
その店の界隈と、早稲田通りを越えた中野区の一帯の住人があずま通りを使うと踏んだ。その主流は学生に専門学校生、独り暮らしのサラリーマン。可処分所得は、好きなモノにはお金を使う人々だ。
その市場把握が功を奏して実験店舗も成功。駅近くへ進出の機会を窺っていたところに舞い込んだ物件だったのだ。
どんどん面接していこう。
「内山くん、ちょっとお歳がいってるけどバンドマンなの?」
高円寺文庫センター伝説が産声を上げたのは、この出会いからだった。いまや、高円寺バンドシーンのレジェンドとなっている「ミサイル兄弟」のヴォーカル、それが彼だった。
忌野清志郎さんに憧れてバンドを始めただけあって、カラオケでRCサクセションナンバーを熱唱させたら右に出るものなし! いまでもバンドを続けつつ、高円寺駅の高架下のスーパーで揚げ物を担当するバイトを続けている。
「佐野さん、セールスポイントはなんなの?」
伝説を作る仲間とは、遭った瞬間に電気パルスが走るものらしい。
この後、「りえ蔵」と呼ばれるミニチュアのように小さい女の子との出会いもその一つだ。静岡の高校を出て高円寺にやってきた同級生の鶴ちゃんと共に、伝説の半分を支えてくれた。
ROCK感を漂わせつつも冷静沈着な片腕として、ボクの迷いを一喝したりと、店長としての判断を後押ししてくれた最高のアドバイザーとなった。
午前10時半ごろに開店、閉店は夜中の12時半か1時だった。
高円寺は夜型の街だ。午前中はろくにお客さんが来ない。売上の大半は、午後6時以降で夜中には酔っぱらいのお客さんもが相手だった。
昼間のうちに、仕入れた商品の店出しと飾りつけを終わらせる。売れ残った商品の返品作業や、独自で問屋に買い付けにいくのも昼間のうちに済ませる。
基本的に本屋の仕入は、取次店という問屋が見計らって送ってくる。多少はお店の個性を配慮されても、それはボクらのポリシーとまったくかけ離れていた。
よく言われる、どこを切っても同じ金太郎飴書店。ボクらは、それを拒否して独自に注文することと、中小の問屋が集まる神保町へ仕入に行ってオリジナリティを出すことにした。
それは手間も時間もかかることなのだが、高円寺に合わせた本屋を作り続けようとしたら背負わなければならないことだった。
そんな苦労が実を結び始めたのか、雑誌に次々と紹介され始めるようになった。
開店から数年後のことだ。「カリスマ書店店長」と書かれ紹介されたが、ボクには不本意でしかなかった。サブカルチャー&ロックテイストの主力は、助けてくれるバイトくんたちだと思っていたからだ。
店長としては、店のプロデュースとみんなをまとめ上げる調整能力くらいの力量だと思っていたので、お客さんに来てもらえるPRになるならと広告塔に徹していたつもりでいたのだが。
テレビ東京のある番組が取材の際に、高円寺と言えば阿波踊りだからと「店長、店の前で踊ってください」には、そこまでは違うだろとお断りさせていただききました。
お店のPRは本絡み、自分がピエロのようにイヂられるのは願い下げ。