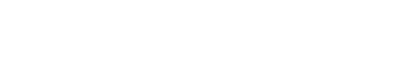発病、事故、解雇…偶然の不幸な出来事から救われる手だてはあるのか?【沼田和也】
『牧師、閉鎖病棟に入る。』著者・小さな教会の牧師の知恵 第16回
人を傷つけてはいけないのかがわからない少年。自傷行為がやめられない少年。いつも流し台の狭い縁に“止まっている”おじさん。50年以上入院しているおじさん。「うるさいから」と薬を投与されて眠る青年。泥のようなコーヒー。監視される中で浴びるシャワー。葛藤する看護師。向き合ってくれた主治医。「あなたはありのままでいいんですよ」と語ってきた牧師がありのまま生きられない人たちと過ごした閉鎖病棟での2ヶ月を綴った著書『牧師、閉鎖病棟に入る。』が話題の著者・沼田和也氏。沼田牧師がいる小さな教会にやってくる人たちはどんな悩みをもっているのだろう? 自分の身の回りで偶然に起こる不幸な出来事から私たちは救われる手だてを持っていない。むしろ自分だけで解決しなければならないような厳しさが増している時代だ。そんなときに「信仰とは救いになるのか?」「信仰するとはどういうことなのか?」。沼田牧師が書きとめたその考え方とは。

新生児に名前をつけるまでに、何日かあける文化をもつ地域は世界各地にある。由来には諸説あるだろうが、その一つに、現代のような医療が確立する以前は、新生児の死亡率が高かったことが挙げられるだろう。
つまり、生まれたばかりの子どもが亡くなったとしても、まだ名前がついていないその子を、人間社会の一員とは見なさないわけである。人間になる前に神仏あるいは精霊の世界に還っていったと考えることで、親は子どもの死を受け容れることができる。名前をつけるまで数日あけるというのは、新生児が安定して育つのか、衰弱して死ぬのかを見きわめるための猶予期間でもあったのだ。
もちろん近代以前の社会、あるいは現代のいわゆる発展途上国であっても、生まれたばかりの子どもを喪う悲しみはわたしたちと変わらないだろう。ただ、たとえば現代の日本のように、多くの子どもたちが当たり前のように成長していくなかで「なぜわたしの子どもだけが死んだのか?」と悲しむことは、子どもの死が頻繁に起こりえる時代や地域で子どもを喪って悲しむこととは、事情が異なってくると思う。
これは死産の受けとめに限ったことではない。神仏や精霊などの外部世界を持っていないということは、自分の身の上に起ることはすべて自分で納得するしかないということでもある。現代の日本ではたしかに古代や中世のようには人が死ななくなった。道端に行き倒れの死体が転がっていることも滅多にない。
そのいっぽうで、とつぜんの発病や事故との遭遇は、今でも頻繁に起こる。頑張ってきたにもかかわらず、不況のあおりで解雇されてしまうこともある。自分の力ではどうすることもできないことに、人は時代に関係なく翻弄される。生きているかぎり納得のいかないことがいくつも起こるのである。わたしたちはこれを、むかしの人々のように外部からの祝福や呪いのせいにすることなく、まったくの偶発的事件として受け容れることを強いられる。もはや自分の外部はない。自分の内部で、すべて解決しなければならないのである。
「たとえ現代であっても、宗教を信じていればそういうことは起こらない」とはよく言われる。けれども、ことはそう単純ではない。宗教を信じる人間、たとえばキリスト教徒であるこのわたしも、現代の社会に生きている。わたしの信仰はおそらく、ザビエルによってキリスト教が伝来した当時の、キリシタンのそれとはかけ離れている。戦国時代のキリシタンは自らに起こる幸不幸を、かなり直接的に神に結びつけていただろう。言い換えれば、幸不幸に対して神が力を持っていないと思えば、彼らは転んだ(棄教した)だろう。