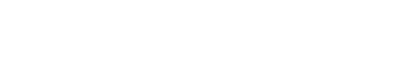不便で、手間もお金もかかるからこそ味わうことのできる「幸福」について【沼田和也】
『牧師、閉鎖病棟に入る。』著者・小さな教会の牧師の知恵 第17回
人を傷つけてはいけないのかがわからない少年。自傷行為がやめられない少年。いつも流し台の狭い縁に“止まっている”おじさん。50年以上入院しているおじさん。「うるさいから」と薬を投与されて眠る青年。泥のようなコーヒー。監視される中で浴びるシャワー。葛藤する看護師。向き合ってくれた主治医。「あなたはありのままでいいんですよ」と語ってきた牧師がありのまま生きられない人たちと過ごした閉鎖病棟での2ヶ月を綴った著書『牧師、閉鎖病棟に入る。』が話題の著者・沼田和也氏。沼田牧師がいる小さな教会にやってくる人たちはどんな悩みをもっているのだろう? 誰もが人知れずもっている幸福への希求にたいして、沼田牧師の視線は遠い過去から遠い未来へと「幸福への実感」を橋渡しているように思える。

‘彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。 ‘ヨハネの黙示録 21:4 新共同訳
まだまだ感染爆発が続いていた頃、家にじっとしていることに耐えられなくなったわたしは、散髪に行った。店員に案内されて、椅子に深く腰を下ろす。ひとまずはリラックス。すると奥の客が店員と会話するのが聴こえてきた。「今日の感染者、30人以上だって!」。まだ出かけるのは早かったかと不安になる。
カットクロスを首に巻かれ、「苦しくないですか?」「だいじょうぶです」。そんないつものやりとりをしていたら、隣の椅子にちいさなお客さんが、ちょこんと座った。3歳くらいだろうか。もっと幼いかもしれない。よくお店に来て慣れているのか、母親は息子を座らせると店員に「あとで迎えに来ます。次は娘もお願いします」とどこかへ去った。
わたしは父に連れられ初めて散髪に行ったときのことを、懐かしく想い出した。頑固おやじが店主で、見習いがいた。頑固おやじを覚えているのは、そのときの一回きりだ。父によれば、おやじはその後体をこわし、見習いに店を譲り、やがて亡くなったのだという。その後わたしは、見習いであったその男から長いあいだ髪を切ってもらうことになる。
初めての散髪はさんざんなものであった。医者や歯医者に行くのと同様、わたしにとって散髪の椅子に独りで座り、白い服の男に覗き込まれるのは恐怖でしかなかったらしい。わたしの髪を切ってくれたのは見習いのほうだったと思う。わたしが号泣するごとに、困惑した彼が鋏を引っ込めたのを覚えている。横で父があやしてくれた、かすかな記憶もある。
見習いであった頃の彼の記憶は、ほとんど残っていない。思い浮かべる彼の姿といえば理髪店の立派なあるじであって、その頼りがいある技術と饒舌である。彼はいかにも頑固おやじな先代とはちがって柔和な物腰であり、バリカンは滅多に使わず、繊細な鋏さばきで襟足のグラデーションを仕上げてくれた。そして幼いわたしにも丁寧に剃刀をあててくれたものである。首筋をやられるときはくすぐったくてたまらなかったが、あとで肌がつるつるになるのが不思議で仕方なかった。
KEYWORDS:

※上のカバー画像をクリックするとAmazonサイトへジャンプします