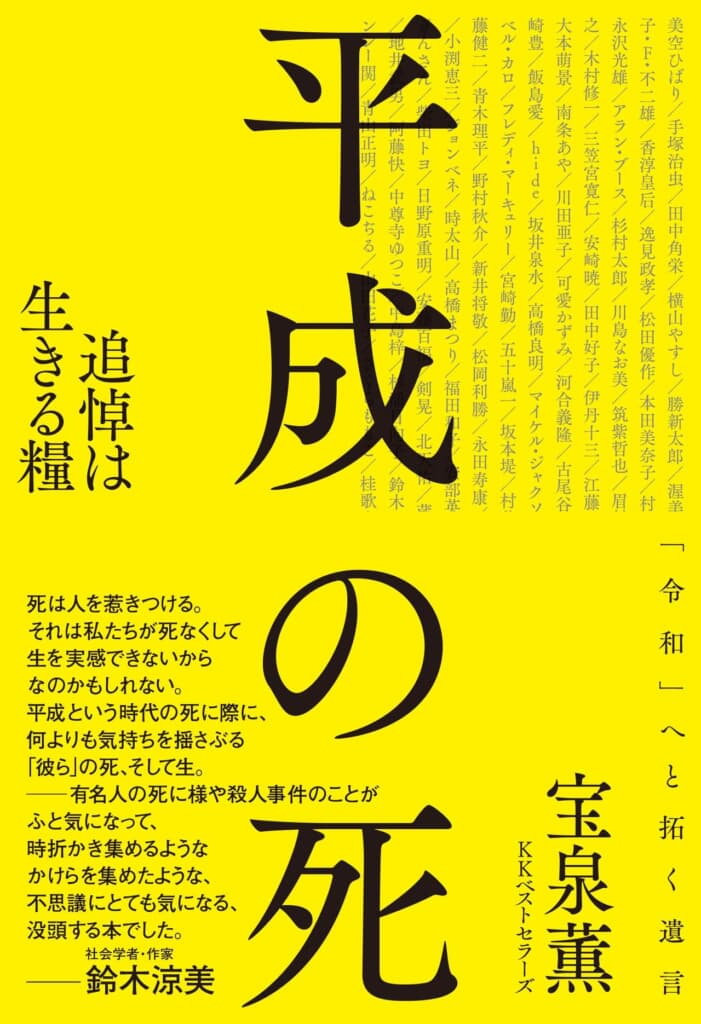有名人の「顔」に厳しかったナンシー関のテレビ批評は現在の言葉狩りルッキズムに耐えられるか【宝泉薫】

今年1月、文春オンラインに「《「美人」「主人」「奥さん」は使わないほうがいい?》断筆宣言の筒井康隆氏が考える現代の“言葉狩り”」という記事が掲載された。そのなかに、こんな文章がある。
「聞くところによると、いまは『美人』『美女』という言葉は『ルッキズムだ』ということで、使いにくくなっているそうですね。このルッキズムというのも変な言葉ですが、外見至上主義とか、外見にもとづく差別や偏見を意味するのだとか。(略)私に言わせれば、その程度でワーワーと騒ぎ立てるほうがおかしい。それこそ本当の言葉狩りになってしまいます」
そんな筒井は29年前の時点で「小説に美人が登場しても差別につながるという常識が一般化した社会を想像する」と書いていた。言葉狩りという問題に人一倍敏感な、この作家ならではの虫の知らせだろうか。
実際、それが杞憂ではなかったことを示すような騒動も起きている。北京五輪のクロスカントリーで銅メダルを獲得した米国の女子選手について、米紙が賞賛した記事がバッシングされたのだ。その原因となったのは、こんな文章である。
「スポーツにおいて、とても多くの女性ががっしりとした肩や太ももを有しているが、ディギンズはレーススーツを着ていると、まるで妖精のように見える。彼女のどこにそんなパワーが秘められているのかは分からないが、たしかに存在するのだ」
これが他の選手だけではなく、彼女本人をも傷つけるものだとする批判が飛び出した。もはや、容姿について語ること自体が悪とでもいうような風潮が、一部とはいえ生まれ始めているようだ。
褒めてもダメなら、けなせば当然叩かれる。昨年、大リーグでも活躍した野球評論家・上原浩治をめぐる騒動を覚えている人もいるだろう。テレビ批評などで知られる作家・麻生千晶がネットニュースのコラム(ここでの筆名は黄蘭)で解説者としての上原に言及。「筆者は彼の顔が苦手で、余り好意をもっていなかった」としながらも「引退後の上原は美醜に関係がなくなり、発言もしっかりしてきた」「単純に面白かった」と評価したのだが――。
これに対し、上原本人が「ブサイクでも野球頑張りました」「自分のことを言うのはまだ我慢します。ただ、容姿について、顔が苦手とか、好意を持ってないとか…親に対して失礼かと思うんです」と反発。世間の空気もそれに味方する流れになった。結果、そのコラムだけでなく、彼女のすべての文章がそのニュースサイトから消されたのである。
そこでふと、気になったのがコラムニストで消しゴム版画家だったナンシー関のことだ。20年前に亡くなった彼女もテレビ批評を得意にしていたが、その芸風において容姿に関する審美眼も大いに活用していた。
たとえば「人前で歌ってはいけない槇原敬之」と題されたコラムがある。世に出た頃の槇原の容姿がテレビ向きでないとして「表現的に不適切かもしれないが、人種が違う、そこに一緒に並ぶんじゃない、という感じなのだ」と書いた。このコラムでは、槇原以外にも大事MANブラザーズバンドや沢田知可子、楠瀬誠志郎について同様の言及をしている。
ちなみに、彼女は子供の頃、郷ひろみの大ファンで、
「小学生の中学年ぐらいまで、ほんとに好きだったんです。部屋にポスター張ってたし」(週刊朝日)
と、明かしている。物書きになってからも、ブレイク当時の神田うのの容姿を高く評価するなど、なかなかの美形好きだった。とはいえ、プロレスラーや凶悪犯罪者の容姿についてもその個性をいろいろ面白がっていたから、必ずしも美醜だけを基準にしていたわけではない。実際「歌番組不在の時代が生んだ『人前で歌うべきでない』歌手たち」というコラムでは、人前で歌っていい顔について「『歌う』という娯楽の一種で人にお金を払わせる、そのことに疑いを持たせない顔」だと定義づけている。華の有無とか笑えるかどうかなどをひっくるめた独自の基準を持っていたのだ。そういう意味で、彼女の死後、かつての冴えない好青年的イメージから怪しい芸術家的イメージに変化した槇原のことなら「人前で歌っていい」と思えたかもしれない。