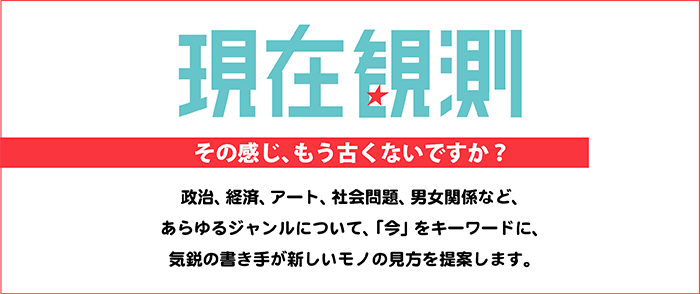消費される「お天気キャスター」という職業
現在観測 第23回
形骸化する気象予報士という“国家資格”
気象予報士という資格を考えるとき、気になるのは、放送メディアにおける年齢やジェンダーのバイアスだけではない。気象予報士という国家資格の地位そのものも気になっている。
今年は、国家資格としての気象予報士制度が誕生して22年を迎える。気象予報士試験を運営する財団法人気象業務支援センターのまとめによると、先日の3月11日の合格者発表で、合格者は計9843人(通算45回)にのぼった。最近は毎回120〜130人ほどが合格することを考えると、1万人超えは目前だ。
人数ばかりが増えていく予報士だが、課題は、資格を生かした職業に付いている人の割合が、驚くほど少ないことだ。気象庁の2013年のアンケート調査によると、現在の業務について尋ねた質問に、「気象に関係ない業務に就いている」と答えた人は約7割にのぼった(回答者数2913人)。すっかり趣味の資格と化して久しい。
なぜそうなったのかについては、様々な要因が考えられるが、私はそもそも、資格を所管する気象庁自体が、気象予報士を「プロ」として扱ってこなかったことも要因の一つであるように感じている。気象庁にいれば予報業務に資格は必要ないため、気象予報士を持つ職員はそう多くない。そんな「持たなくてなくてもいい」という空気が、資格の位置づけを曖昧なままにしてきたのではないだろうか。
気象予報士をめぐる新しい動き
そんな気象庁も、新年度から単年度のモデル事業ではあるが、地方自治体の防災や危機管理の部局に対し、梅雨や台風の多い時期の6月〜10月に気象予報士を常駐させることになった。
気象庁情報利用推進課の説明によると、シビアな天候が予想される時に、避難勧告や避難指示を出す首長や、住民に適切な情報を提供する部局職員のために、専門情報を解説をする情報の橋渡しが主な役目だという。
こうしたリスクコミュニケーションの一端を担う役目は、気象庁職員が人事交流で地方自治体に所属して行う例はあるが、今回の要員は、あくまでも「気象予報士」。制度開始以来、初めて公式に「気象防災のプロ」として扱う方向に転換をしたといってもよいだろう。
4月始めには事業者が決まり、派遣先の6自治体も決まる予定だ。
どのような気象予報士が、自治体防災の現場で活躍することになるのか。その適正や人物像、具体的な自治体は、4月以降、大学教授や地方自治体職員、気象庁OBらで構成する検討会で話し合われることになる。一部関係者の間では、議論はすでに始まっているとも聞く。
自治体幹部と渡り合うだけの技量や作法が必要とされる現場の特殊性を考えると、現実には、行政の事情に詳しい人物でなければ勤まらない。新年度からの派遣は、気象庁OBや気象防災のコンサルタントとして長くキャリアを積んできた気象予報士に絞られるだろう。
まだその数は少ないが、地方自治体の防災部局で働く気象予報士はいる。
2年前から出身地の群馬県前橋市で、危機管理課の危機管理アドバイザーを務める栗原弘一さんは、気象庁や各地の気象台勤務を経て、退官時は東京管区気象台長を務めた経歴を持つ。
そんな栗原さんが実際に市で働き始めてから、驚いたことがあるという。
「1都16県を管轄する東京管区気象台長だったなんてことよりも、気象予報士という肩書きの方が、ずっと市民に受け入れてもらえるんです。警戒態勢の時、市長に呼ばれて解説を求められた際も、『気象予報士の栗原さん』と言われました。気象予報士という資格は、テレビの影響なのか、それだけ社会に定着しているんです」
長らく趣味の資格、あるいは持っていなくても困らない資格に甘んじてきた気象予報士の位置づけを、いま、しっかりと専門職として見直すべき時期にきているのではないだろうか。
- 1
- 2