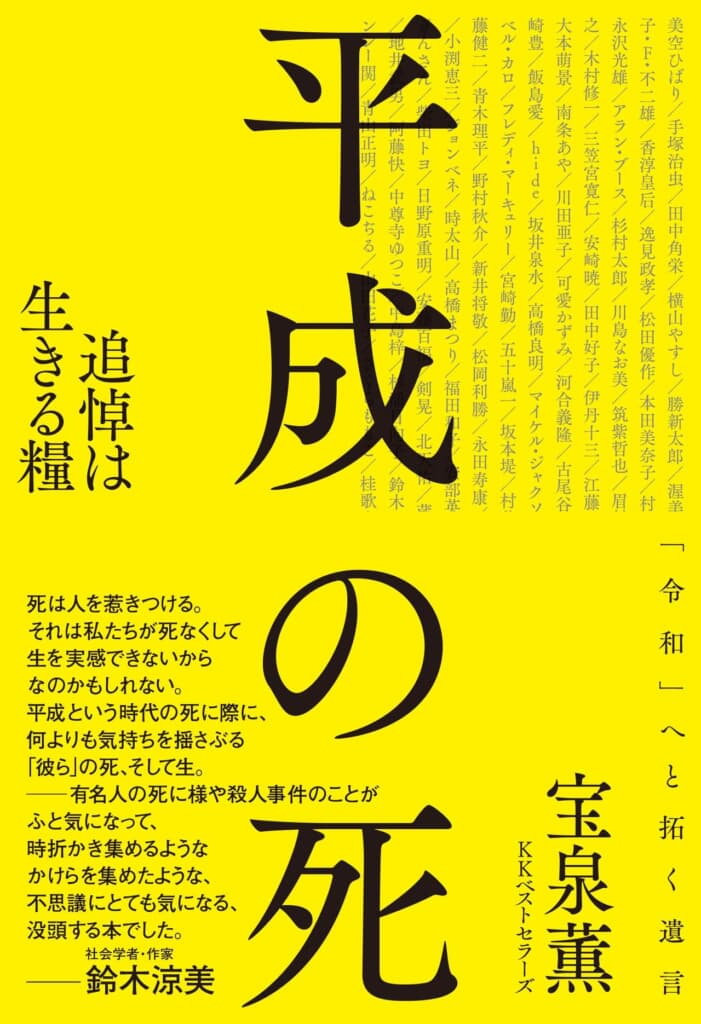「自分の晩年を20代半ばに想定していた詩人・立原道造。日本の近代文学は結核によって発熱した」1939(昭和14)年とその前後【宝泉薫】
【連載:死の百年史1921-2020】第15回(作家・宝泉薫)
死のかたちから見えてくる人間と社会の実相。過去百年の日本と世界を、さまざまな命の終わり方を通して浮き彫りにする。第15回は1939(昭和14)年に夭折した立原道造など、明治から昭和前期にかけて繰り広げられた結核と文学の「蜜月」を振り返る。

■1939(昭和14)年
結核と文学、死の味のする生の幸福
立原道造(享年24)
かつて、結核は不治の病だった。また、工業化が猛スピードで進む劣悪な都市環境で蔓延する傾向があり、日本では明治から昭和初期にかけて猛威をふるった。なかでも目立つのが、文学関係者の夭折だ。暗くじめじめした狭い部屋で、古本に囲まれ、ろくなものも食べず、不規則な生活をしがちなのが災いしたのだろう。
この連載が扱う以前の時代には、樋口一葉や石川啄木が20代なかばで世を去ったし、すでに見てきた時代では、1927(昭和2)年に詩人の八木重吉が29歳で亡くなった。また、この年、鬼籍に入った徳富蘆花(58歳・心臓発作)は、薄幸な美女が結核で悲劇的な死を遂げるベストセラー小説『不如帰(ほととぎす)』の作者だったりする。
なお『不如帰』というタイトルは、ホトトギスが鳴きながら血を吐いたという中国の故事が由来だ。また、ホトトギスは「子規」とも書く。それゆえ、俳人の正岡子規は喀血をして肺結核と診断されたことをきっかけに、子規と号した。
その後、子規は結核による脊椎カリエスにも苦しみ、寝返りも打てないほどの激痛にさいなまれるが、34歳で亡くなるまで、俳句・短歌の改革を過激に推し進めた。重病人だからこそ、対抗勢力がひるんでくれるのだとも語っていたという。

1932(昭和7)年には、梶井基次郎。結核と文学がある意味蜜月的なことに若くして気づき「肺病になりたい」と叫んだりしたという猛者だ。初志貫徹というべきか、この病に罹患し、代表作『檸檬』をはじめ、結核の影が見え隠れする小説を多く残した。遺作となった『のんきな患者』は「吉田は肺が悪い」という一文で始まり、こんな一文で終わる。
「しかし病気というものは決して学校の行軍のように弱いそれに堪えることの出来ない人間をその行軍から除外してくれるものではなく、最後の死のゴールへ行くまではどんな豪傑でも弱虫でもみんな同列にならばして嫌応なしに引摺ってゆく――ということであった」
この作品が初めて商業誌『中央公論』に掲載されたものの、翌月には31年の生涯を閉じる。そんな梶井がかつて「肺病になりたい」などと叫んだことを後悔したかどうかはさだかでない。ただ、当時の文学青年にとっても、ほとんどの人の場合、結核は恐怖だった。
たとえば、室生犀星は自伝的小説の『性に目覚める頃』のなかで、文学青年仲間が結核で夭折したあと、こんな本音を綴っている。
「いつか表が咳入っていたとき、蚊のような肺病の虫が、私の坐ったところまでぱっと拡がったような気のしたことを思い出した。そのときは、なに伝染るものかという気がしたし、友に安心させるためにわざと近近と顔をよせて話したことも、いま思い出されて、急に怖気がついて来て、とりかえしのつかないような気がした」
幸い、室生は結核にはかからず、72歳まで生きて旺盛な文学活動を続けた。

KEYWORDS:
オススメ記事
-

日本史上初の痩せ姫⁉「鎌倉殿の13人」の大姫(南沙良)は「真田丸」茶々(竹内結子)の悲劇性を超えるか【宝泉薫】
-

「妻を神がかりにした北一輝、夫によってミューズにされた高村智恵子。愛の作用は不可思議だ」1937(昭和12)年 1938(昭和13)年【宝泉薫】
-

有名人の「顔」に厳しかったナンシー関のテレビ批評は現在の言葉狩りルッキズムに耐えられるか【宝泉薫】
-

フィギュアスケート版「女工哀史」ワリエワ騒動に見るロシアという国の強さと徒労の美【宝泉薫】
-

美談と奇談。「英雄に祭り上げられたハチ公」と「阿部定に局部を切り取られた男」は最期に何を思ったか 1935(昭和10)年 1936(昭和11)年【宝泉薫】