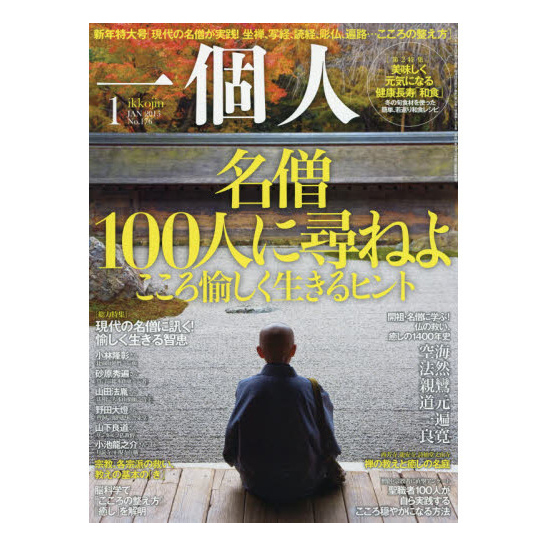意外と深い一休さんの「とんち」
人の目を気にせず、自由に生きた風狂の僧
「抱擁と接吻」が大好きな一休さん
当時、京の五山はもとより、禅宗寺院全体が急速に俗化し、頽廃の色を濃くしていた。こぞって名利を漁り、貴族趣味の道楽にふけったほか、商売にいそしむ売僧(まいす)や印可状を安売りしてするニセ師家も当たり前だった。それでいて体裁だけは気にする。一休はそんな偽善を徹底的に嫌い、批判する一方、みずからは破戒僧を自演した。
臨済宗の本山である大徳寺から要請され、しぶしぶ山内の如意庵に止住したときも、わずか10日ほどで逃げ出し、「後日、この一休を訪ねられるならば、拙僧は魚屋か酒屋か遊郭にいるだろう」という退去の辞を残している。事実、肉を喰らい、酒を飲み、女犯を犯すなどして傍若無人に世俗を闊歩した。「婬坊に題す」という詩では〈私には抱擁とか接吻とかの楽しみがあり、いまや命がけの求道心などない〉とまで書き綴っている。
当然、禅林からは異端視されたが、一休は「持戒は(来世に)驢馬となり、破戒は(来世に)人となる」と言い放った。「ガンジス川の砂の数ほどの戒律は人の霊妙な心の動きを弄ぶだけ」というのが一休の境涯である。
では、一休は世俗化した多くの僧侶と同じく「糞虫」だったのか。破戒をきわめた一休の行為は「逆行」とも呼ばれている。いわば戒律を守り、修行の道程を踏み外さず実践する「順行」に対し、あえて戒を破り、修行を否定することで逆に仏教の本質を明らかにする方法論である。
一休は、若きより死を賭して大悟を徹底させ、そののちは修行そのものを捨て、あえて濁世に分け入った。寺で語られる教説や悟りではなく、人間社会の現実をふまえ、臨機応変、融通自在な禅風を目指したのである。
禅の古典『臨済録』によれば、人間一人ひとりの内に、位のつけようがない真の人間がすんでいるという。あらゆる立場は一切関係なく、ましてや修行も悟りも関係なく、生まれたまま、そのまま具わる立派な主体性があるという。それを「一無位の真人」という。
一休の面目はそこを明らかにすることにあった。お前は周囲の環境や立場にとらわれず、本来の自分を生きているか、お前は自分の主人公になっているか。一休は自身の生き方を通じ、我々にそう問うているのだ。
- 1
- 2