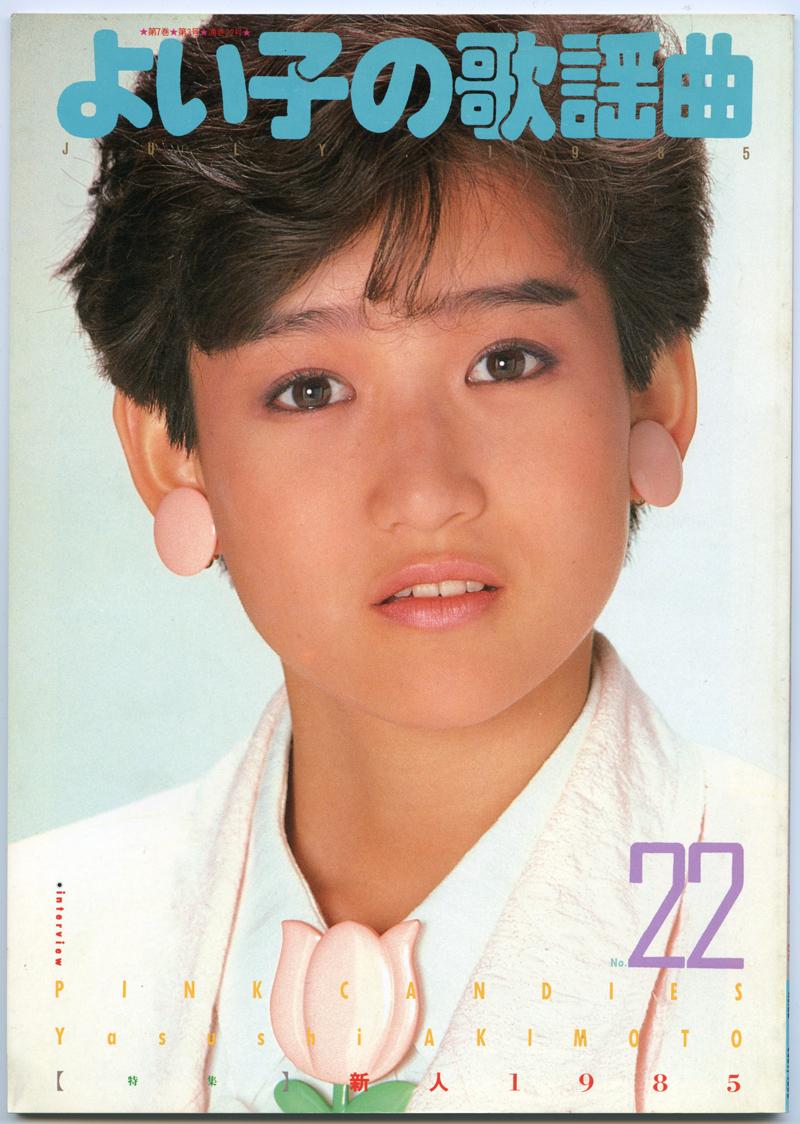終戦・原爆モノは役者の人生を変える。三浦春馬が戦後75年の節目に「太陽の子」をやった意味【宝泉薫】

8月は戦争の月だ。二度の原爆、ソ連の侵攻、第二次世界大戦の終結、進駐軍の上陸といった出来事が続いたせいで、メディアも世間(?)も戦争振り返りモードとなる。
熱心なのはNHKで、ドラマやドキュメンタリーを毎年放送。今年のドラマは「軍港の子~よこすかクリーニング1946~」(10日)と「アナウンサーたちの戦争」(14日)の2本だった。
ただ、以前に比べ、地味というか、下火になってきた印象もある。それもそうだろう。終戦から78年がたち、実際に兵隊として戦った人はもうほとんど生き残っていない。かつての「鬼畜米英」ともすっかり仲良くなり、広島サミットでは先進国の首脳たちが原爆資料館を訪れた。「人の噂も七十五日」というが、それこそ75年くらい過ぎれば、国を挙げて殺し合った恨みの記憶も薄れていくのかもしれない。
なお、終戦から75年目にはコロナ禍が起きた。世界のあちこちで戦争レベルの死者を出したこの3年半が、大戦の記憶をさらに風化させたともいえる。
ただ、長年にわたって作られてきた終戦・原爆モノのドラマや映画は、出演した役者たちの人生にも影響を与えた。ここではそのいくつかを振り返ってみたい。
まず、草創期の傑作として名高いのがTBSのドラマ「私は貝になりたい」(58年)だ。
市井の平凡な床屋が召集され、上官の命令に従って捕虜を負傷させたところ、それが戦後になって告発され、戦犯として処刑されてしまう。タイトルは、その遺書に記された、
「もう人間には二度と生まれてきたくない。私は貝になりたい」
という言葉からとられたもの。その悲劇と、主役を演じた芸人・フランキー堺の飄々とした芝居のギャップが絶妙で、深い感動をもたらした。近年では、中居正広主演による映画版などもあるが、減量による役作りなどで悲壮感が強調されすぎていた感も。もともと、芸人が演じて成功した作品だけに、国民的アイドルには向かなかったのかもしれない。なお、フランキーはこのあたりから役者に転じ、人情味あふれる芸風で親しまれていった。
芸人が演じて成功したといえば「さとうきび畑の唄」(03年・TBS系)というのもある。
大阪から沖縄に移り住み、写真館を営む主人公を明石家さんまが演じた。笑わせるのが何より好きな男が召集され、戦死するという筋書きで、やはり芸人ならではの芝居が効果を発揮。ただ、さんまが人情系の役者に転じることはなく、むしろ、戦争モノならではの苛酷な撮影経験などを笑いのネタにしたりしている。それでも、彼のような人までやってみたいと思わせる魔力が戦争モノには潜んでいるのだろう。
まして、真面目な優等生というか、デビュー時から正しさのようなものを背負ってきたような女優だと、積極的に取り組みたくもなるはずだ。