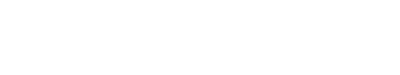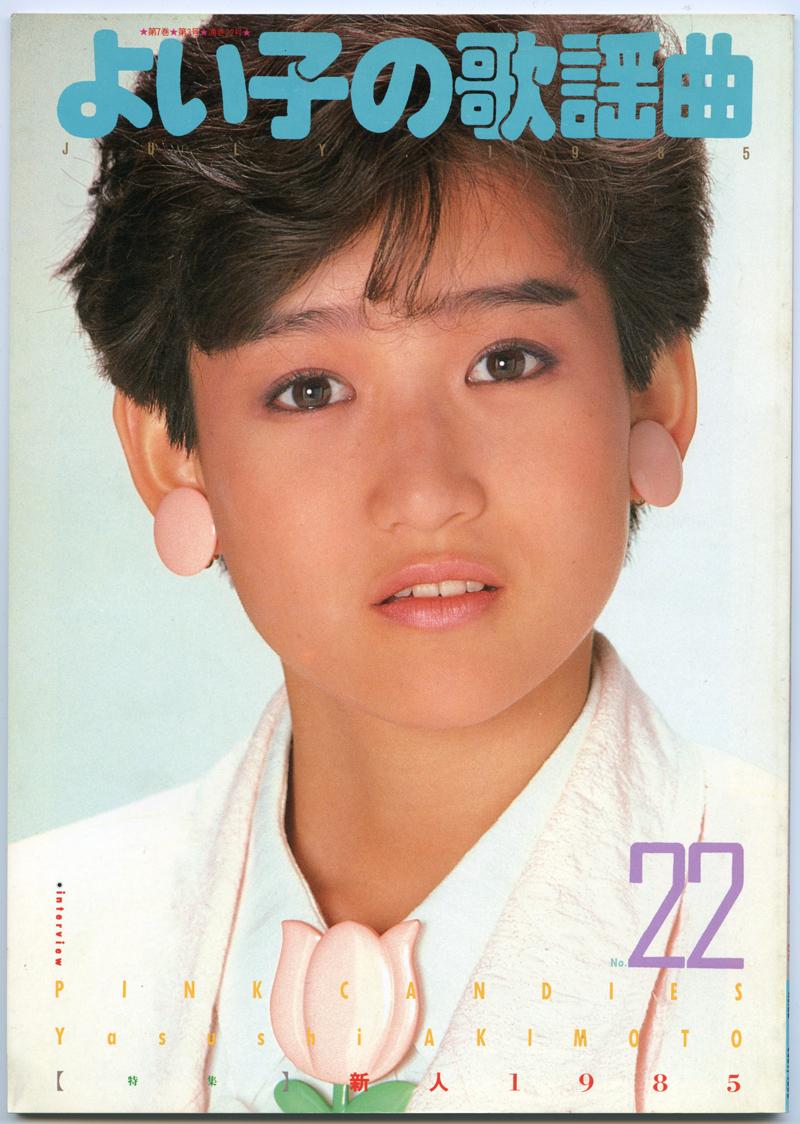終戦・原爆モノは役者の人生を変える。三浦春馬が戦後75年の節目に「太陽の子」をやった意味【宝泉薫】

とまあ、のんの場合は役柄とのシンクロがプラスに働いたわけだが、そうともいえないケースもある。20年の8月15日に放送されたドラマ「太陽の子」(NHK)と三浦春馬との関係だ。
彼はこの作品で主人公の弟を演じたが、放送されたとき、すでにこの世の人ではなかった。その28日前に自ら命を絶ったからだ。そして、劇中でも自殺を図るシーンがあった。彼が演じた役は、病気で郷里に帰された陸軍兵。戦死した仲間たちに対して「自分だけがどうしてここに」「おれだけ死なんわけにはいかん」という思いにさいなまれてのことである。
そんな葛藤を演じるにあたって、彼は死の10日前、このドラマの記者会見でこんな話をしていた。
「今、僕たちはいろんなことで、人生を諦めたいと思う瞬間もある。けど、その空しく生きた一日が、当時あれほど生きたいと思っていた一日。一日は変わらないじゃないですか。そんなことを胸に、生きていきたい」
あとになってみれば、彼自身が生と死のあいだで揺れ動き、活路を求めて葛藤していたようにも思われる。そんな人が戦争モノでこうした役を演じることは、かなりしんどく、身を削り心をすり減らすような作業だったのではないか。
ただ、彼のおかげで、作品は戦後75年という節目にふさわしいものになった気がする。生きづらさを抱える若者の葛藤はあの頃も今も変わりないこと、それだけにむしろ、あの頃を特別視しすぎるような戦争モノのあり方はそろそろ見直す時期に来ているのではとも思わせてくれたからだ。
また、戦後が長くなるにつれ、戦争モノもかなり変質してきた。「マー姉ちゃん」(79年)や「本日も晴天なり」(81年)「おしん」(83年)といった昭和の朝ドラの再放送などを見ていると、戦争の扱い方が意外なほど明るく朗らかなことに気づかされる。もちろん、悲惨な部分も描かれるのだが、それを乗り越えて前に進もうとする日本人のたくましさも十分に感じられ、励まされるのだ。おそらく、実際に戦争を経験した人がまだまだたくさんいて、制作に関わっていたからだろう。
しかし、作り手も見る側も戦後の自虐史観教育を受けた人たちが中心になってくると、悲壮感ばかりが強調されたり、戦争を起こした罪悪意識のようなものが濃く出すぎたりという傾向が目立つようになった。このサイトで3年前に配信された「『エール』五郎『麒麟』義昭の共通点、朝ドラ・大河における戦争観の歪みと葛藤を考える」でも触れたように、今の日本人にあの戦争をフラットにとらえることは難しく、ともすれば、いびつな描き方にもなりがちなのである。
何より残念なのは、二度の世界大戦に象徴される帝国主義時代の最終対決に残ったことへの誇りが欠落してしまっていること。スポーツの大会にたとえるなら、ヨーロッパラウンドでドイツが負けたことにより、決勝は日本対米国(及び英国や中華民国など)の組み合わせとなった。野球でいえば、2回くらいまでは3対0くらいでリードできたが、3回には追い付かれ、5回以降は大量点をどんどん入れられた感じだ。普通ならコールドになるところ、決勝だから9回までやって、最後は4対23みたいな試合である。
それでも、決勝まで残ったのは事実だし、地政学上の不利や人種的な劣勢をはね返し、あそこまで持っていったことを改めて誇れるような作品がもっと生まれてもよいのではないか。
そういう意味で、ようやくその記憶が風化しつつある今、見直すにはよいタイミングに思われる。俯瞰的に見れば、あの時代は戦国や幕末のように、何度かあった激動期のひとつなのだから、戦国や幕末のように描いても構わないわけだ。それこそ、今年のNHK大河ドラマ「どうする家康」は、その歴史解釈や展開が自由すぎて賛否両論だが、あの時代についてもいずれは「どうする五十六」みたいなものが出てくるはずだし、そうでなくては困る。
ちなみに、大河ドラマ第1作の「花の生涯」(63年)は日米修好通商条約や安政の大獄で知られる井伊直弼が主役。大弾圧を行ったことで必ずしもイメージはよくなかったが、没後103年目にして再評価がもたらされた。同名の原作はその10年ほど前、没後90年余りの時期に書かれている。おそらく、薩長主導の大日本帝国が終戦で斃れたことが転機となり、開国派として日米外交でも活躍した井伊に追い風が吹いたのだろう。
さまざまな歴史観や人物造型を楽しめるのが史実を扱った作品の魅力であり、4分の3世紀が過ぎたことで戦争モノもぜひそう変わってほしい。たとえば、東条英機あたりが再評価される作品も見てみたいものだ。
文:宝泉薫(作家・芸能評論家)