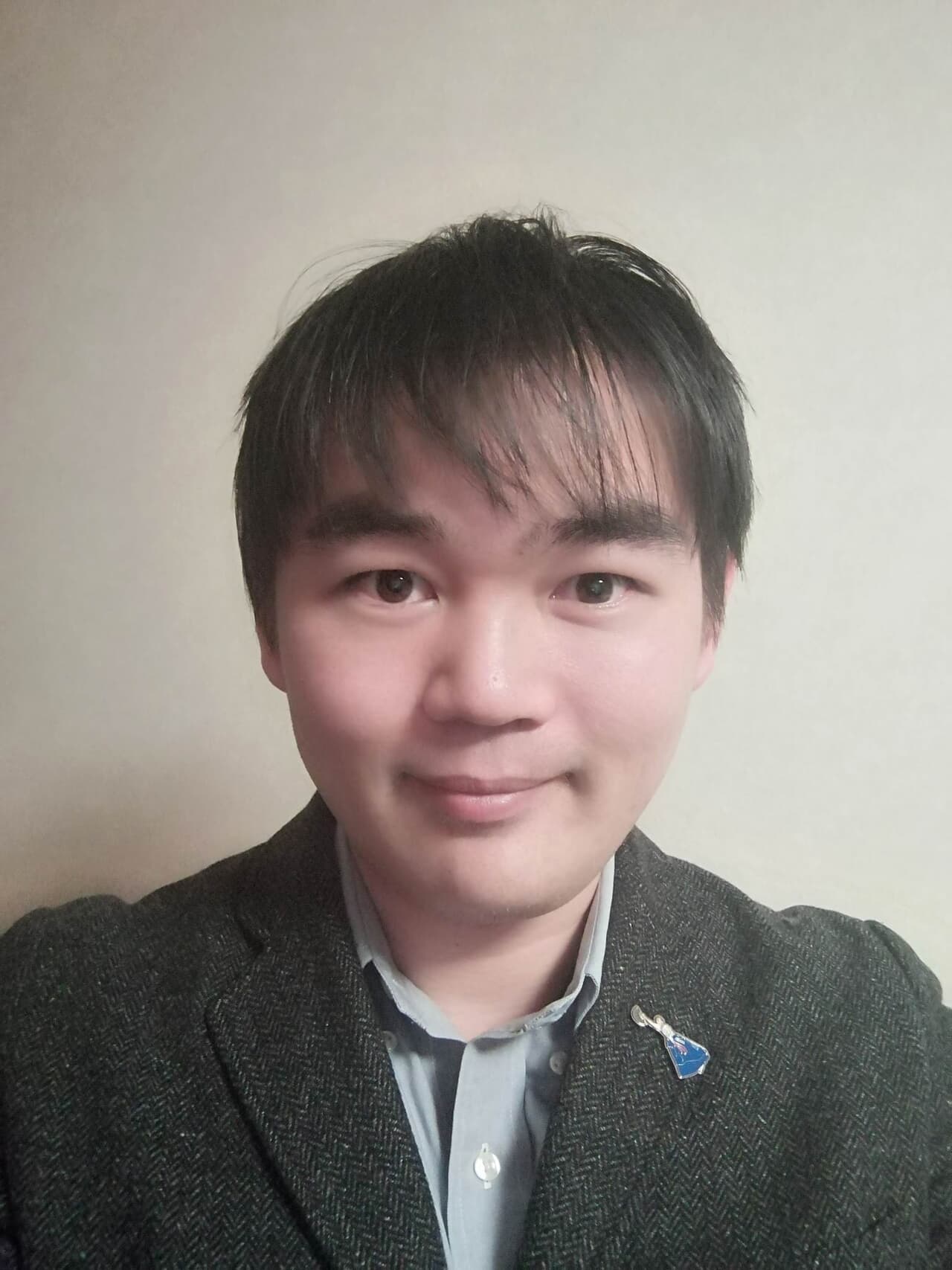【芥川賞候補に!】ブックライターが読んだ 向坂くじら『夫婦間における愛の適温』。そして感じた清々しいまでの嫉妬心【甲斐荘秀生】
◾️「寄る辺ない自分」を描こうとする美しさ
でもまあ、ただ文章が巧いだけだったら、感心こそすれど敗北感を抱くまでではなかっただろう。そもそもプロに対して「巧い」というだけの感想は失礼だ。例えば音楽なら、ライブが終わった後のミュージシャンに、いい大人が「巧かったです」とだけ感想を伝えたら侮辱と受け取られても仕方ない。その上で観客の心を何かしら動かすことができなかったなら、少なくともその観客との関係においてライブは失敗だった、ということになる。
それでは彼女の文才の他に、何が私に「俺は、こんな風には書けない」と思わせたのか。それは、自分自身の思索に真摯に向き合い、決して単純ではないひとまずの結論とそこに至るまでの過程を、できる限り文章で描こうとする勇気だ。
例えば日常で起こしたちょっとした失敗や、家族や友人と噛み合わないやりとりをする様子の場面では、エッセイの登場人物としての自分を客体化して描き、リズムよく読ませる。
けれども「エッセイの中の自分」が一旦何かを考えはじめると、書いている自分もその時点に戻って丁寧に思索を追いはじめ、思索のバトンはいつのまにか、文章を書いている現在の自分へと渡される。
「寛容にふるまうことを考える。単に心の中に寛容さを持つということだけでない。他人に対してそのようにふるまうということを。」
「わたしは生徒に(中略)「これを書けてよかった」と思う、あの時間に辿りついてほしいと思っている。けれどもそれ以上に、本心ではいやなことを、わたしの命令のために黙ってやらせてしまいたくない。その両者はどちらが見せかけというのでなく、同時にわたしの中で起こっている。」
(本書収録「「そっちでいくのかよ」」より引用)
「思索の前の自分」と「思索の後の自分」の間にたしかにいたはずの「寄る辺ない自分」にもう一度同化して、思索の痕跡を一歩一歩確かめる。そうして描かれた文章は端正で、私にはこの上なく心地いい。と同時に、「俺もこういう風に書けたら」と一抹の悔しさを覚える。
本来、人間の思考はとりとめなく混乱しているので、特に自分の思考を真正面から見つめるのは恐ろしい。だから多くの文章では、思索のプロセスをなかったことにして、思索の末に辿り着いた見栄えのいい結論だけが書かれがちだ。このコラムもそこから逃れられたとは言いがたい。
けれども向坂くじらは、蝶の美しさではなく、蛹の中で起こっているメタモルフォーシスの様子こそを描こうとする。「分かってもらえないかもしれない」という不安から、思索する自分を茶化したり装飾に逃げたりせずに、「たとえ理解してもらえなくても、受け止めてはくれるはずだ」と読者を信頼して、エッセイを送り出す。そこには「最初の読者」である編集者への信頼もあるのだろう。
きっとこれまでも、同じ詩人として向坂くじらを知っていた人たちは、いま私が感じているのと同じような清々しい嫉妬心をもって彼女に接していたんだろう。私もその秘密を共有する仲間入りが出来たと思うとなんだか嬉しいし、本書をこれから読む人たちが同じように心かき乱される姿を想像すると、にやにやを禁じ得ない。
文:甲斐荘秀生