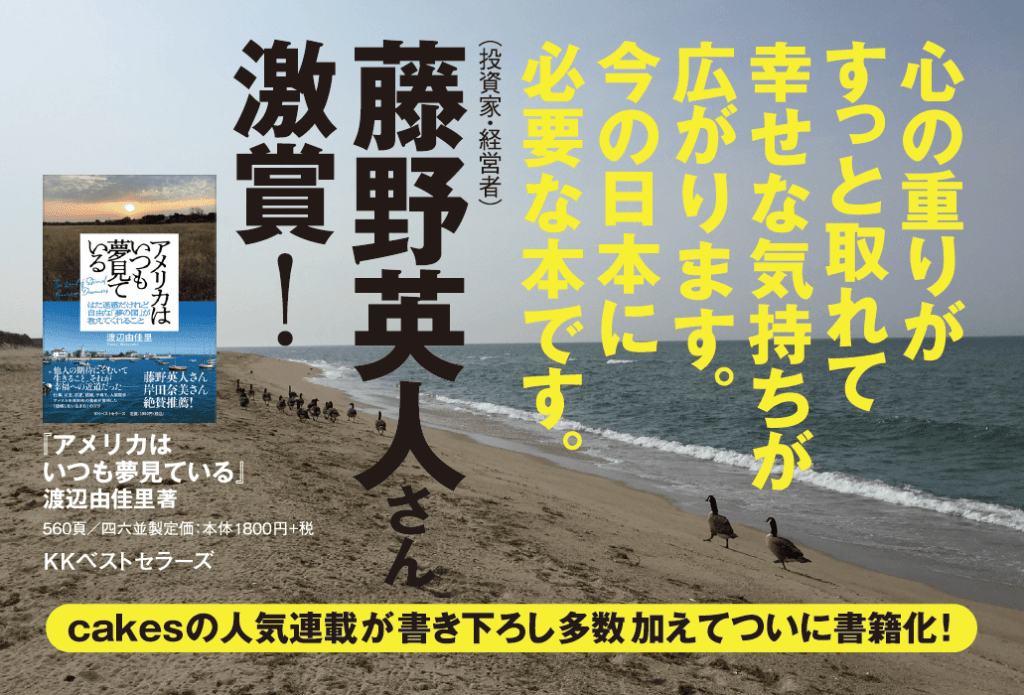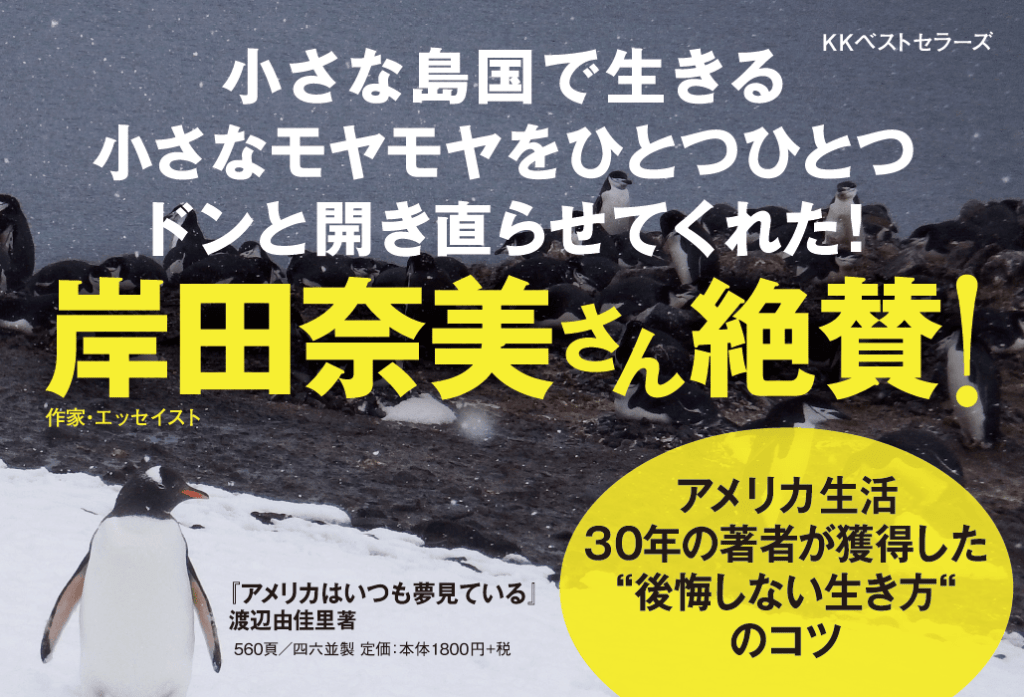ジャニーズ問題で改めて考える。「大人と未成年者の性行為は、いかなる場合も大人に非がある」ということ【渡辺由佳里】
■大人は子どもを心理的に圧倒し、簡単に操作する
そこで、「嫌だと感じたのに、なぜケヴィンはシャンリーと性的関係を続けたのか?」と疑問に思う人がいるだろう。だが、これはよくあることなのだ。
大人である加害者のほうは、「誰にも言うな」と脅し、犠牲者のほうが「自分で求めたこと」だと思い込ませることに成功する。これは被害者が自分の認識を疑うようになる「ガスライティング」である(『ガス燈』というパトリック・ハミルトンの戯曲および映画化作品で描かれる心理操作から生まれた言葉)。心身ともにまだ未熟な性暴力の被害者は、よく理解できないままに、自分が体験したことが「汚いこと」だと感じ、自分が汚れてしまい、価値がなくなったと感じる。そのために加害者と肉体関係を続けることもある。「ロックスターの自殺が浮き彫りにする性暴力被害者の苦悩」で紹介したケースもそうだった。ジェンダーにかかわらず犠牲者の心の傷は深く、その傷が人生を徹底的に壊してしまうことも少なくない。犠牲者らの数えきれないほどある体験を読めば、彼らがその後何十年にもわたってどれほど悩み、苦しんだのかがわかる。
冒頭の件で「キスぐらいで騒ぐほうがおかしい」という意見も目にした。
だが、性的な知識も体験もない年齢での性的な体験による心の傷は、性交に達しなくても深いことがある。
初期に「スポットライト・チーム」に体験を告白した犠牲者のひとりパトリック・マックソーリのケースがそうだ。
パトリックが12歳のとき、父親が自殺した。その悲劇に打ちひしがれている母と息子を家庭訪問したジョン・ゲーガン神父は、母親に優しく悔みの言葉を伝え、アイスクリームを買いに少年を連れ出してやろうと提案した。
アイスクリームを買って戻る途中、車の中でゲーガンはパトリックの短パンの中に手を差し入れ、性器を弄んだ。パトリックは「僕は凍りついた。茫然自失した」とそのときの心境を語った。
「なんだ、触られただけじゃないか」と思う人がいるかもしれない。だが、犠牲者にとっては、それだけでも人生を破壊する大きな心の傷になる。
それ以降パトリックは精神状態が不安定になり、酒やドラッグで心の痛みをやわらげようとするようになった。ボストン・グローブ紙に告白した後も自殺未遂のような事件を起こし、最終的に29歳の若さでドラッグの過剰摂取で命を失った。
神父の児童性虐待と状況的によく似ているのがスポーツコーチによるアスリートの性的虐待だ。ある調査では、女子アスリートの31%、男子アスリートの21%が何らかの性的虐待にあっているという。
スポーツの狭い世界で生きるエリート選手にとって、自分の命運を決めるコーチは神に等しい存在だ。自然と父親に対するような敬愛の感情も抱く。そういったコーチがアスリートを心理的に操作するのは簡単なのだ。カナダやアメリカでも、マッチョとみなされているアイスホッケーやフットボールでコーチが少年アスリートを性的虐待していたことが何十年もたってから明らかになることが多い。
私が個人的に知るケースの犠牲者は少女だったが、「誰かに言ったら、この世界で生きられないようにしてやる。選手生命は終わりだ」と脅され、親にも打ち明けられなかった。
これらのケースでわかるように、ターゲットにされた子どもには、選択肢はないし、逃げ道もない。逃げ道がないところに「同意」などは存在しない。
もし性的に成熟している態度の未成年者がいるとしたら、すでにケヴィンやパトリックのように心を壊す体験をしているのかもしれない。家庭に悲劇や問題があるのかもしれないし、自暴自棄になっているのかもしれない。いずれにしても、未成年者は「性的に成熟しているように見えるから大人と対等」ということにはならない。
「赤子の手をねじる」というたとえがあるように、大人は子どもを心理的に簡単に圧倒し、操作できる。だからこそ、大人は子どもを利用するのではなく、守ってやらなければならない。
子どもを守るとはどういうことか?
まずは、子どもを性的対象として扱うのをやめなければならない。それを肯定するのも。
たとえむこうからアプローチされたとしても、大人は未成年者との性的関係を避けなければならない。「深夜に自宅のアパートに呼び込む」というシチュエーションを避けなければならないのは大人のほうだ。誘われた子どものほうではない。
そして、大人が子どもを犠牲にしたとき、ソーシャルメディアで加害者をかばったり、被害者の子どもを責めたりするのをやめなければならない。
それが、無事にここまで生きられたラッキーな大人の義務である。
(『アメリカはいつも夢見ている』本文から抜粋 [2018年5月2日cakes掲載])
文:渡辺由佳里