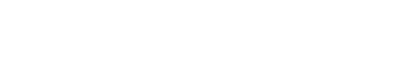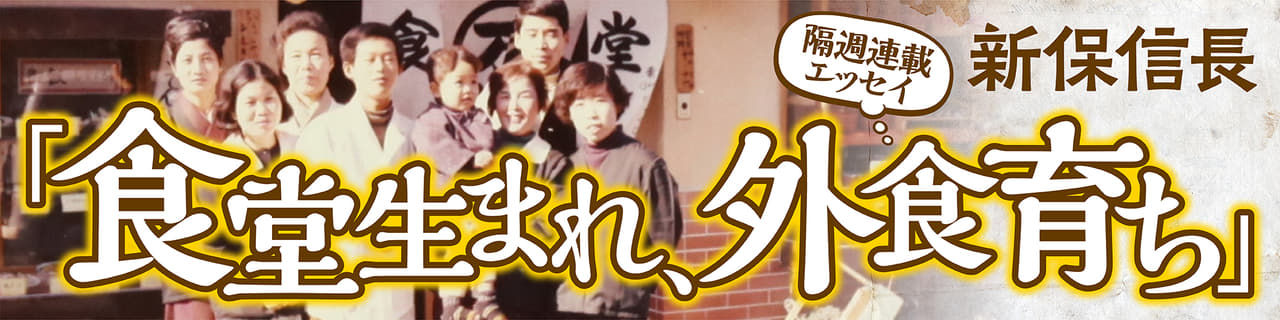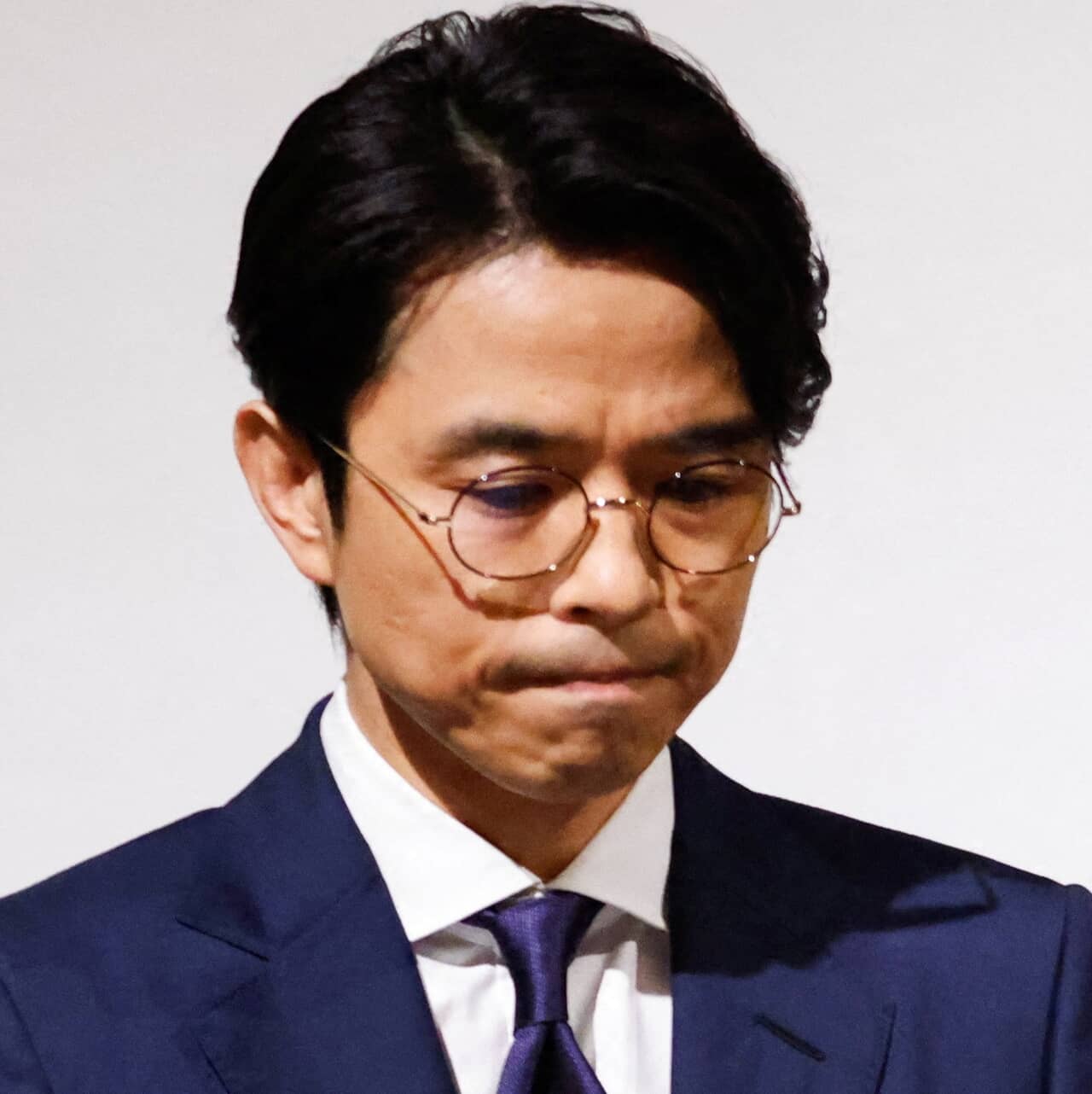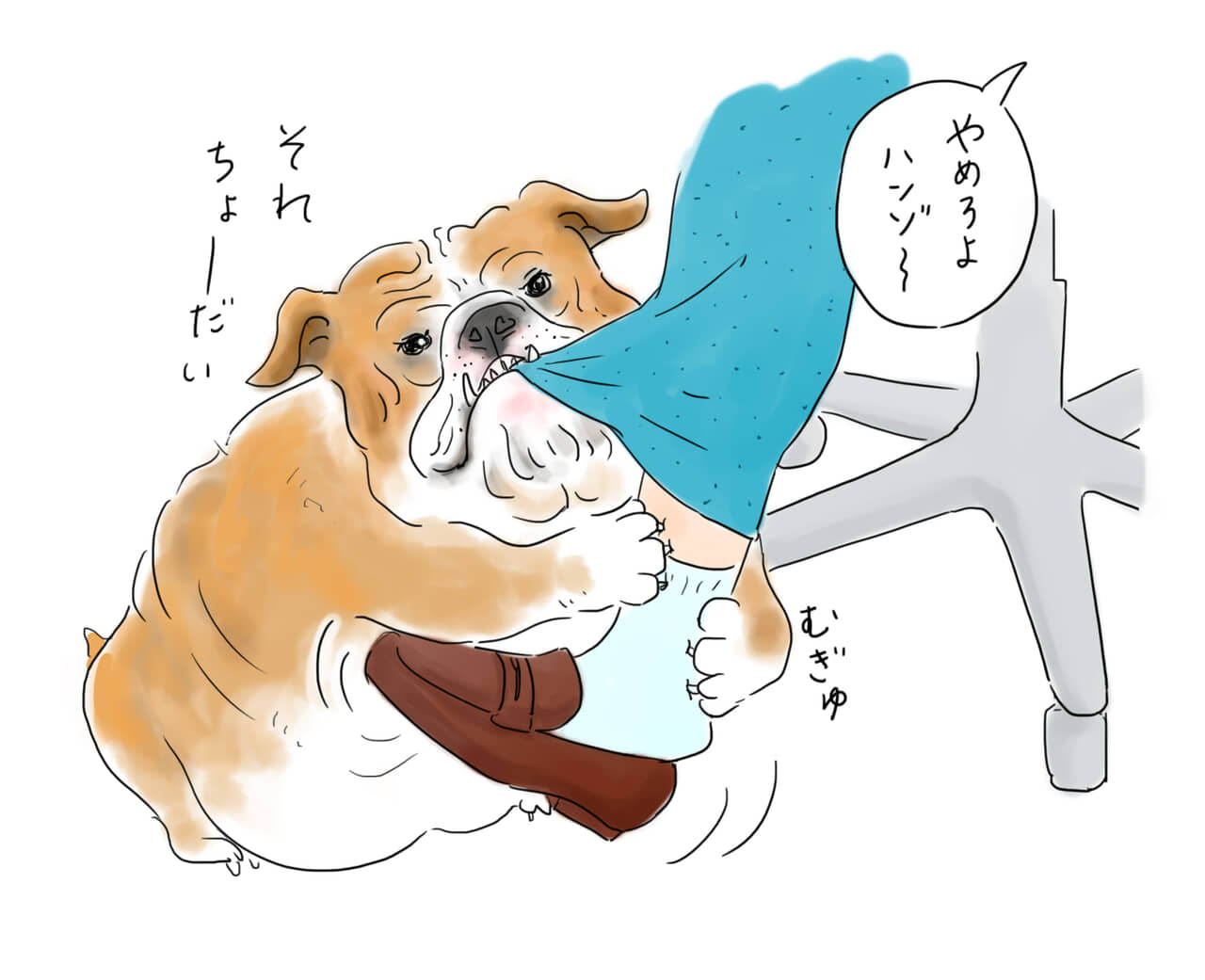校外学舎の悲しき夕食【新保信長】「食堂生まれ、外食育ち」40品目
【隔週連載】新保信長「食堂生まれ、外食育ち」40品目
「食堂生まれ、外食育ち」の編集者・新保信長さんが、外食にまつわるアレコレを綴っていく好評の連載エッセイ。ただし、いわゆるグルメエッセイとは違って「味には基本的に言及しない」というのがミソ。外食ならではの出来事や人間模様について、実家の食堂の思い出も含めて語られるささやかなドラマの数々。いつかあの時の〝外食〟の時空間へーー。それでは【40品目】「校外学舎の悲しき夕食」をご賞味あれ!✴︎連載全50回がついに書籍化、絶賛発売中です!

【40品目】校外学舎の悲しき夕食
私が通っていた小学校では、高学年になると年に1回か2回、校外学舎に泊まりがけで行く行事があった。校外学舎というのは、読んで字のごとく学校外にある学舎、いわば別荘のようなものである。といっても、そんな立派な建物ではなく、プレハブ小屋に毛が生えた程度のものだったが、要は泊まりがけの遠足と思ってもらって間違いない。
所在地は兵庫県川西市。能勢電鉄妙見口駅から徒歩15分ぐらいだったか。妙見山という東京でいえば高尾山みたいなポジションの山の麓にあり、自然豊かな環境だった。というか、自然豊かな環境だからこそ、都会っ子たちを泊まりがけで連れていくことに教育的意義があったのだろう。
到着すると、最初にやるのが布団干しだ。たまにしか使われないため湿気ってカビくさくなった布団を、みんなで庭に運び出す。大変な作業のようだが、自分が寝る分の布団を運べば数は足りるわけで、さほど大変ではない。雑草だらけの地面に直で置いていたような気もするが、いくら昭和の衛生感覚でもゴザかブルーシートぐらいは敷いていたかも。とはいえ、たまに地面から這い出してきた大ミミズが布団の上をのたくっていることがあり、それはさすがに気持ち悪かった。ミミズのぬめりで汚れた布団をどうしたかは記憶にない。
その後、妙見山に登って(ケーブルカーがあるので小学生でも登れる)、山上の広場かどこかで各自持参の弁当を食べる。普段は給食なので、弁当というだけでイベント感があった。ウチの小学校は校内調理だったので給食はそれなりにおいしかったが、こういうシチュエーションで食べる弁当は本来の味の2割増ぐらいには感じられる。
そして何よりの楽しみは、おやつである。当時は「おやつは100円まで」だった。友達と一緒に駄菓子屋に繰り出して、真剣に吟味する。「オレこれ買うから、オマエそれ買うて半分こせえへん?」みたいな密約を結ぶのも楽しい。今考えれば、別に検査があるわけでもないので多少オーバーしてもバレやしないのに、きちんと限度額内に収めようとするのがいかにも小学生である。
そのおやつ代は自分の小遣いから出していたのか、それとは別に親が出してくれたのか。学校行事ということで親が出してくれていた可能性が高いが、だとしたら全部使わず余らせた分を自分の小遣いにするという手もある。たかが数十円でも、小学生にとってはバカにならない。友達とのおやつ交換でも、いかに有利な取り引きをするかが大事。そういう意味では、今よりはるかに真剣に生きていた。
校外学舎の周辺には小さな池もあり、そこでよくアカハライモリを捕って遊んだ。セミやカブトムシも普通に捕れた。今では夏の終わりのセミファイナル(死にかけのセミが突然ブブブブと暴れるやつ)にビクッと後ずさる体たらくだが、当時は生きたセミでキャッチボールしたりもした。何でも遊びにできるのが小学生男子というものだ。
しかし、何事も楽しいばかりでは終わらない。日が沈み暗くなってくるにつれ、憂鬱な気分がふつふつと湧いてくる。ああ、またアレの時間がやってくる……。本当に嫌なんだけど、どうにかならないのかなあ……。
- 1
- 2

✴︎KKベストセラーズの7月新刊✴︎
新保信長 著『食堂生まれ、外食育ち』
作家・平松洋子さん推薦!!
「気配をスッと消し、食の現場をニヤリと斬る。
選ばしし外食者の至芸がすごい。」
外食歴50年超の著者が綴る異色の外食エッセイ!
一口に「外食」と言っても、いろんなシチュエーションがある。子供の頃に親に連れていかれたデパートの大食堂。夜遅く仕事帰りに一人で入る牛丼屋。ここぞというデートや記念日に予約して行ったレストラン。気の置けない仲間と行く居酒屋。たまの贅沢のカウンターの寿司屋。出先でたまたま入った定食屋。近所のなじみの中華屋や焼き鳥屋……。
誰もが心当たりあるような懐かしくも愛しき「外食の時空間」への旅が始まる!
カバー&本文イラスト描いたイラストレーターおくやまゆかさん。
イラストが最高に愉快!(全50点収録)
目次
序 「今日のごはん何?」と聞いたことがない
第1章 ノスタルジア食堂
1品目|外国人と鴨南蛮と中華そば
2品目|ランチタイム地獄変
3品目|「天丼」と「うどん天」と「シマ」
4品目|出前とデリバリー今昔物語
5品目|おでん定食というギャンブル
6品目|ハンバーグ記念日
7品目|おいしい味噌汁の条件
8品目|最高のおやつ
9品目|校外学舎の悲しき夕食
10品目|わんこスイカ
11品目|ところ変われば品変わる
12品目|「恵方巻」と「丸かぶり」
13品目|ちくわぶとはんぺん
14品目|「肉じゃが=おふくろの味」って誰が決めた?
15品目|スマホがなかった時代
16品目|Gに気をつけろ!
第2章 私が通りすぎた店
17品目|あの素晴らしい寿司屋をもう一度
18品目|気まぐれすぎる女将
19品目|選択肢のない店
20品目|日本一大きいビアガーデン
21品目|カニ・マイ・ラブ
22品目|国会図書館でナポリタンを
23品目|夫婦の肖像
24品目|サハリンの夜
25品目|インドで大炎上
26品目|開幕前の至福の宴
27品目|私がスポーツジムに通う理由
28品目|かわいそうな寿司屋とその弟子
29品目|残業メシ格差
30品目|よそンちの食卓はつらいよ
31品目|大食いと早食い
32品目| BGMも味のうち?
第3章 外食の流儀
33品目|大盛りはうれしくない
34品目|取り皿問題
35品目|デザート嫌い
36品目|お熱いのはお好き?
37品目|器のTPO
38品目|あんまり尽くされても困る
39品目|スパゲティがパスタに変わった日
40品目|何をかけるか問題
41品目|どの席に座るか問題
42品目|酒飲み認定
43品目|11人きた!
44品目|硬と軟
45品目|人はだいたい同じものを注文する
46品目|トングどっち向きに置く?
47品目|箸と愛国
48品目|ステキなタイミング
おわりに 入れなかったあの店の話