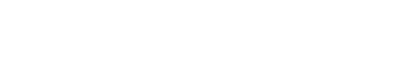着手から埋葬まで20年! 大仙陵の造り方を徹底解剖①
大仙陵はいかにして造られたのか? 第2回
■大仙陵が造られた工程をCGで再現!(前編)
(1)海の見える台地を選ぶ

大阪湾を見下ろす台地上が選ばれたのは、海上の船に巨大古墳の威容を見せるためである。海上を往来する人々の目には巨大な力の存在が間近に映ったことであろう。なお、『日本書紀』にも仁徳天皇が石津原(いしづはら)にて生前に陵墓を築くという特別な記事がみえる。
(2)杭と縄を使って、設計図を地面にひく

台地上といっても決して平坦ではないので、丘を削り、谷を埋めておよそ800m四方の水平の地盤を造成した。そこに設計図をもとに杭と縄を用いて地面に縄張りを行った。これだけの平坦地を測量して造成した当時の技術は相当のものであったろう。
(3)表面の土を掘り起こしてレンズ状に盛り土にする

平坦に造成した地面に最初に盛る土は、表土のような黒土で、しかもひっくり返して積み上げる。3~4単位積み重ねて全体で厚さ30㎝程の層をなし、土台とした。古墳の盛り土ではこうした層はよく見られる。これは土木工学的に必要な作業であったのであろう。
(4)濠を掘削する

濠の形状に合わせて粘土層や砂礫層の掘削を進める。掘削に使う道具は木製の本体に鉄製の先端部を付したもので、今のスコップと比べて機能的に劣る。しかしながら、当時はまさに鉄の時代、これとて最先端の技術を駆使した道具であった。
(5)「もっこ」を使って掘った土を運び、盛り土にする

濠を掘削した土だけでは盛り土のすべてを賄えないので、離れた場所でも採掘して運び込んだ。掘削土の運搬は1人で行うこともあったであろうが、「もっこ」と呼ばれる道具を用いて2人1組で行ったのではないかと考えられる。
(6)1.5mの高さに水平に積んでいく

運ばれた土は監修者の指示に従って決められた場所に山のように積み上げていく。その高さは人の目線の高さを目安とし、それぞれの山がほぼ同じ高さで盛られていった。その後、山と山の間を埋めると水平な層となり、またその上に同様に盛っていくのである。
《大仙陵はいかにして造られたのか? 第3回へつづく》
※この記事に掲載されている画像の無断転載を禁じます。