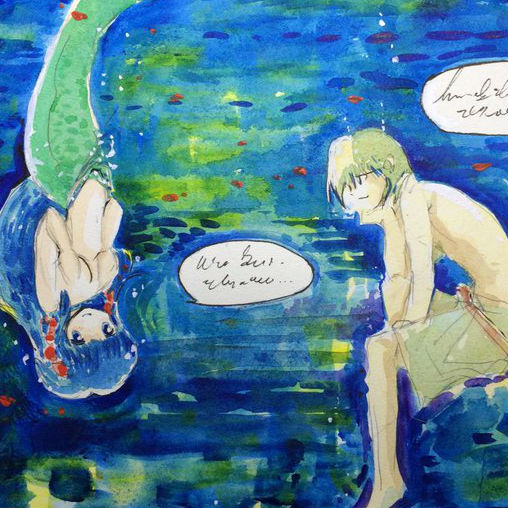身分の差と時期によって異なる古墳の種類
大仙陵はいかにして造られたのか? 第4回

古墳の種類と年代
■3世紀から7世紀までさまざまな形状が登場した
古墳は、時代によって築造された、その形状が異なる。前方後円墳や前方後方墳は古墳時代の初期から見られ、後期にあたる6世紀まで築造されていた。また帆立貝(ほたてがい)式古墳は、前方後円墳の変形あるいは円墳の変形であるが、5世紀を中心に築造されたものであった。円墳と方墳は初期から古墳時代の終末期である飛鳥時代まで続くものである。ちなみに最も多い形は円墳であり、全国に20万基ともいわれる古墳のほとんどを占める。

【円墳】 初期から終末期までどの時代にも築造。古墳のほとんどが円墳である。後期末には奈良県藤ノ木古墳など、一部有力な古墳がある。

【方墳】 初期から終末期までどの時代にも築造。円墳に次いで数が多い。後期末には奈良県の赤坂天王山古墳など、有力な古墳がある。

【前方後円墳】 初期から後期まで築造され、出現期より規模の巨大さを特徴とする。北は岩手県から南は鹿児島県まで、約4700基に及ぶ。

【前方後方墳】 初期から中期にかけて築造された。全国で約500基が確認されている。特に前期の東日本に多くみられる形状である。

【帆立貝式前方後円墳】 中期から後期にかけて築造。円墳に張出(はりだし)が取り付いたものと前方後円墳の前方部の短いものとの2種類がある。
この他には、数が少ない特殊なものがいくつかあげられる。双方中円墳(そうほうちゅうえんふん)は前方後円墳の変形で、前方後円墳に方の段が取り付いたものであり、前期に見られたもの。一方、双円墳(そうえんふん)には後期の例がある。上円下方墳や八角形墳は時代が下った7世紀代に見られる形で、八角形墳は天皇陵と見られるものであった。
また、墳丘に造出状の施設が取り付いていたり、段築(だんちく)、周濠、中島、堤(つつみ)などの施設があるものなど、そのヴァリエーションはさまざまであった。

【双方中円墳】前期に築造。類例は大変少ない。奈良県の櫛山(くしやま)古墳が代表例だが、普通の前方後円部に短い突出部を付けたような形状。

【双円墳】 後期に築造された形だが、類例は極めて少ない。大阪府の金山(かなやま)古墳が代表例である。韓国慶州の皇南大塚もこの形である。

【八角形墳】 終末期の天皇陵にみられる特殊なものである。京都府の御廟野(ごびょうの)古墳や奈良県の野口王墓古墳などが代表例である。