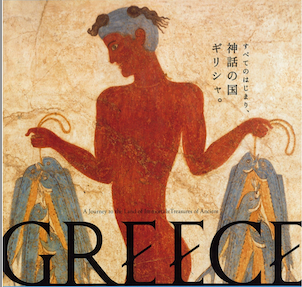天皇の「生前退位」をめぐる、男系固執主義者たちの葛藤
ベスト新書「ゴーマニズム戦歴」発売記念コラム①
天皇を憲法の外側に置く危うさ
わしの『天皇論』を読まずとも、現実には大多数の日本人が天皇や皇室を敬愛している。正月の一般参賀ともなれば、皇居前はたいへんな賑わいだ。天皇について何も知らなくても、自然と敬愛の気持ちがわいてくる。そこが「本物の権威」の持つ凄味にほかならない。日本人の無意識の中に、天皇が入り込んでいるのだ。
だから、仮に左翼の主張どおりに天皇制を廃止したり、憲法の枠組みから外したりしても、その権威はまったく揺るがないだろう。その瞬間に、日本には最大・最強の新興宗教が生まれることになる。ふつうの宗教は教祖や教団の私利私欲に基づいているからお布施が必要だが、天皇は「無私」の存在だからそんなものはいっさい求めない。国民の圧倒的支持を集めるそんな宗教的存在が憲法の外側にあれば、権力を脅かすことになる。
実際、江戸時代まではそうだったのだ。たとえば天明の大飢饉のような事態になれば、政治権力を握る幕府には誰も頼らない。「あいつらはダメだ」と幕府を見限って、京都御所のまわりをみんなでグルグルと回り始める。明治維新のときも、戊辰戦争で薩長軍が錦の御旗を掲げただけで、幕府軍は「朝敵になってしまったら、もうおしまいだ」と観念して敗走してしまった。そこに天皇がいるわけでもなく、錦の御旗も密造した偽物だったのに、その権威には絶大な存在感があったのだ。
二・二六事件を起こした青年将校たちも、自分たちが「玉」を取れると信じて決起した。政治家から権力を奪い、天皇親政を実現できると思っていたのだ。本来なら政府が鎮圧するべきだったが、当時の権力はまったく動こうとしない。そこで昭和天皇が自ら指揮を取るとまで言った。「玉」が動いたことで、決起した連中は狙いとは正反対の「賊軍」になってしまい、ショックを受けて投降する。それぐらい強力な権威が天皇にはあるのだ。
だから、日本における天皇の扱いはよほど慎重に考えなければいけない。なにしろ、伊勢神宮を参拝した西行法師が、「なにごとの おわしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる」という歌を詠んだぐらいの存在である。仏教の僧侶がこんな歌を詠んでしまうぐらいだから、一般庶民にとって天皇の存在感は圧倒的だ。その存在を意識しただけで「ありがたい」と思え、涙をこぼしてしまうような信仰心がそこにはある。天皇や皇室が暴走することはあり得ないが、その権威を悪用すれば政治権力の転覆もできてしまうだろう。
もしこれを憲法の枠組みから解き放てば、政府の権力を支えてきた権威が、政府とは別の場所で国民への支配力を持ってしまう。それは社会を混乱させるから、天皇は憲法の中に封じ込めて「立憲君主制」にするのが正解なのだ。