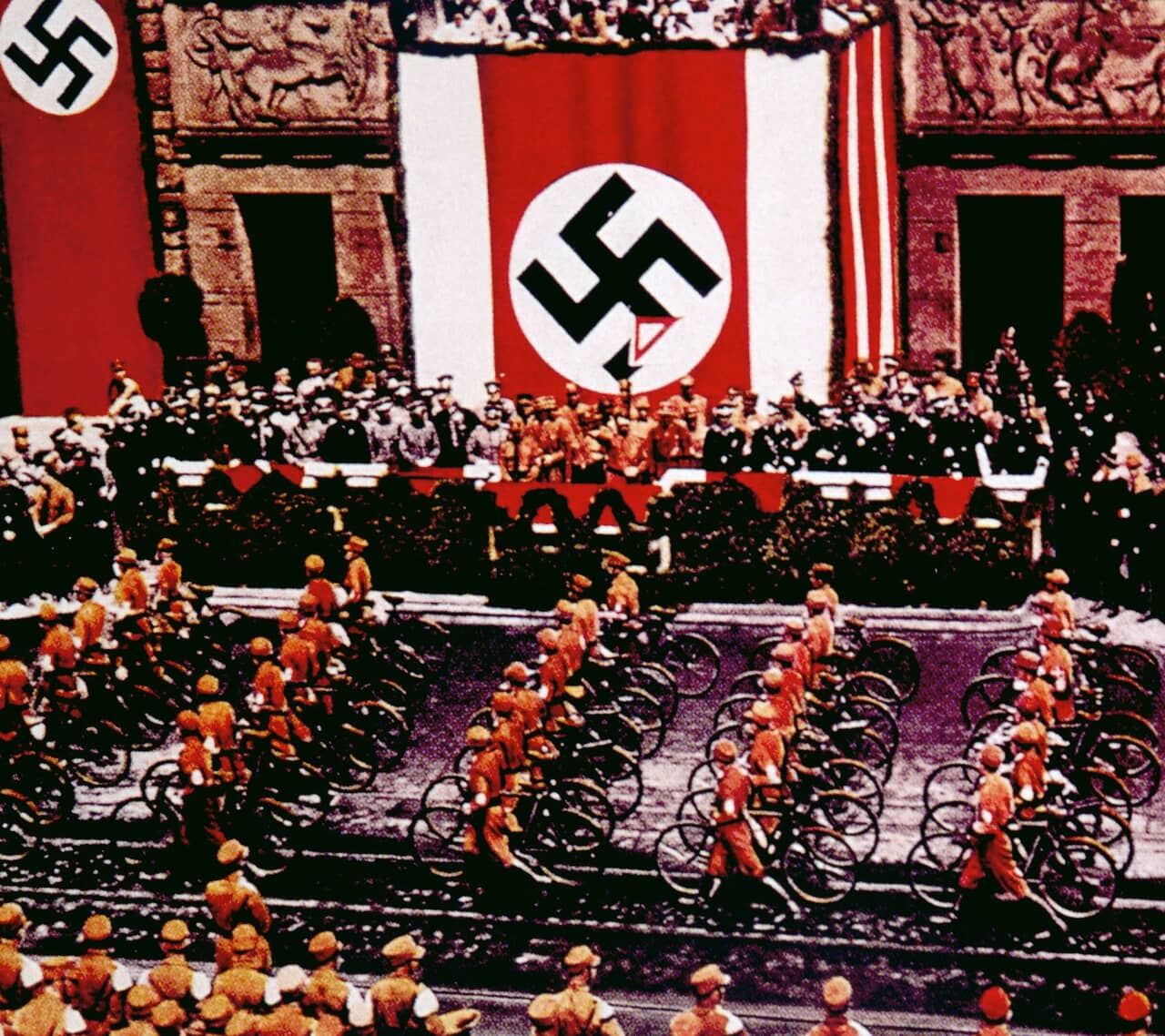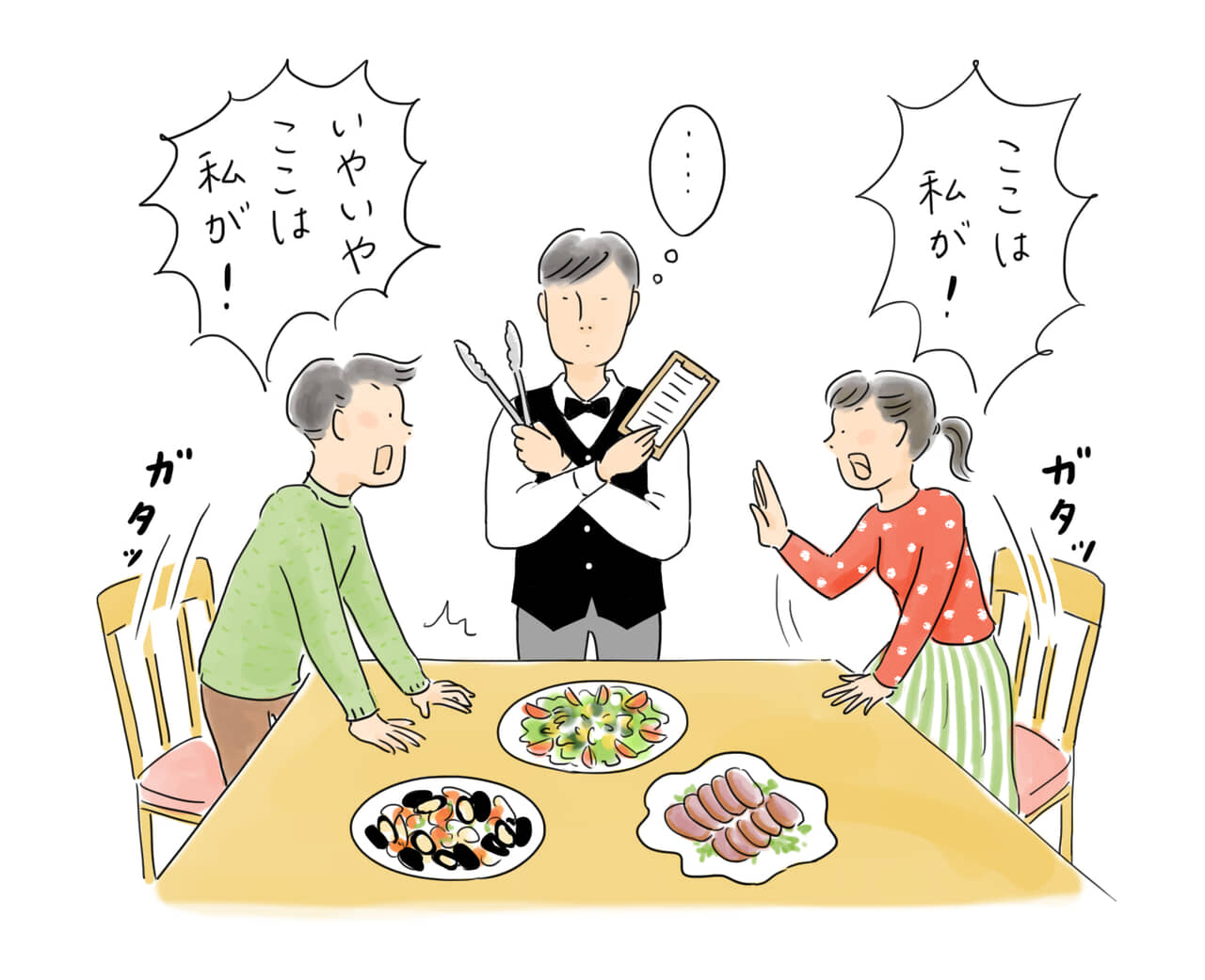「若さを失うことは、可能性を失うことか」 雨宮まみ『40歳がくる!』葛藤を強さにして生きた証【若林良】

『40歳がくる!』(大和書房)は、2016年5月から同年12月にかけて大和書房HPで連載された、雨宮まみによる同名の連載、また山内マリコや穂村弘をはじめ、さまざまな書き手が雨宮の思い出や彼女の残したものを振り返る、10におよぶ特別寄稿を収録した一冊である。連載自体は16年11月の、雨宮の40歳での死をもって中断されたものの、それから7年を経て、書籍として出版された。
■個人的「雨宮まみ」体験
私はいま33歳の男性だが、生前の雨宮まみに対する思い入れはそこまで強いとは言えず、一般的な読者の域を出ていなかったとは思う。たとえば、雨宮まみが亡くなった当時、その死を悼む声はリアルな知人からも続々と出ていたし、『愛と欲望の雑談』(ミシマ社)で雨宮と対談をした社会学者の岸政彦が、「さようなら」というタイトルでブログにアップしていた長い追悼文(本稿を書くにあたり再読したところ、その想いの強さに思わず圧倒されてしまった)をネットで読んだ記憶もあるのだが、それらも当時は、今ひとつピンときてはいなかった。ちょうど熱狂的なファンの集まるアイドルのライブ会場、もしくは交流会のような場に、たまたまずぶのビギナーとして入り込んでしまったかのように。
雨宮まみの生前における、私の雨宮の思い出といえば、『東京を生きる』(大和書房)を読んだことであろうか。それは出版時の2015年だったが、そのときの読後感はおおむね以下のようなものである。
「三十歳になったら、バーキンを持つんだと思っていた。二十代の頃の私にとって、東京で働く女のイメージとは「自力でバーキンが買える女」だった」(冒頭の章「お金」より)
「バーキンとはなんぞや?」(筆者25歳・なお童貞)
~〈完〉~
……いや、もう少し続けよう。続く「まさか三十を過ぎる頃には別のバッグが流行っているとも思えなかったし」という箇所で、ああ、ブランドもののバッグのことかと理解はできたものの、「ラ・ぺルラの下着」や「ダイアン・フォン・ファステンバーグ」など、その後もファッションに無知な私には聞きなれないワードが次々と登場し、どうにも自分とは別世界の話のような思いが増していった。そのせいか、それ以降のページもあまり頭に入ってはこず、中途半端なかたちで本を閉じてしまった。これは雨宮の文章の問題ではなく、大学院という狭い世界で、専攻に関係した情報以外を極力シャットアウトしていた当時の私の問題である。とはいえ、大学院を卒業して社会に出たのちも、雨宮の著作からは、その後は長らく離れていたままだった。
したがって、私にとっての『40歳がくる!』との出会いは、ありし日の雨宮の姿を思い浮かべ、当時の自分の感慨を噛み締めるようなたぐいのものではなかった。だからこそというのか、むしろ現在の自分を峻烈に問うものとして『40歳がくる!』に、そして読了後の興奮が覚めやらぬまま書店や図書館に足を運び、初読のものも含めた雨宮の数々の著作に「出会う」ことができた。