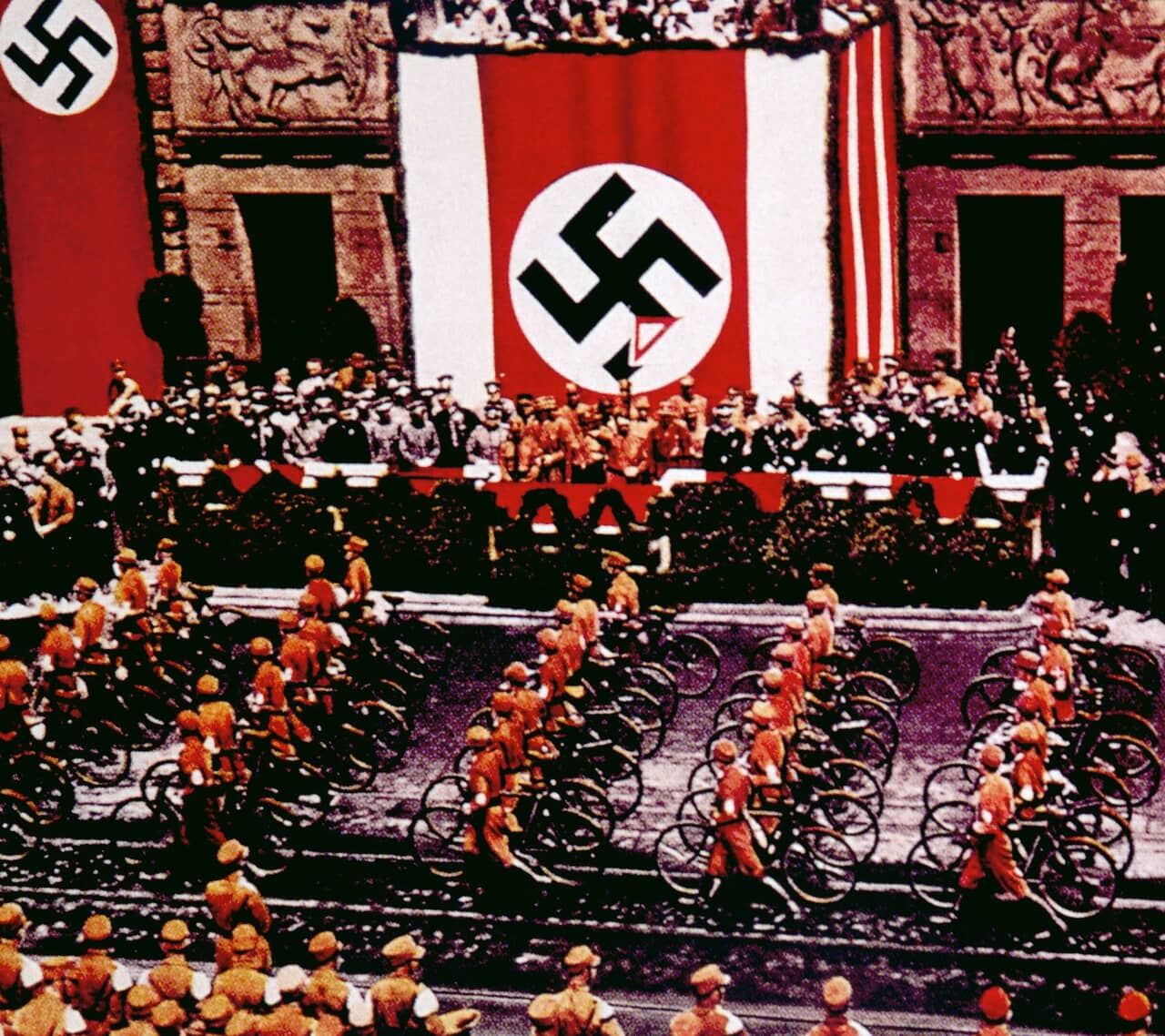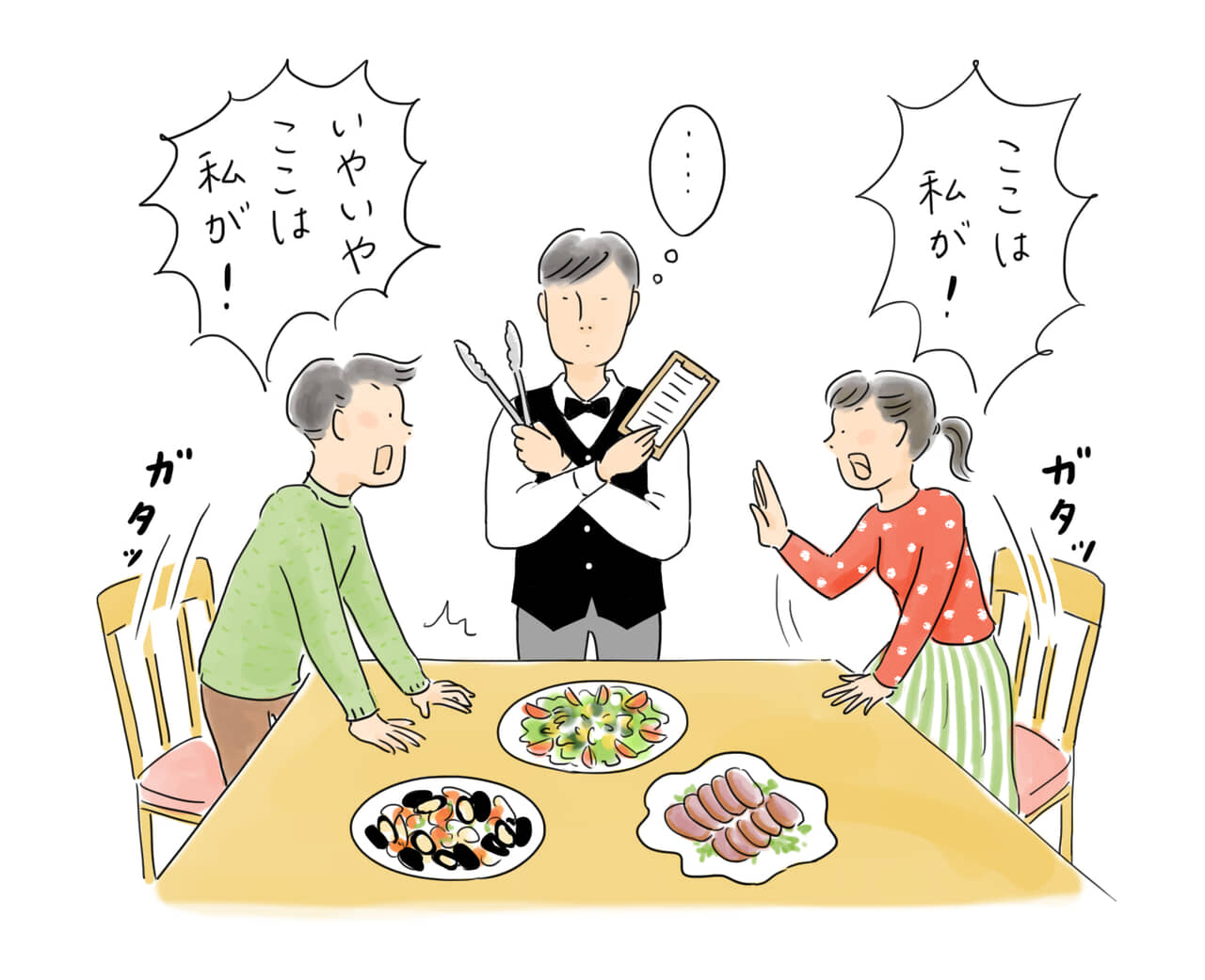「若さを失うことは、可能性を失うことか」 雨宮まみ『40歳がくる!』葛藤を強さにして生きた証【若林良】
■自分が激しく問われる感覚
『40歳がくる!』においては、文字通り40歳を直前にした雨宮が、自身の身体のコンディションや環境の変化を実感しつつ、自分にフィットした「40歳」を模索する過程がつづられている。「不惑」と呼ばれる年齢の40歳だが、じっさいは惑い続けるのが人間の常ではあるだろう。雨宮もまた、人間として完成されたようなイメージのある40歳が迫りくるという事実に、はじめは違和感や戸惑いを隠すことができず、「私は、私のままで、どうしたら私の『40歳』になれるのだろうか。そしてどんな『40歳』が、私の理想の姿なのだろうか」と率直な心情を綴る。
雨宮のこうした心情は、今だからこそ私の中に染み渡るものがあった。たとえば、「若さを失うということは、可能性を失うということである」という言葉。これを連載当時の私が読んで、納得することはできただろうか。意味はもちろん理解できただろうが、理解と納得とは違う。しかし、ある程度の年齢を重ねたことで、私の感触は「言葉としての理解」より「身体としての納得」に確かに近いものとなった。ふと鏡を見て自分の白髪に気づくようなこと。夜にぐっすりと眠り続けることができず、途中で目を覚ましてしまうこと。逆に夜通しで作業し、次の日に疲労でどっと動けなくなるようなこと。もちろん、当時の雨宮といまの私を比較しても、ちょうど新生児が小学校に入学するくらいの年齢のひらきがあるし、生きてきた境遇もさまざまな異なりがある以上、安易に「わかる」ということはできない。しかし、こうした身体の変化から、自分の可能性が少しずつ、物理的に狭まっていくことを実感するようになった今のほうが、この言葉への納得の度合いは深まったように思う。
同時に精神面での変化としても、先のことに心を輝かせるよりも、いま目の前にある仕事の量や生活の課題にため息をつくような、ネガティブな心情ばかりが強まったり、また「自分の年齢で……」などと分別くさくなっていくことも実感するようになった。だからこそ、本書で示唆される「そんなトシでそんなことして何になるの?」と他人から言われるようなことや、または言われないにしても、自身のなかの暗黙のストッパーとしての「自分は○○歳だから」が作動するようなことが、実感としてすんなりと心に伝わってきた。
その一方で、「これは自分とは違うし、まねできない」と、いい意味で実感できたことも多い。「裸になっていこう!」という章では、雨宮は『セックス・アンド・ザ・シティ』に触発され、文字通り、カメラマンに依頼して自身のヌード写真を撮影する。続く「変身していこう!」という章では、かねてより憧れていた『新世紀エヴァンゲリオン』のヒロイン・綾波レイにプラグスーツと青いカツラで扮し、確かな手ごたえと快感を得る。また、「東京の女王」という章ではバカラの新作ジュエリーのお披露目パーティーに足を運び、さまざまなシャンパンやカクテルを堪能しながら、片っ端から高級ジュエリーを試着し、そのさなかに飛び込んだ、松任谷由美さんに会えるというチャンスに迷わずに飛びつく。その果て、「決してためらわない。好きなものは好きと言い、好きな人には好きと言い、嫌いなものは嫌いだとはねのけ、嫌なものは嫌だと言い、欲しいものは手に入れて、自分自身で遊んで、面白そうなことがあればいつでもどこへでも行こう」という決意を口にするのである。そのような行動力と姿勢には、まさに圧倒されてしまう。
ここまで、私は第三者目線の書評というよりも、自分自身に引き付けての感触を文字に起こしてきている。そのように最初から決めたわけではなく、むしろ自然にそうなっていった。なぜだろうか。少し考えてみて、それは、書き手がここまで真摯に、虚飾のない自分の心情を書いてくれている以上は、私もある程度は「自分」を出さなければならないと思ったからだと気がついた(と言いつつ、雨宮と比較すれば自己開示がさっぱりできていないという自覚はあるのだが)。
「もっと、どこにでも行けるのではないか。もっと遠くを目指してもいいのではないか。いろんなものを、低く設定しすぎているんじゃないか。でも、どこを目指せばいい? 何を目指せばいい? 私は混乱していた」「どうせ、大きく道を踏み外すなんて、自分はできない。もともと真面目で小心者なんだし。だったら、その自分がしたいことぐらい、やったっていいじゃないか」……。俗な世間知が増えるにつれて、自然と口にできなくなる、自然と書けなくなる自分の等身大の悩みや率直な決意を、雨宮は書き続ける。そうした文章に触れていくなかで、読む私も「自分を出さなければ」とどんどん勇気づけられていく。