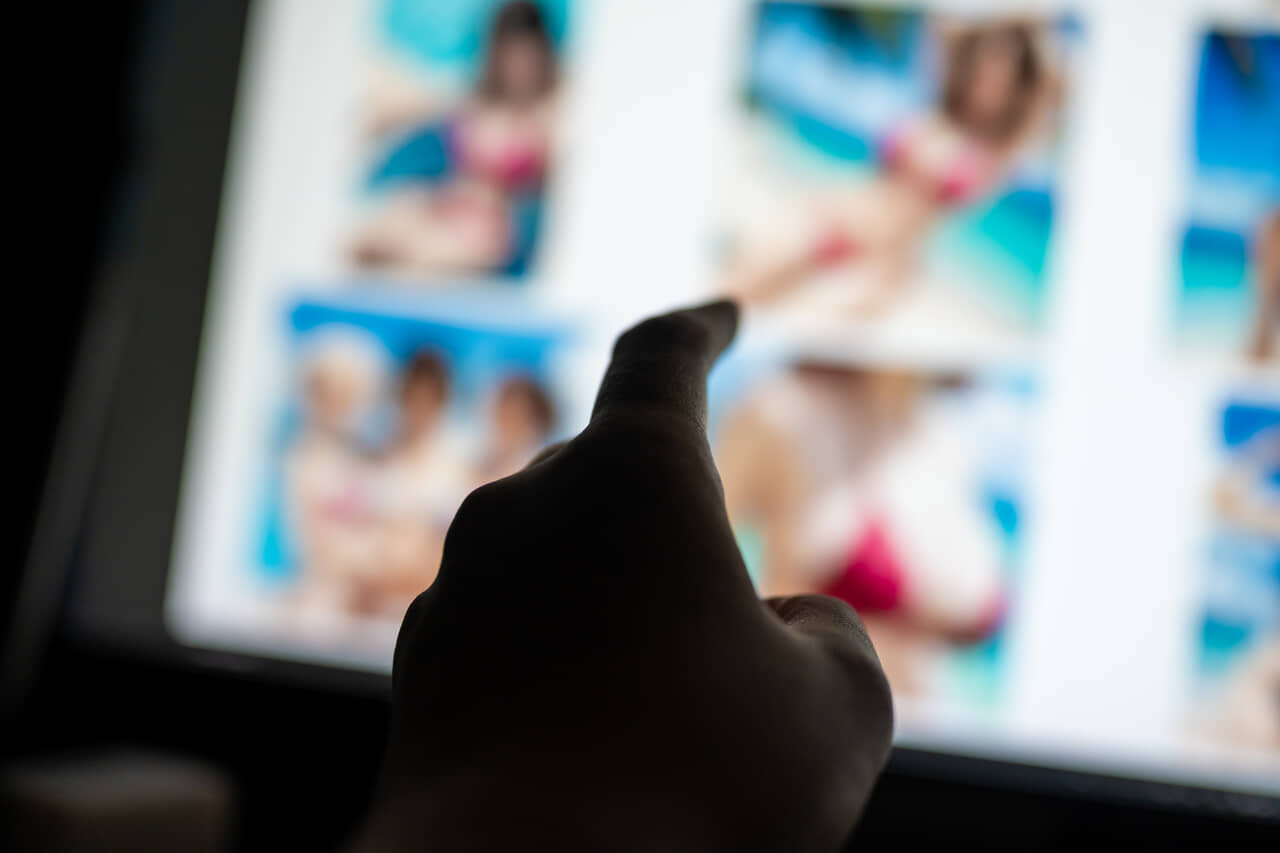ドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』はなぜこれほどまでに輝かしい人間の息吹を感じるのか? 故・佐藤真監督の眼差しとは【若林良】

本日9月12日は、ドキュメンタリー映画監督・佐藤真の誕生日である。佐藤自身は2007年に49歳で急逝したものの、今年は佐藤が残した作品が、再び国内で大きな注目を集める年となった。
というのは、「暮らしの思想」と題された佐藤作品のレトロスペクティブが、5月末から行われていることが大きい。首都圏での主だった
開催を記念し、早稲田大学では4月20日、<小森はるか監督登壇 早稲田大学講義「マスターズ・オブ・シネマ」<佐藤真 RETROSPECTIVE 開催記念>>として、ドキュメンタリー映画監督の小森はるかさんによる特別講義が行われた。

小森さんは新潟在住で、現在は『阿賀に生きる』の関係者を追ったドキュメンタリー映画を制作しているという。そうした縁もあってか、講義ではまず『阿賀に生きる』を上映し、そののちに早稲田大学文学学術院教授の角井誠氏を聞き手に、90分におよぶ小森さんのトークが繰り広げられた。本稿では講義における小森さんの言葉を通して、『阿賀に生きる』、ひいては佐藤真作品の持つ魅力を探っていきたい。
◾️震災時に気づいた『阿賀に生きる』の魅力
さて、1992年に発表された佐藤のデビュー作であり、代表作とも目される『阿賀に生きる』は、日本のドキュメンタリー史を語る上では欠かせない作品である。ただ、その内実、また理由については前置きとして性急に説明するよりも、小森さんの言葉からじっくりと感じていただくことのほうが大きな意味があるだろう。
多くの場で『阿賀に生きる』への強い思いを語っている小森さんだが、その出会いは大学1年生時における、映画の授業の場であったという。「その時は全然面白いと思えず、授業中に寝てしまいました」と苦笑する小森さんは、しかし2度目の出会いで、その面白さに目覚めた。それは小森さんが大学を卒業し、大学院に進学しようとする2011年の春。ちょうど東日本大震災が起きた直後で、小森さんは東北へと移住し、変わりゆく土地や人々の姿を映像で記録していく活動をはじめようとしていた。やがてその活動が『息の跡』をはじめとしたさまざまな映画作品へと結実していくが、その準備として、「その地域に暮らし、暮らしながら撮る」ドキュメンタリーを探したところ、『阿賀に生きる』へとふたたびたどり着いたのだ。

では、2度目の鑑賞では、小森さんは『阿賀に生きる』のどのような点に魅了されたのか。「出てくる人たちのいきいきした感じ」にあったという。映画の中心になるのは、3組の老夫婦。先祖代々田んぼを守り続け、日々農作業に汗を流す長谷川芳男さんと妻ミヤエさん。船大工の遠藤武さんと、そばで支える妻のミキさん。「餅屋のじいちゃん」と慕われ、じっさいに作中でも見事な餅つきを披露する加藤作二さんと妻キソさん。「映画のなかでは、やがてテロップやナレーションを通じて、この人たちが新潟水俣病という公害の患者であることがわかります。でも、それを知っても、みなさんのいきいきとしたかっこよさは揺らがない感じを覚えたんです」
そう。『阿賀に生きる』の舞台となる新潟県阿賀野川流域は、上流にある鹿瀬町(現・阿賀町)で操業していた化学工業・昭和電工が垂れ流した工業廃水によって、新潟水俣病が引き起こされた地域なのだ。阿賀野川の豊かな恵みとともに生きてきた彼らも、廃水の毒を受け、身体に障害が残っていることがしだいに了解されていく。

にもかかわらず、作品のトーンは決して悲劇的にはならない。なぜか。それはひとつには、小森さんの言葉にあるように、登場人物の「いきいきとしたかっこよさ」が画面に刻まれていることに起因するだろう。小森さんがその例として挙げるのは、遠藤武さんの表情だ。工房はすでに閉鎖していた遠藤さんだが、弟子を取ることになり、久しぶりに船づくりを再開する。弟子に指導するときの威厳に満ちた表情や、できあがろうとする船に名前を入れようとするときの誇らしげな表情が印象に残ることを語る。
また、イデオロギーには収まりきらない、日常の豊かさがたしかに反映されていることも大きいのだという。たとえば、加藤家で鍋を囲む中で、脇でキソさんがペヤングをつまんでいるシーン。「都会にはない豊かな暮らし」を強調するのであれば、やや不都合にも感じられる場面だが、むしろこのようなでこぼこにも感じられるシーンがあることで、イデオロギーに還元されない生活の豊かさが逆に浮き上がってくるのだとも。
加えて、「中断」も彩りを与える。小森さんもお気に入りのシーンとして挙げた、映画の前半、長谷川芳男さんが鮭の取り方を説明するシーンはその最たるものだろう。かつては農作業とともに、鮭の鉤流し漁を行っていた芳男さんは、用具を操りながらの説明にも熱がこもっていく。しかしそのさなか、「話しちゅう申し訳ねえども」とミヤエさんがあらわれ、じゃがいもがどこにあるかを芳男さんに尋ねる。漁の内実をつまびらかにすることのみに焦点を当てるのであれば、この中断はアクシデントともなりうる。しかし、佐藤やスタッフはそのようにはとらえず、画面の中にその「中断」を残した。むしろ、そうした予期せぬこと、その場の文脈と無関係のことが絶えまなく起きるほうが「日常」らしさではあるだろうし、それを重視したことが、『阿賀に生きる』の豊かさにつながっていることが伝わってくる。