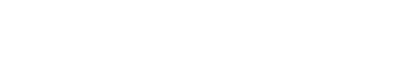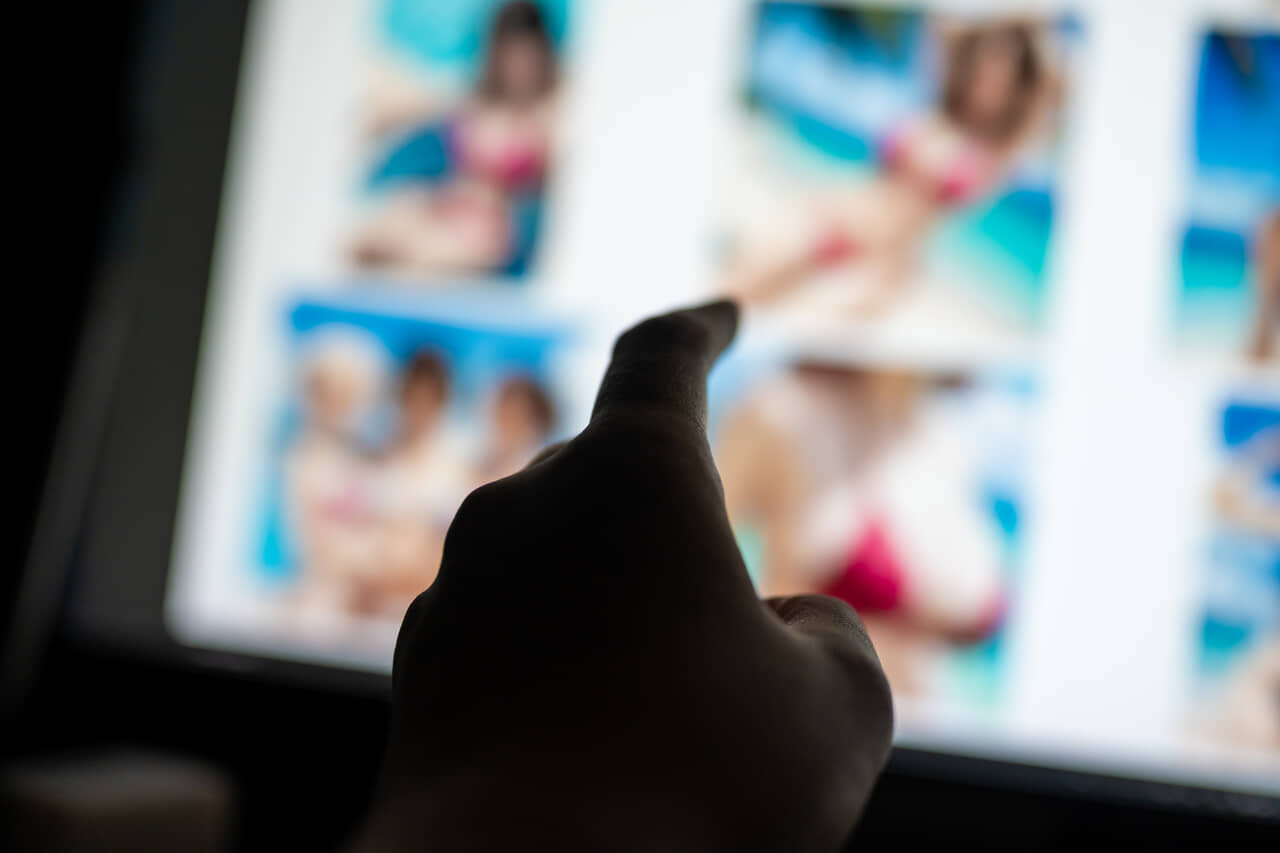ドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』はなぜこれほどまでに輝かしい人間の息吹を感じるのか? 故・佐藤真監督の眼差しとは【若林良】

◾️「他人のように思えなくなってくる」
「出てくるひとが他人のように思えなくなってくる」と、小森さんは『阿賀に生きる』について語る。それは作品の節々から、スタッフが被写体となる方と親密な関係性を築いたことが伝わってくるからかもしれない。現在は機材の軽量化が進み、スマートフォンで撮影された作品が劇場で公開されるというケースも見受けられるようになった。しかし、『阿賀に生きる』当時はまだフィルム撮影であり、作品には「フィルムをからから回す音」があらわれていることを小森さんは指摘する。「また、村の家には明るい照明があるわけではないので、ちゃんと照明を焚かないと、フィルムに映らないこともあります。ただいろりでご飯を食べるようなシーンでも、けっこう大掛かりな撮影が必要になるんですね。つまり、被写体になる方にも、はっきりと機材の存在は認識できますし、その中であんなふうに自然なかたちで撮影できたということが、本当に驚きです」
日本のドキュメンタリー史において二大巨頭と呼ばれるのは、小川紳介と土本典昭だ。本稿ではこのふたりの作家的な特色の深部に踏み込む余裕がないので、簡単な紹介にとどめるが、両者はひとつの土地に住み込み――小川であれば三里塚や牧野に、土本であれば水俣に――、そこで作品づくりを続けてきたという点で共通する。それは佐藤の『阿賀に生きる』にもまた引き継がれた作法だが、しかし、小森さんは、小川・土本との佐藤の違いも改めて強調した。「小川さんや土本さんは、その土地に住み込んで暮らす中でも、被写体となる方たちと一定の距離は置いていました。でも佐藤さんの場合は、畑仕事を手伝ったり、日常的な交流もありましたよね。政治的な戦いではなく、あくまで日常を重視した点に、佐藤さんの特色があると思います」
「日常」という言葉はここまででも幾度か使用してきたが、この言葉は佐藤の世界から決して離れたものではない。佐藤自身も、『阿賀に生きる』の成り立ちを振り返った書籍(『日常という名の鏡』)に「日常」の二文字を付しているように、そもそも佐藤の主眼は、「日常」をどのように画面に反映させるかということにあった。
では、その試みはどこからスタートしたのか。『阿賀に生きる』が作られるうえで重要なキーパーソンとなったのは、出演者でもある旗野秀人さんだ。そもそもの成り立ちを整理すると、『阿賀に生きる』の制作の起点は、1984年に佐藤が助監督を務めた映画『無辜なる旅――一九八二年・水俣』を全国で自主上映する、その旅の過程で安田町を訪れた際、安田町の水俣病未認定患者の会のまとめ役をしていた、当時34歳の旗野さんに出会ったことにあった。出会いの夜に大酒を飲んで佐藤と意気投合したという旗野さんは、上映会ののち、阿賀野川の川筋の家々に佐藤を案内し、以下のように繰り返し佐藤を鼓舞した。
「水俣病問題も、川の暮らしもどうでもいい。この囲炉裏や茶の間の出来事をそっくりそのまま撮ってもらえば、立派な映画になるんだ」
そこから、自身の映画のスタイルのテーマも、「ありきたりの日常を見つめていこう」という方向にはっきりと向かっていった――そう佐藤は振り返っている。
政治的、社会的なイデオロギーのみに還元されない、目の前の日常をしっかりと見つめること。このような姿勢は、今ではそこまで新鮮には響かないかもしれない。しかし、当時はドキュメンタリーの多くは「社会問題」を扱ったもので、とりわけ『阿賀に生きる』のように、まさに「社会問題の温床」とも呼べる土地を舞台にしながらも、かつ「社会問題」を描くことを主眼としないような作品は、ほぼ類例がなかった。
では、なぜ『阿賀に生きる』のような作品が可能になったのか。もともと『阿賀に生きる』は、いわゆる「プロ」の集団によって作られた作品ではなかった。佐藤にしてもこれがはじめての長編ドキュメンタリーの制作であったし、撮影の小林茂さんは、写真や助監督の経験はあるものの、映画撮影の経験はなかった。ほかのスタッフの方にいたっては、たとえば鍼灸師や証券会社の社員など、映画に関連したキャリアがあるわけではなく、いわば人の縁やその場のノリなどを通して、『阿賀に生きる』に携わることとなったのだ。いわば「手さぐり」であるからこそ、既存の作法を離れた『阿賀に生きる』は生まれたのだと言えるし、小森さんもまた、「経験のない人たちが手さぐりで作る、そういう風に映画を作ってもいいということに救われたし、悩み続ける勇気をもらいました」と語る。
『阿賀に生きる』の撮影をはじめた1989年には、最年少のスタッフが18歳、佐藤は32歳、最年長の小林さんが35歳だった。「30代って、けっこういい大人じゃないですか。スタッフの方たちの中にも、結婚して子どもがいた方もいて。でもそういう方たちが、3年間阿賀に住み込んで映画を作ったということに励まされます」