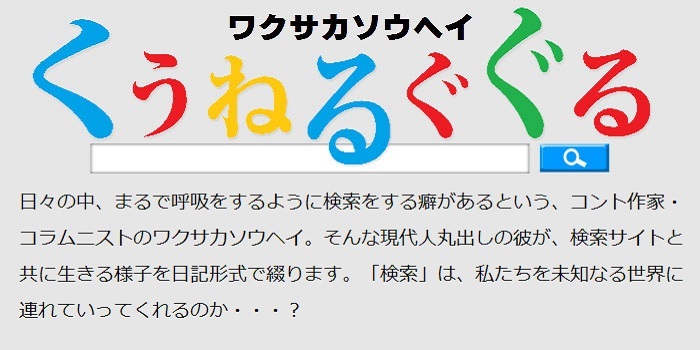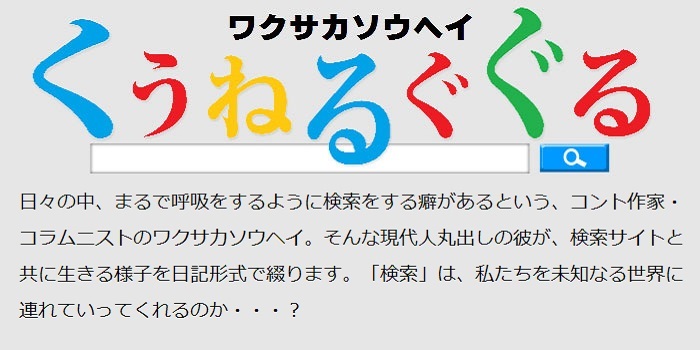第54回:「恥ずかしい」
<第54回>
10月×日
【「恥ずかしい」】
「恥ずかしい」でGoogle検索すると、思っている以上に「恥ずかしい体験談」をまとめたサイトがゴロゴロ出てくる。
やはりインターネットとは「穴」である。みんな、その「穴」に向かって「王様の耳はロバの耳ーっ!」とばかりに、誰にも言えぬ秘め事を叫ぶのだ。
ネット上の「恥ずかしい体験談」を読んでいるだけで、あっという間に時間が過ぎていく。
静かな会議中に放屁、恋人と間違えて親にLINE送信、授業中に居眠りをして大声で寝言…。
「穴」の中は、放り込まれたささやかなエピソードたちで満ちている。そのどれもが、「ゆる〜い」というか「植田まさ〜し」というか「大槻ケンヂのエッセ〜イ」といった、実に弛緩した湯加減なのである。
このぬるさがなんとも心地よく、気づけば様々な「恥ずかしい体験談」のサイトを湯めぐりしている自分がいた。
そして、サイトを巡回しているうち、あることに気がついた。
どのサイトにも必ずひとつは「先生のことを『お母さん』と呼んでしまった」というエピソードが載っている。
「先生のことを『お母さん』と呼んでしまった」。これはまさに、「キング・オブ・あるある」だと思う。
誰もが経験のある、ほのかな恥辱。
誰も傷つけない、小鳥のようなエピソード。
ああ、ぬるい。実に良いぬるさの「あるある」である。
ふと、自分の身を振り返る。
ああ、そういえば、僕もいままで何度か他人に対して「お母さん」と呼びかけてしまったことがあったなあ。
かすかに赤面しつつ、過去を想う。僕はどんな場面で、誰を「お母さん」と呼んでしまったんだっけ?
そして、記憶の絵巻の紐を解く。
小学生の頃、担任の先生を「お母さん」と呼んでしまった。
幼き日ならではの、恥ずかしくも微笑ましい体験である。
中学生の頃、隣の席の女の子を「お母さん」と呼んでしまった。
思春期の僕は、その夜、枕に顔をうずめて叫んだ。
同じく中学生の頃、友人の小林くんのことを「お母さん」と呼んでしまった。
同性を「お母さん」と呼んでしまい、顔から火を吹いた。
高校生の頃、初めて付き合った彼女を「お母さん」と呼んでしまった。
彼女の引きに引いた顔、今でも忘れない。
20歳の時、ラジオ局でバイトしていた。FAXの使い方がわからなくて近くにいた女性アシスタントのKさんに「Kさん、すいません」と話しかけようとして、「お母さん、すいません」と言ってしまった。
Kさんは「なんでこいつは急に、母親に謝罪を?」と訝しげな顔をした。「生まれてきてすいません、ということか?」と僕をまじまじと見つめてきた。
僕は僕でしどろもどろになり、二の句を継げないでいると、やっとKさんは意を得て「ああ、あたしのことを呼んだのね」と笑い、親切丁寧にFAXの使い方を教えてくれた。
その夜、僕は生まれて初めて強いお酒を飲んだ。
三年前、親類の葬式に出席する際、父親と新幹線を同乗した。
浜松を通過する辺りだったろうか。隣の席に座っている父親に対して、「お母さんさあ」と呼びかけてしまった。
名古屋を通過しても、新大阪を通過しても、あろうことか新神戸を通過しても、重く気恥ずかしい空気が父親との間に流れ続けた。
記憶の絵巻を放り投げたくなる。
「お母さん」って言い間違えた回数、多すぎる。
僕、病気なんじゃないのだろうか。
これを読んでいる方、教えてほしい。人って、生きている間に、こんなにも他人に対して「お母さん」と言ってしまうものなのですか?
それとも単に、僕がサイコパスなのですか?
ぬるい記憶を辿るつもりが、殺伐とした気持ちになってきた。
他人ごとの「恥ずかしい体験談」だと思って、弛緩した話を読んでいる気になっている、そこのあなた。油断しないでほしい。次に「お母さん」と呼ばれるのは、あなたかもしれないのだから…。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)