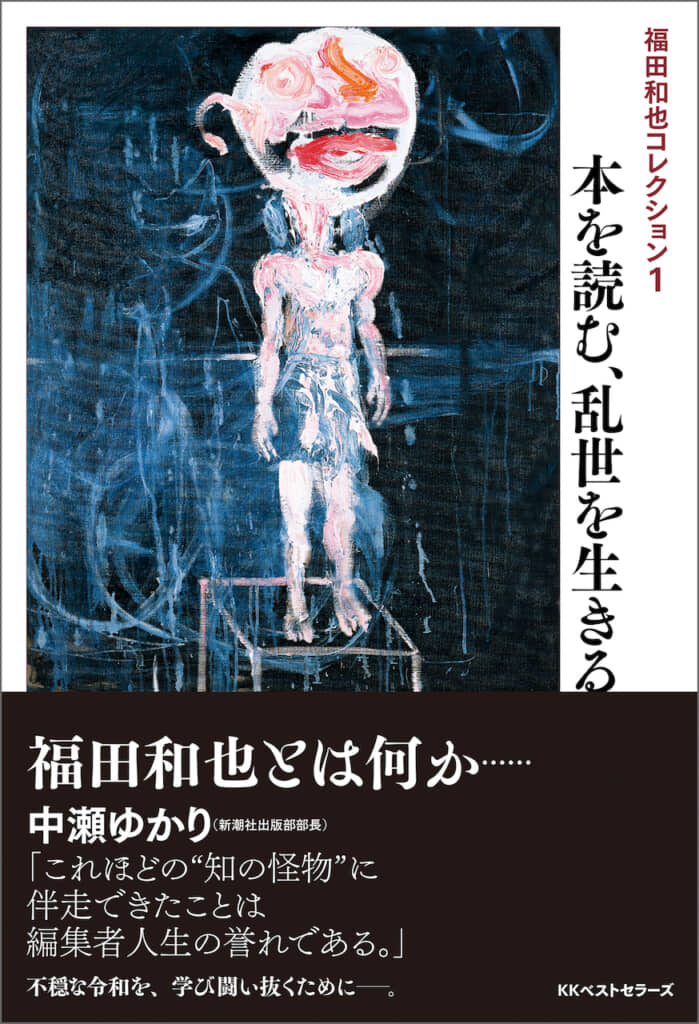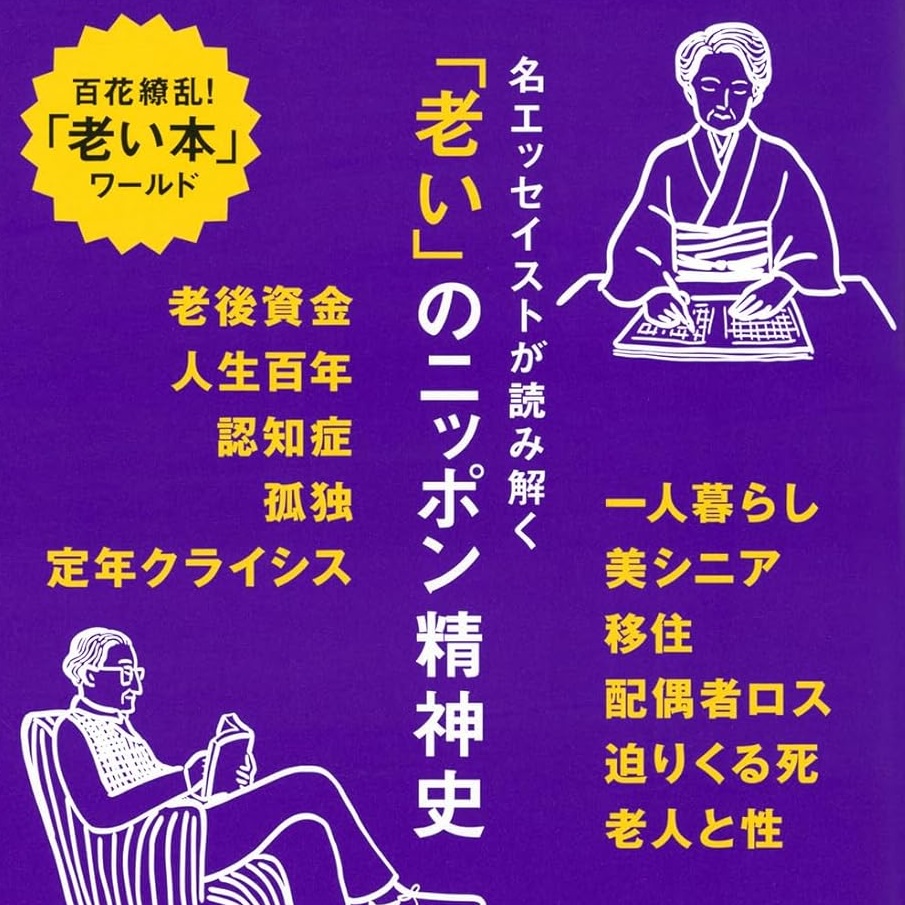横塚眞己人『さがりばな』 一晩しか咲かない花の命の輝き【緒形圭子】
「視点が変わる読書」第17回 『さがりばな』横塚眞己人 著
休憩をはさんだ後半では、朗読座の代表作である「さがりばな」が朗読された。実はこの脚本は私が書かせていただいたのだが、原作となった本が今回取り上げた『さがりばな』横塚眞己人(講談社)である。
さがりばなはアフリカや東南アジアなど、熱帯や亜熱帯に咲く花で、日本では石垣島や西表島をはじめとする八重山諸島や宮古島で見ることができる。
四枚の花弁を白や薄ピンク、ピンクのたくさんのおしべが覆い、綿毛のような形状をしている。木から垂れ下がる茎の周りに連なって咲くため、この名がついた、また「幻の花」と呼ばれるのは、咲く期間が極端に短いからである。一週間? 一日? いいや。たったの一晩なのだ。
夕方になると咲き始め、夜に満開を迎え、翌日、朝日が昇る頃には花が茎から落ちて、夜に咲いた花は全て散ってしまう。
カメラマンの横塚さんは、蕾が少しずつ開いて綿毛のような花を咲かせ、虫を介して受粉し、明け方に散っていく様子や、散り落ちた花が一面に浮かぶ川、その実が海を渡り、たどり着いた場所で芽を出すところまでを写真におさめ、それらの写真に命をつなぐ物語を添えて、さがりばなを紹介している。
貴重な一瞬をとらえた写真の一枚一枚はただ美しいだけでなく、見ていると厳粛な気分になるのは恐らく、たった一晩で散ってしまう花の命の輝きが写し取られているからだろう。
この本は2011年3月に起きた東日本大震災の直後に刊行された。刊行されてすぐ本を手にした紺野さんは、さがりばなの命のつながりの物語を朗読座の公演を通して多くの人に知ってもらいたいと思った。そこで、昔からつながりのある私に脚本の話が回ってきたのだが、脚本を書くにあたっては、さがりばなを実際に見て欲しいという強い要望があり、私は2011年7月、生まれて初めて西表島を訪れた。
東京から直行便はなく、羽田から飛行機で石垣島まで行き、フェリーに乗り換えて島に渡った。宿泊したマリンロッヂアトクは、かつてレストランでシェフを務めていたというご主人と奥さんの二人が営む民宿だった。
部屋は清潔で広々としていて風通しがよく、梅雨明け直後だというのに、冷房を使う必要がなかった。森へとつながる庭は100平米はあるだろうか。東京でのせせこましい生活とはかけ離れたスケールと風の心地よさに、私はつい、仕事を忘れそうになってしまった。
いや、しかし、さがりばなである。
さがりばなは川岸近くの湿潤な場所に自生する。花を見るためには、マングローブ林の後背地に分け入り、ボートやカヌーに乗って川を下らなければならない。一人でそんなことができるわけもなく、当然のことながらアテンドしてくれる人が必要となった。
その役を引き受けてくださったのが、琉球大学熱帯生物園研究センター教授(当時)の馬場繁幸先生だった。西表島でマングローブ生態系の研究と保全を行っている馬場先生は紺野さんと知り合いで、朗読座の脚本のためにさがりばなの取材に行くから協力してほしいという依頼を快諾してくれたのだ。
夜の8時過ぎ、先生の後についてマンブローグ林の後背地に入ると、あちこちから甘い香りが漂ってきた。「咲いてるよ」。先生のライトが照らす先を見ると、何と、さがりばながたわわに咲き誇っているではないか! 甘い香りはさがりばなから発せられていたのだった。真っ暗な夜に咲くさがりばなは強く甘い香りを発散して虫を呼ぶのだ。
自分が持っているライトをぐるりと回せば、あっちにも、こっちにも綿毛のような花が垂れ下がり、見上げれば満天の星空。横塚さんの写真で見たそのままの光景が現実のものとして目の前に広がっていた。
KEYWORDS:
✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎
『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』
国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー
学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。
文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集
◆第一部「なぜ本を読むのか」
◆第二部「批評とは何か」
◆第三部「乱世を生きる」
総頁832頁の【完全保存版】
◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)
「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。
彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。
これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」