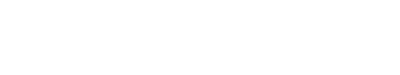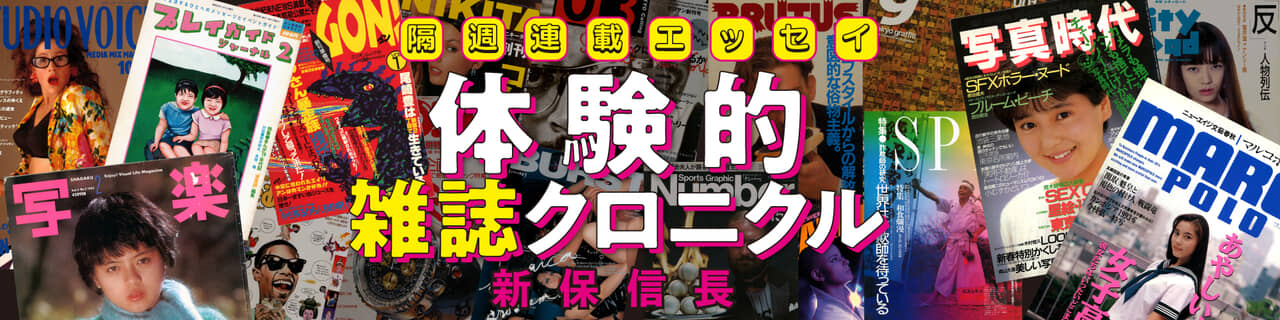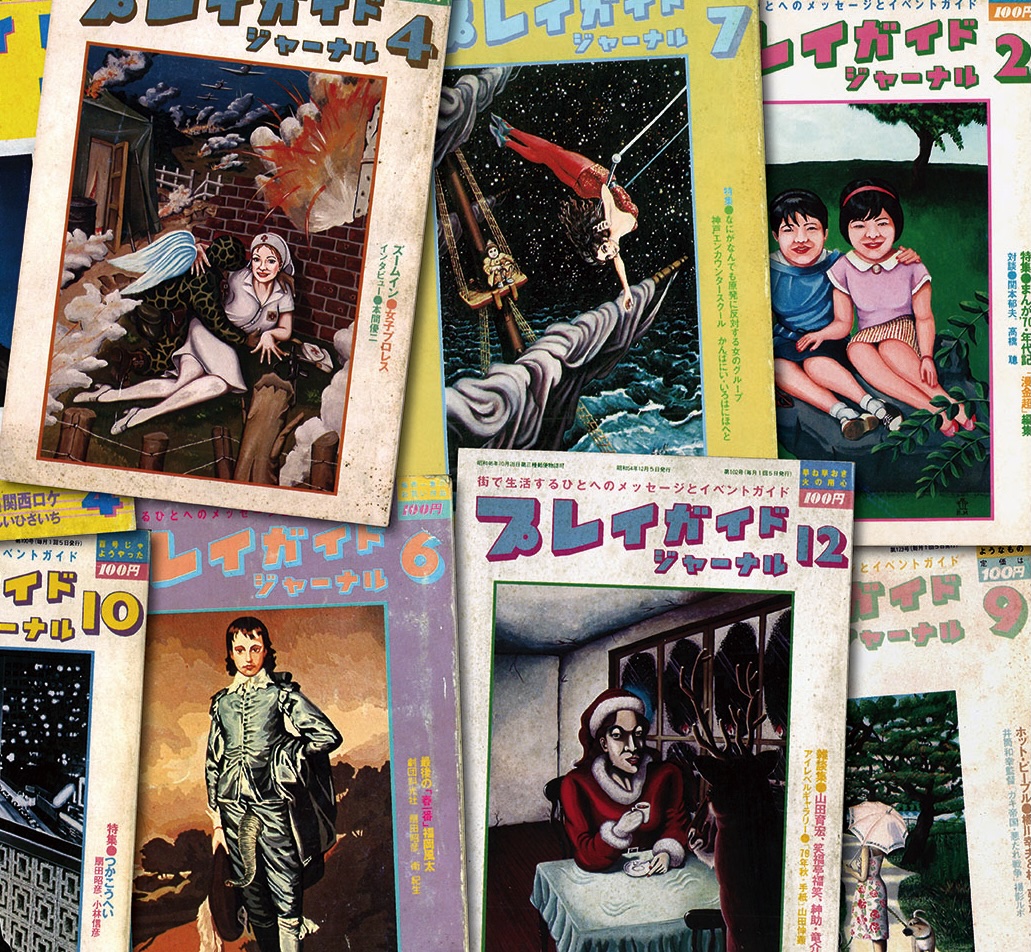『モノ・マガジン』という発明【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」7冊目
新保信長「体験的雑誌クロニクル」7冊目
さらに「モノ・コラム」「モノ・インタレスティング」などの読み物ページも、なかなかの充実ぶりだった。当時の執筆者をざっと挙げると、山崎浩一、寺崎央、押切伸一、渡邊祐、みうらじゅん、まついなつき……って、ほとんど『宝島』かというメンツである。今もそうだが、人気の書き手は、いろんな雑誌で引っ張りだこなのだ。小説家デビュー前の奥田英朗による微苦笑エッセイ「モノモノしい話」は長期連載で、人気作家になったあともしばらく続いていた。
さて、私のほうはといえば、前述の「ワープロ進化論」「カード大作戦」のほか2~3の小特集を担当したあと、『ガジェット・モノ腕時計’89』という別冊を、ほぼ一冊丸ごと任された。「人生で一番キツかった仕事は?」と問われれば、まずコレを挙げる。
巻頭特集は「マスターピースウオッチ」。アンティークを中心に40本ほどの腕時計を撮影する。類似誌とは一線を画す『モノ・マガジン』の強みとして、商品を(それこそ実物以上に)美しく魅力的に見せる写真のクオリティがあった。が、そういう撮影には時間がかかるわけで、このとき最初の1カットの照明を決めるのに8時間近くを要した。
なんでそんなにかかるのか、と思われるかもしれないが、ゴールドの時計(しかもアンティークなので細かい傷がある)を本当に艶っぽく撮るのはそう簡単ではない。当時はデジタルではなくフィルムなので、いちいちポラロイドで写り具合を確認しながらの撮影となり、それも時間がかかる要因のひとつ。一度照明が決まってしまえば、あとはそれほどでもないとはいえ、カラフルな小物と絡めたパターン、暗闇に浮かび上がるパターン、明るい光の中のパターンとページ構成上変化を付けた3つのパターンで「これだ!」というカットを40以上も撮るのは、いかに腕利きのカメラマンでも大変なのだ。

午前中に撮影用の時計を借り出し、午後からスタジオにこもって撮影。その合間に翌日以降の借り出しや取材の手配、原稿依頼などをして、深夜に編集部に戻り原稿を書く。翌日も午前中に駆り出しと返却、午後から撮影(以下同)というのが2週間ぐらい続いた。
それだけでも難儀だが、借り出す時計の中には時価数千万円のものもあり、傷つけたらどうしよう、落としたり盗まれたらどうしようと思うと気が休まらない。会社に金庫はあるものの深夜に帰ると開けられる人がいないので、家賃6万3000円の自宅アパートに持ち帰るしかなく、これまた心労のタネとなる。特集の撮影が終わっても、いざ入稿が始まるとますます作業量は増えて、1週間トータルで10時間寝られないのが3週間続き、歩きながら寝落ちしたこともあった。
そんな過酷な状況ではあったが、何しろ若かったので、どうにか乗り切れた。今どき“若い頃の大変だった自慢”が流行らないのは百も承知だが、このときの経験があったから、その後の修羅場も「アレに比べればマシ」と思えたのは確かである。体力的にはキツかったものの、自分の好きな人に取材したり原稿を依頼することができて、その点はうれしかった。というより、それこそが編集者の醍醐味であり役得であろう。
この別冊のあと、編プロからワールドフォトプレスに正式に移籍。『モノ・マガジン』通巻150号記念(1989年11月2日号)で同誌の歴史と世相を振り返る巻末企画129ページ分を担当した。そこで『モノ・マガジン』からは離れ、リニューアルした『SPY』1990年1月号から同誌編集部に籍を置くことになるのだが、それはまた別の話。