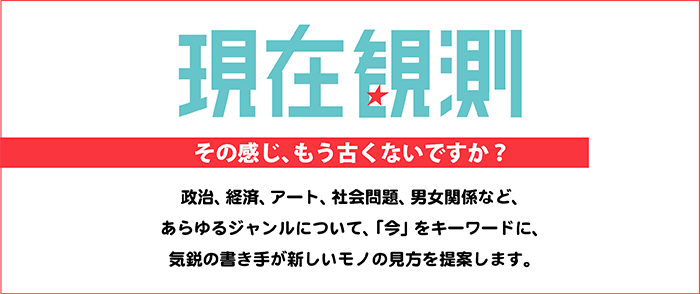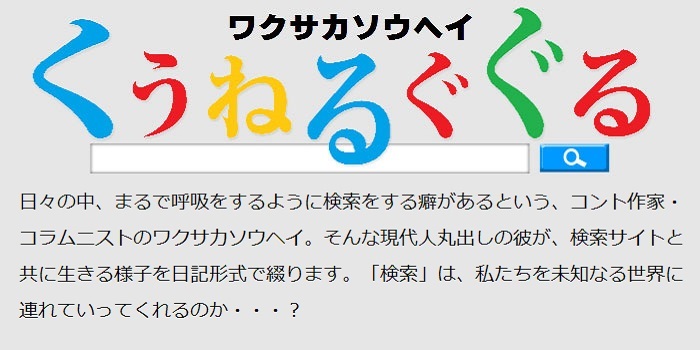「人間はどう生きれば良いのですか?」という問いに現代の哲学者は口ごもってしまう……
現在観測 第3回
二つの現代思想
一方で、19世紀末から20世紀以降の現代の哲学者たちは、大きく分けて二つの、それぞれ正反対の方向へ進む道を歩むことになる。
一つは、「究極的な真理」と「全ての人間にとっての正しい生き方」があるとする考え方を批判し、その探求を放棄する方向である。これはすなわち、伝統的な「哲学」の在り方そのものの否定にあたるのだが、大雑把に言えば、主にニーチェ、ハイデガー、フーコー、デリダといった、ドイツやフランスを中心としたヨーロッパの哲学者たちによって論じられた。これらの哲学は「現代思想」として日本でもよく知られているものである。先ほど例に挙げた「タートルネックの哲学青年」が好んで読むのは、こういった思想家たちの書物だろう。
これとは別にもう一つ、世界的に大きな影響力を持つ哲学の潮流がある。それはドイツやフランスの哲学とは正反対に、「究極的な真理」を知るための探求の方法を、近代よりもさらに厳密かつ精確なものへと磨き上げようとするという方向へ進むものであった。
その一つの金字塔となった書物が、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』である。ウィトゲンシュタインはこの本の序文で「今までの哲学は言語の論理に誤解があり、そもそも問いの立て方を間違えていたため、ナンセンスに陥っていた」という趣旨を論じ、結論部分で「語り得ないものについては沈黙しなければならない」と閉じた。
この考えに強く影響を受け、独自の学説を発展させたのが、「ウィーン学団」と呼ばれる学派を形成した「論理実証主義」の哲学者たちである。
「論理実証主義」の考え方によると、何かが「正しい」と言えることの根拠は「論理的に正しいこと(矛盾していたり不条理であったりしないこと)」と「誰の目にも明らかな形で実際に確認できること」である。
近代までの哲学は、小難しい言い回しではあるものの、基本的には日常的な言葉によって論じられている。しかし、私たちが普段、日常的に使用している言葉は、曖昧で多義的なものである。
たとえば「一休さん」には、「このはしわたるべからず(この橋を渡ってはいけない)」と書かれた立て札を見て、「端じゃなければ良い」と堂々と橋の真ん中を渡ったという「とんち」のエピソードがある。言葉を書いた者の意図と、読んだ者の理解が異なってしまうことは、実際にはよくあることだ。しかし「真理」を探求する時に、そういった誤解が生まれてしまってはいけない。そこで、論理実証主義の哲学者たちは「哲学」で用いるために理想的な言語とはどのようなものなのかということを追求した。このことによって、「言葉」と「論理」の分析を主題とする哲学の学派が誕生したのである。
論理実証主義の哲学者たちは、当初はオーストリアのウィーンを中心として集まっていた。しかし、1930年代のナチスの台頭により、多くの哲学者たちは、アメリカなどへ亡命していった。
また、先にケンブリッジ大学に職を得ていたウィトゲンシュタインや、その師匠にあたるラッセルなどの影響もあり、イギリスでも同じようなスタイルの哲学が主流となっていた。
このような経緯から、もともと経験主義の伝統が強かったイギリス、アメリカといった英語圏において、20世紀中頃以降、「哲学」といえば言語や論理を主な対象とする「分析哲学」と呼ばれるスタイルのものがほとんどになったのである。
哲学の本といえばカントやヘーゲルのことについて論じているというイメージがあるかもしれないが、分析哲学の哲学者が論文や著書の中でそういった過去の人物の思想を主題として扱うことはほとんどない。
それは、最新の物理学者がいちいちガリレオやニュートンの理論を論じることがないのと同じで、分析哲学の哲学者の意識としては、カントやヘーゲルの思想は、「哲学史」の中の偉大な人物ではあるものの、最新の哲学の主題となるものではないからである。
そういった点から見れば、英語圏における「哲学者」とは、黒板や紙に一心不乱に数式を書き続け、非論理的で情緒的な思考や根拠の無い議論をナンセンスなものとして排除するような「数学者」や「科学者」というイメージが近いかもしれない。