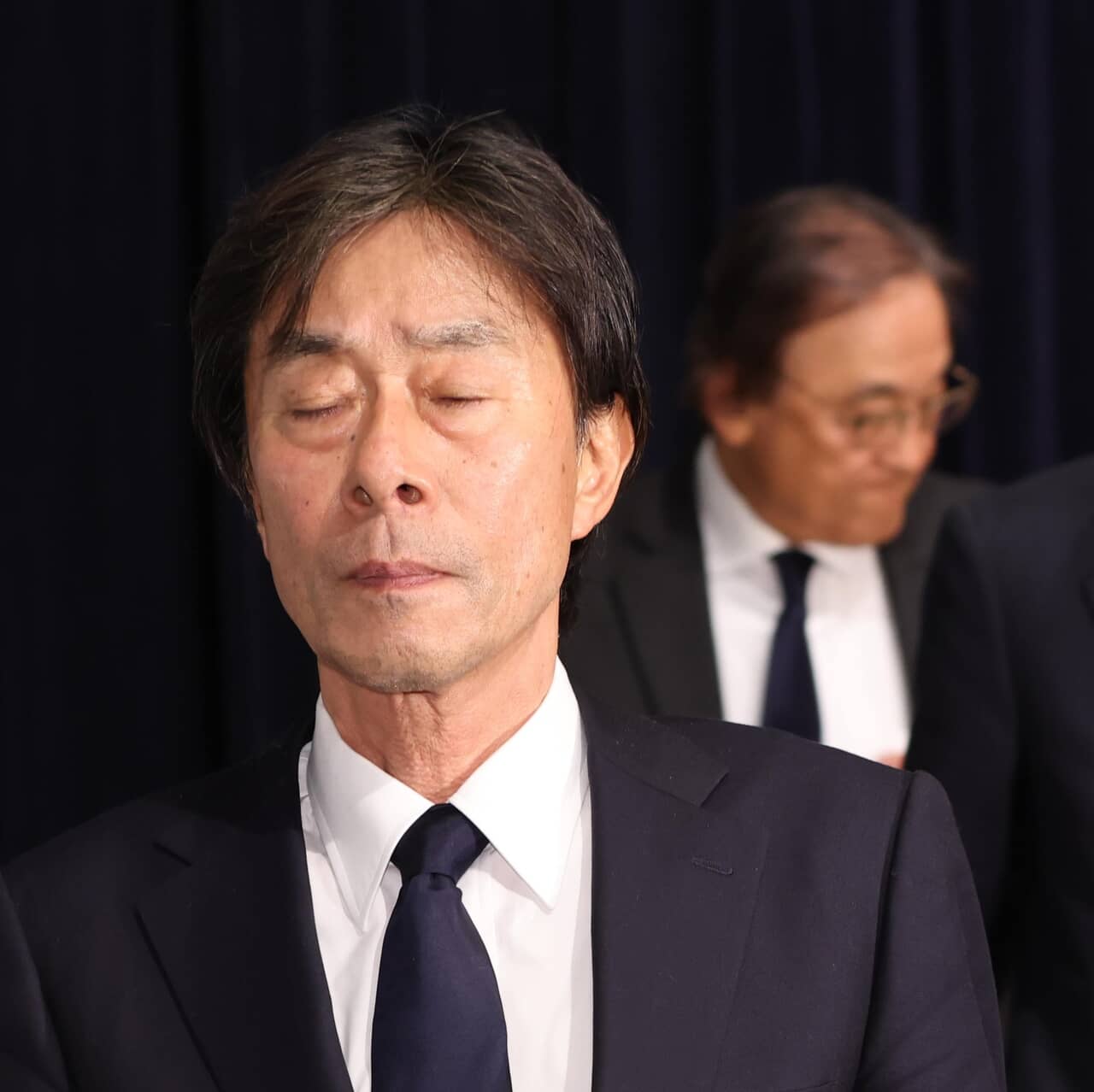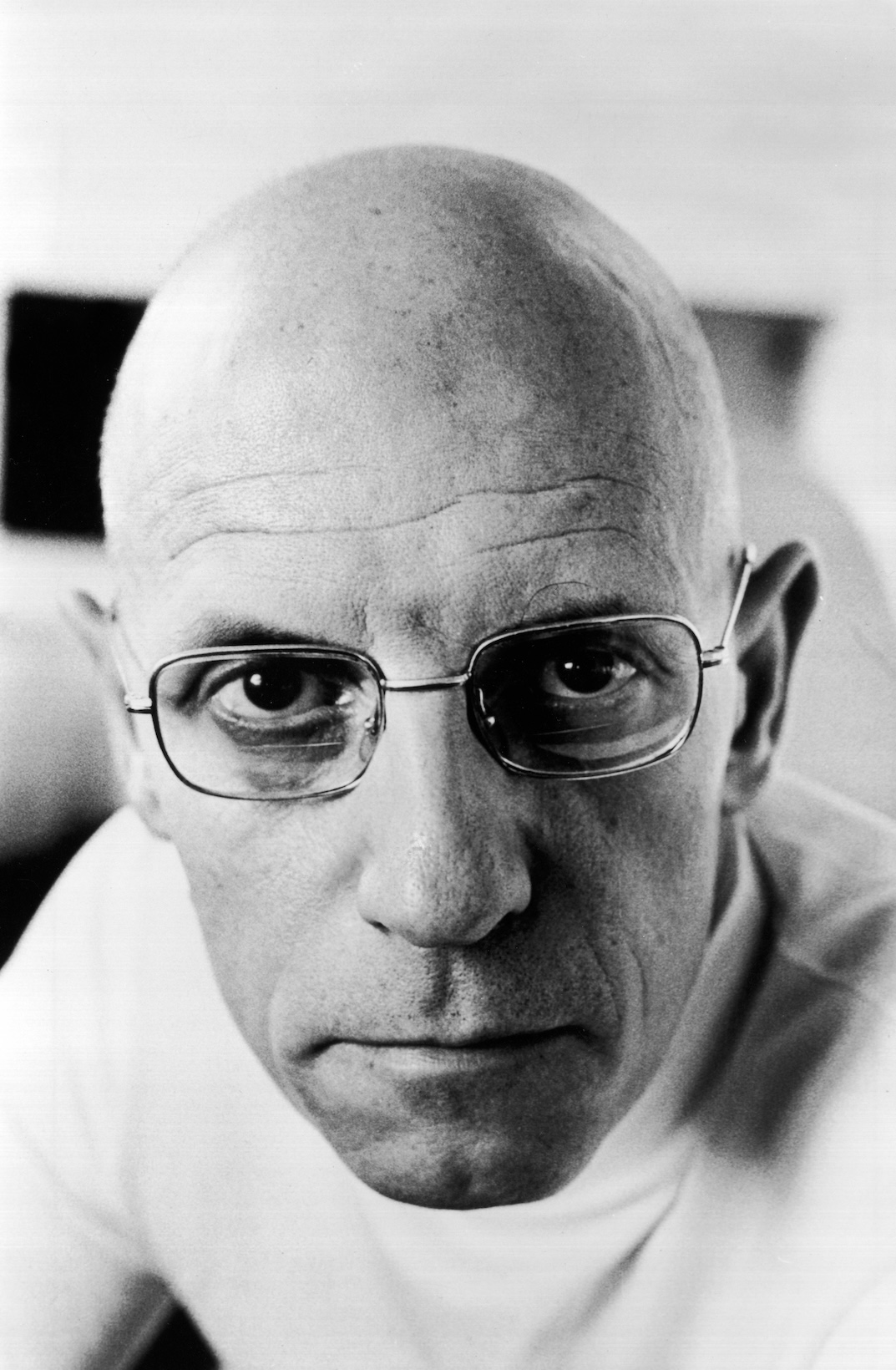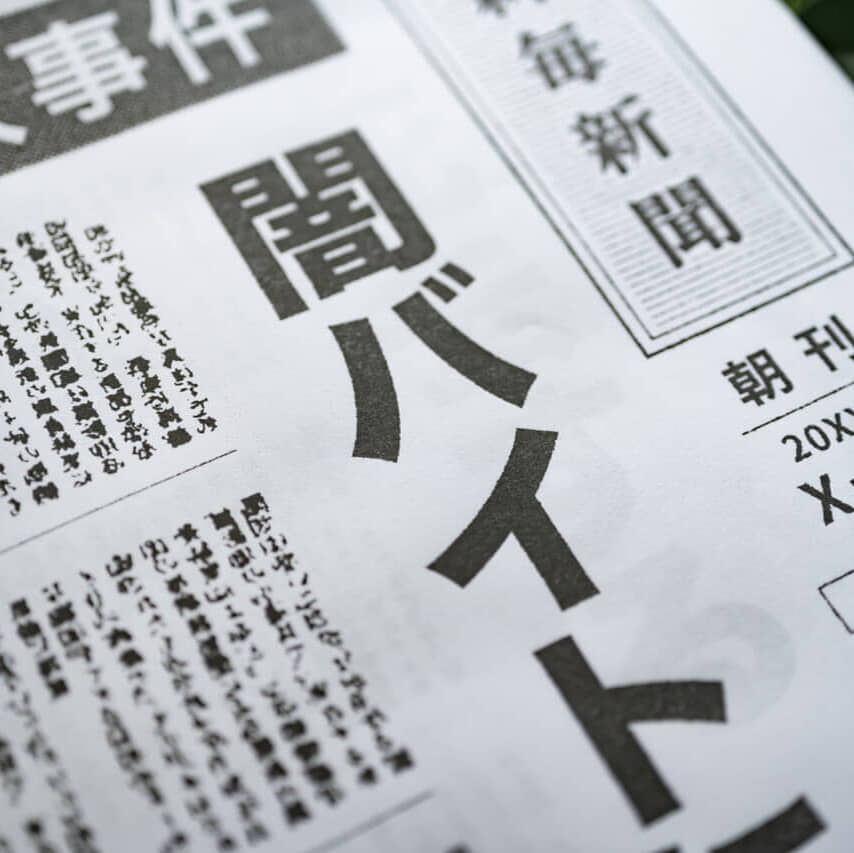自発的に性産業で働いている人たちのことをフェミニズムは一体どう考えているのか?【仲正昌樹】
「ポルノと女性の権利」についての考察1
■幸福とは何かを自分で決め、自分で追求することは可能か?
近代法では、自分の幸福とは何か自分で決め、自分のやり方で追求する幸福追求権が、あらゆる権利の基礎とされているが、それを実行するには、経済的な基盤や他者からの承認もさることながら、アイデンティティ形成の基盤となる本人の「想像界」が重要だ。例えば、それまで〇〇教の信者として自認して、教団の中で生活し、それ以外の人生は想像できなかった人が、何かのきっかけでその教団を出たいと思うようになっても、信者でない自分の生き方をそう簡単には想像できないかもしれない。そこにはもう居たくないと思っても、外で生きる自分の生きる目的をどう設定したらいいか分からない。そうしたことは多かれ少なかれ、ほとんどの民族的・ジェンダー的慣習、家庭生活、職業、趣味について言えることである。
コーネルはポルノワーカー、特に幼少時のトラウマ的な体験が「想像界」に強く影響し続け、ポルノワーカーとしてのアイデンティティと結び付いているような人にとって、いきなり違う生き方を選ぶのは難しいと指摘し、新しい生き方を選ぶようパターナリズム的な圧力をかけるべきではないという立場を取る。
コーネルは「自己決定」を行うための基礎として、他者とよりポジティヴと思える関係を築きながら「想像界」を再創造するための権利が、特に困難なアイデンティティを抱えた人に与えられるべきだとし、それを「イマジナリーな領域への権利 the right to the imaginary domain」と呼んでいる。具体的には、コンシャネス・レイジング・グループなどに参加し、演劇等の自己表現活動に関わるなどし、自分にとってしっくりくる自己のイメージを形成し直す余裕を与えられることである。
広い意味でのカウンセリングのことかと思う人が多いかもしれないが、「想像界」が様々な人々の言語化される以前――言語化されたものは、「象徴界」の管轄――のイメージのやりとりによって形成されるものである以上、一対一の――それもカウンセラーの方が父の代理のような位置を取る――言葉のやり取りによってクライアントの心的領域にほぼ一方的に操作を加えるカウンセリングは、「想像界」の再編にとって必ずしも有効な手段ではなかろう。言葉よりもイメージだ。
セクシュアル・ハラスメントは、ハラスメントを受ける側の「イマジナリーな領域への権利」侵害と捉え直すことができる。自分らしい性的なイメージを発展させることを、権力行使によって妨げられるからである。対価型、何かの報酬と引き換えに、または制裁をちらつかせることで相手を性的に従えようとするタイプのものではないセクハラ、女性差別的な言動とか、卑猥なことを語ったり、見せたりする環境型セクハラの場合、どういう権利が侵害されたのか考える際、「イマジナリーな領域」を想定すると、議論が分かりやすくなる。