「ポルノ表現は保護されるべきものか否か?」 前衛芸術と「公/私」の境界線への挑戦【仲正昌樹】
「ポルノと女性の権利」についての考察2

■ポルノ規制を主張する人の多くが望んでいること
一九七〇年代から二一世紀の始めにかけて最も強い影響力を発揮した法哲学者ロナルド・ドゥウォーキン(一九三一-二〇一三)に、「ポルノへの権利はあるのか」という論文がある。タイトルから予想されるように、ドゥウォーキンは、ポルノは表現の自由等の自由権的基本権によって保護されるべきものか、そんなものはないのか問うている。
憲法の「表現の自由」で保護される「表現」とはそもそもどういうものか、それにポルノは含まれるのか、それを表現することが誰にとってどういう利益があるのか、ポルノとはそもそもどういうものか、規制すべきだとすればポルノ全てか、ある特定の種類のものか、そしてどのようにかといった問題を、英国の内務省の検討委員会の報告やミル(一八〇六-七三)の『自由論』(一八五九)などを参照しながら詳細に検討している。興味深い論点が多々取り上げられているが、私がここで取り上げたいのは、公/私の境界線への挑戦をめぐる問題である。
標準的な近代自由主義の理論は、「公/私」の区分を前提とする。「公的領域」というのは、不可避的に多くの人が関わっているので、国家の政策によって人々の行動が規制され、みんなで共通の方向を目指すのが当然とされる領域である。「私的領域」とは、自分だけ、あるいは、多少無作法に振舞っても許し合える家族やごく親しい人たちとの関係だけで構成される領域である。両者の区別は純粋に空間的なものではないが、空間的に分かりやすく言えば、前者と想定されるのは、議会など会議の場、公共の施設や交通機関などであり、後者と想定されるのは、個人の家、特に個人が使用できる部屋である。
公的領域では、公共の福祉のため、個人の自由はお互いの迷惑にならないよう、国家の事業の妨げにならないよう制限される。それに対し私的領域では、明らかな犯罪を除いて、可能な限り第三者、特に公権力からの干渉を受けないで放っておいてもらう権利があると見なされる。事情が許す限り、「私的領域」を拡大して、個人が自分のライフスタイルを選べるようにするのが、近代自由主義の大前提だ。「公的領域」が拡大しすぎると、自由主義社会ではなくなる。
無論、そうは言っても、私的領域/公的領域の境界線は常にはっきりしているわけではない。会社、学校、●●同好会のようなものの中の人間関係は、公共的性格と私的性格が混じっているので、錯綜としている。「ハラスメント」というその適用範囲が曖昧な概念が法的に通用しているのは、境界線が曖昧だからだ。
ポルノ規制の問題は、この公/私の境界線と密接に関係する。ドゥウォーキンは、自分がポルノを見ている人でも、子供がポルノを目にするのは好ましくないと考え、ポルノ規制に賛成する、という単純な事実に注意を向ける。それは、彼らにとって「ポルノ」は私的(private)にこっそり見るものであって、子供などが簡単に眼にする公共の場から隠されるべきだと考えているからである――英語の〈private〉には、「秘密裡の」という意味合いもある。
そこから類推すると、ポルノ規制を主張する人の多くは、ポルノの全面禁止を望んでいるわけではなく、不特定多数の人、特に子供が簡単に見ることができる公共の場で、ポルノが上映されたり、グッズが販売され、広告が堂々と展示されたりすることが許されない、と見ているわけである。セックスに関係するものは、私秘的(private)であるべきで、プライベートな空間で他人の迷惑にならないようにこっそり見るのであれば、許される、という考えの人が多いということだろうか。


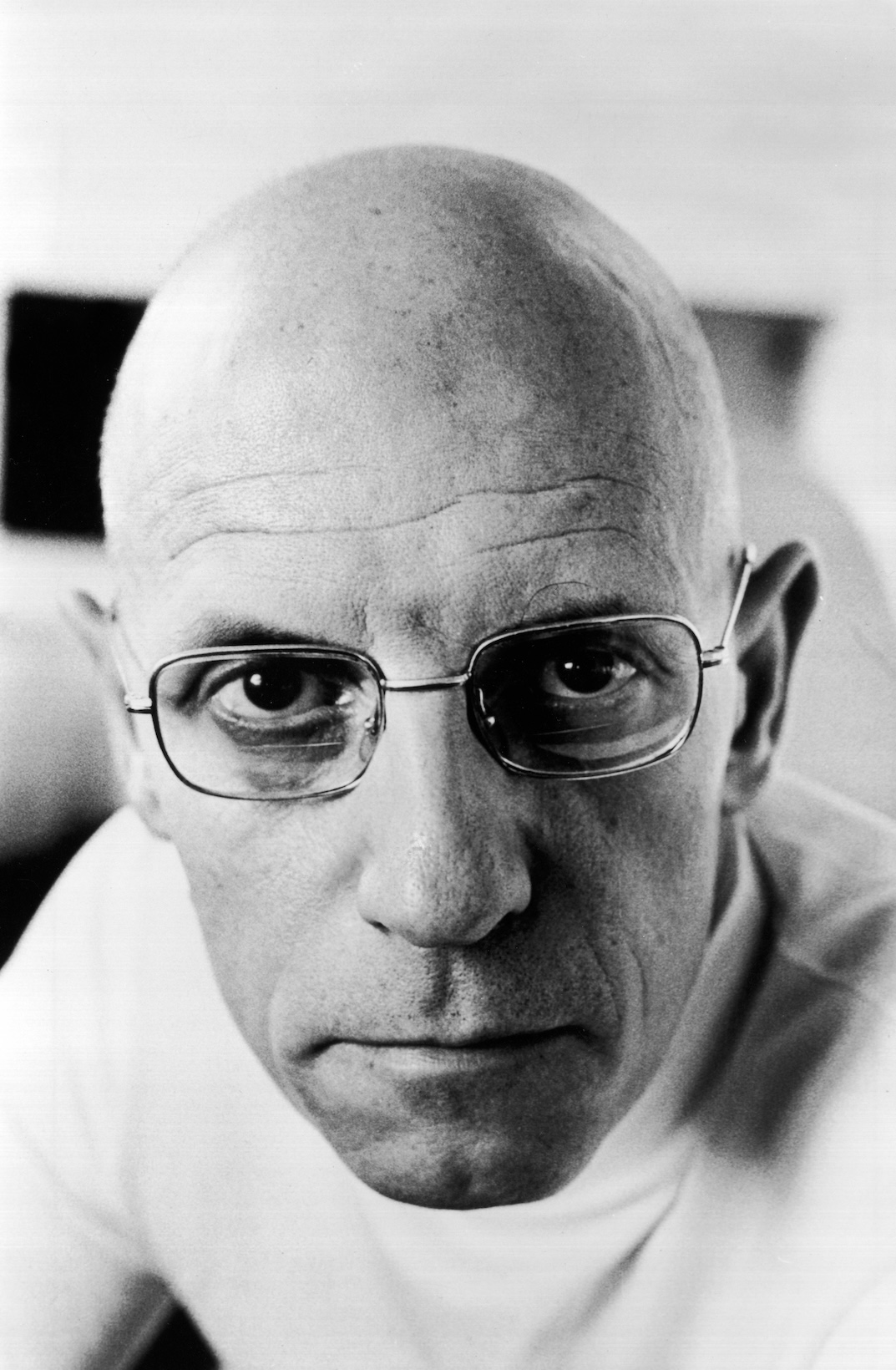

産経のコピー.jpg)




