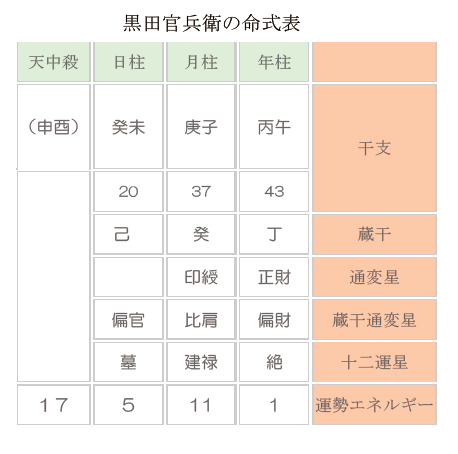なぜ今、日本でマリー・アントワネットが注目されているのか?
アントワネットを介して見える、「歴史の逆輸入」
アントワネット、親子で愛した「日本の美」
さて、私たちが彼女を知っているのと同じように、彼女もまた日本を知っていた。王侯貴族の常として、権力の誇示や趣味のための美術品のコレクションは欠かせないものだが、アントワネットの美術工芸品コレクションの3分の2は、なんと日本の「蒔絵」であった。漆の黒に映える金――、アントワネットといえばピンクやリボンといった華やかなロココのイメージが強いなかで、これはなかなかに渋いチョイスだ。
実は、彼女の母親マリア・テレジアは、宮殿内に「漆の間」をつくるほど無類の漆器愛好家として知られ、アントワネットも幼少の頃から漆器に慣れ親しんでいた。
1780年、最愛の母が亡くなり、形見として50点あまりの漆器コレクションがアントワネットに遺贈される。彼女はそれらを飾るためのガラスの飾り戸棚を発注し、部屋全体の内装も改装して、「漆の間」ならぬ「黄金の間」をつくりあげた。
先述の「マリー・アントワネット展」でもいくつか展示されていたが、現在ヴェルサイユ宮殿には、アントワネットが集めた70点あまりの漆器コレクションがある。文箱、硯箱、重箱などにはじまり、雄鶏をかたどった小箱や、リスの姿があしらわれた収納箱などの可愛らしいものも。犬をかたどった蒔絵は、ずっと猫だと勘違いしながらも彼女のお気に入りのひとつだったという。
また、フランスを代表する磁器「セーヴル焼き」の販売会がヴェルサイユ宮内で催された際、アントワネットは華やかに目を引く青と金で装飾された食器を見つける。スープ鉢やボトル・クーラー、平皿などからなるその食器セットは、色使いや絵柄の構図などが日本の伊万里焼に近しく、<日本>とのタイトルがつけられていた。彼女にとっては、崇拝する母を思い起こさせるものだったのかもしれない。その食器セットを自ら購入し、母の喜ぶ顔を思い浮かべながら祖国オーストリアへと贈ったのだ。
一般的にヨーロッパで言われるジャポニスムは、19世紀中頃から。1867年に開かれたパリ万国博覧会を機に、日本ブースに並ぶ浮世絵や漆器、扇子などの大胆で繊細な美が西洋の人々の心を掴み、「ジャポニスム(日本趣味)」として流行した。
しかし蒔絵は、16世紀、布教のためにやって来た宣教師や貿易で訪れるスペイン・ポルトガル・オランダの商人たちによって海を渡り、貴族社会で高級品として好まれたのだ。徐々に彼らは“西洋”と“蒔絵”をコラボさせ、西洋家具の表面に蒔絵を施すなどの新境地を開いていくが、そのような中で純粋に日本で使われていた漆器がコレクションに入っている様子は、アントワネットの日本愛を感じさせる。
日本人はフランス人以上にフランス革命を知っている
『ベルばら』のおかげで、世界史もフランス革命の授業だけは楽しかった――、時を経て翻訳本が出版されると、それは海を越えた本場フランスでも同じ現象が起こる。
「『ベルばら』でフランス革命を勉強しました」
「贅沢な悪女だと思っていたアントワネットの本当の一面を知ったの」
これは、『ベルサイユのばら』の作者である池田理代子氏が実際にフランス人から聞いた言葉である。
『ベルばら』などのエンタメ作品によって、もしかしたら現代の私たちは、本国よりも彼女の真実の姿を知っているのではないだろうか。フランス人以上にフランス革命を知っているのではないだろうか。
教科書では一瞬で終わってしまう出来事が、「漫画文化」の根づく日本において深く掘り下げられたことにより人間味を帯びてくる。異国の、しかもはるか昔の彼女に、私たちは親しみを感じるのである。漫画に夢中になった女性たちが親となり、子へと薦め、その世界観に魅了されていく人が世代を超えて増え続けていく。
なぜ今、日本で最大規模のアントワネット展が開かれたのか。それは、この展覧会が日本でこそやってしかるべきものだからだ。
そして興味深いことに、「国の歴史をその国の国民が一番わかっている」とは限らないのだ。
- 1
- 2