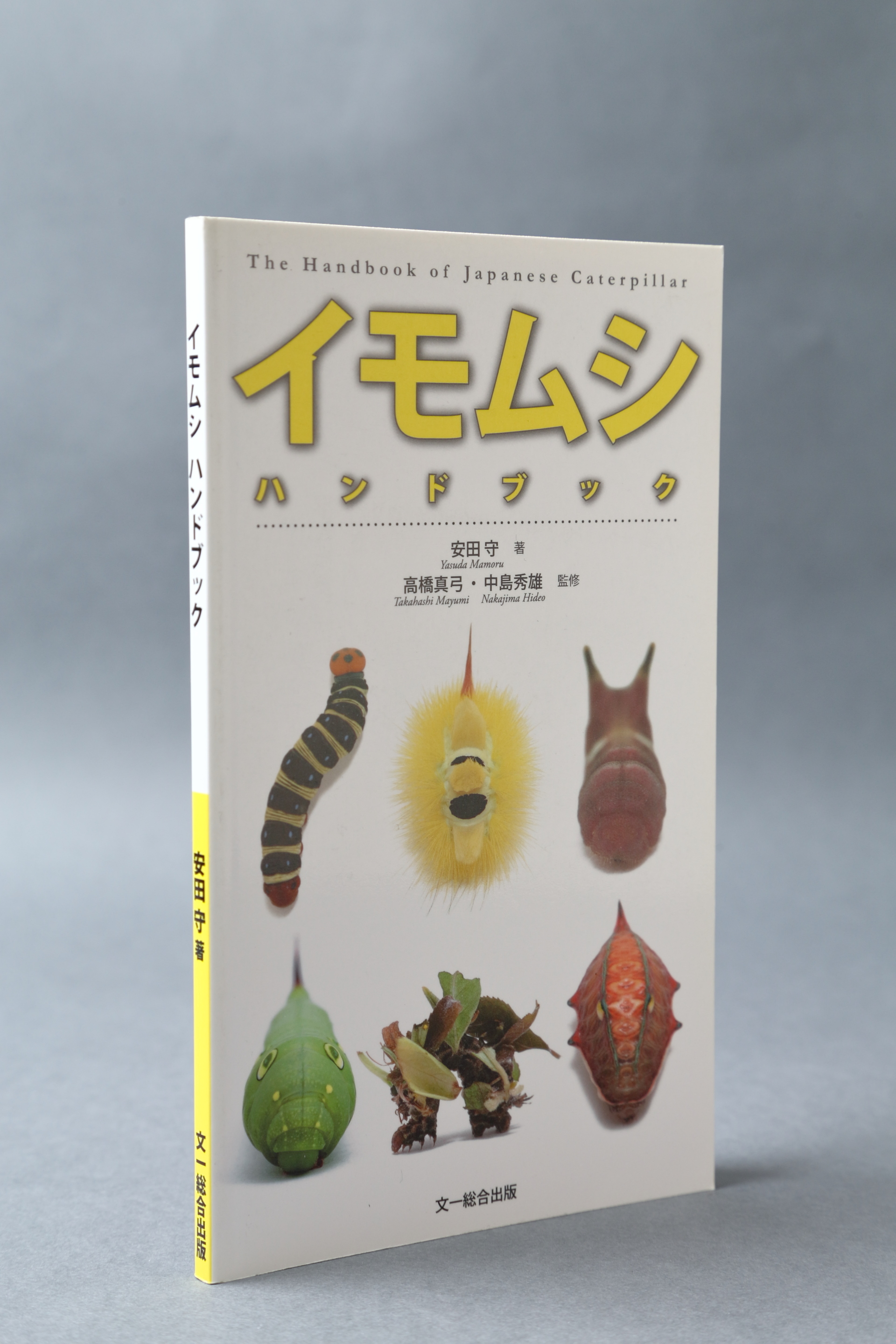『ナルニア国物語』が救った、芥川賞作家・柳美里の少女時代
第2回「柳美里書店の10冊」
「将来、南相馬市に書店を出したい」
そう話すのは作家の柳美里氏。柳氏にとって作家デビュー30年、
『人生にはやらなくていいことがある』刊行に際し、「
出版関係者や読者からは「
まだまだ本にはできることがある。
辛い現実世界が後ろに退いていった
本って不思議な存在だな、と思います。
紙に書いてある文章は同じでも、読む人によって頭の中で思い描くことは大きく異なるし、同じ人が同じ本を読んだとしても、何年か経って再読すると、全く異なる感想を抱くこともあるからです。
読みながら、忘れかけていた自分の記憶と引き合わせられる時もあるし、実人生以上に濃密な体験をしたような心持ちになることもあります。
本の最後の頁をめくり終えることが終着点なのではなく、本の中の言葉やイメージからの働きかけが、現実世界に新たな道を拓くこともあります。
その逆に、現実世界で八方塞がりになった時に、いつでも一時避難所になってくれる本もあります。
今回は、そんな本を紹介します。『ナルニア国物語』です。
わたしは小学校入学と同時に、激しいイジメに遭いました。
わたしのあだ名は「バイキン」でした。
運動会のフォークダンスの練習では、男子たちは指でバリアを拵え、わたしと手を繋ごうとはしませんでした。
全員参加のクラス対抗水泳リレーでは(ひとり25メートル泳ぐ)わたしの時だけ「Aちゃん、がんばっれ!」の声援が、「やっなっぎ、オェーッ!」に変わりました。
わたしのよそった給食のシチューは「バイキンが染るから」という理由で、クラス全員が食べることをボイコットして、困り果てた若い女性の担任教諭はわたしを給食当番からはずしました。
授業中は、全員が黒板を見ているからイジメは起こらないのですが、休み時間になると、体を硬くして黙って座っているしかないわたしに、クラスメイトの誰かしらの視線が突き刺さり、「バーイキン! バーイキン!」とバイキンコールをされる中で、消しゴムのカスを頭に振りかけられたり、前後の机を狭められてサンドイッチのように机に挟まれたりするのが堪え難く、わたしは授業と授業の間の短い休み時間は窓から上半身を乗り出してチャイムが鳴るのを待ち、昼休みは廊下を早足で歩いて図書館のいちばん奥の書棚の陰に身を潜めていました。

そこで出会った本が、『ナルニア国物語』だったのです。
4人の子どもたちが空襲を避けてロンドンから田舎に疎開をする、という辛い現実世界から物語は出発します。
子どもたちが疎開先の老学者の大きな家を探索し、鏡のついた衣装ダンスの中に入り、その奥にある雪の森に通じる――、というシーンを読んだ時、わたしは自分が身を置いている辛い現実世界が後ろに退くのを感じました。
わたしは『ナルニア国物語』を借りて、家で読み耽りました。
白い魔女との戦い、ライオンの姿をした救世主アスランの受難、ナルニア国の一員となる子どもたちの運命を、布団の中に懐中電灯を持ち込み読み進めました。
『ナルニア国物語』は、わたしが生まれてはじめて寝る間を惜しんで読んだ本です。
大人になってからも、辛いことがあるたびに『ナルニア国物語』を開いています。
20年前、十二指腸潰瘍と出血性胃炎を併発して2ヶ月にわたる入院生活を送った時は、病床で第6巻『魔術師のおい』の「世界と世界のあいだの林」を読んで、涙があふれて止まらなかったのを憶えています。
「これほど静かな林は、考えられないくらいなのです。鳥もいない。虫もいない。けものもいない。風もありません。あんまり静かすぎて、木がすくすく育つのが感じとれるくらいでした」
あの時のわたしは、小学生だった時と同様に、世界と世界のあいだの林の「池のふちのやわらかな草の生えた地面」に横たわり、なにもかも忘れてしまいたかった――。
いま読み直したら、自分がなにを感じるのか――、久しぶりに『ナルニア国物語』を読んでみようと思います。