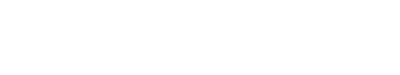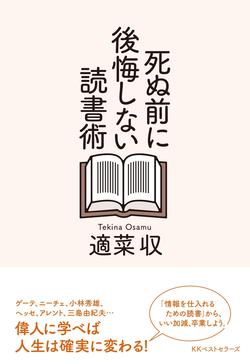「儒教」は、宗教? 宗教ではない?
中国人の「宗教観」とは?
「中国」がこんなにも存在感を増しているのに、私たち日本人は中国人のことをあまり知りません……。
中国人は何を信じてきたのか? あの国を動かしている根本原理とは何か?
なぜ日本人の「常識」は彼らに通じないのか?
「第23回山本七平賞」作家・石平先生が、「拝金主義」に毒された現代中国人の“心の闇”を解き明します―。
中国人は何を信じてきたのか? あの国を動かしている根本原理とは何か?
なぜ日本人の「常識」は彼らに通じないのか?
「第23回山本七平賞」作家・石平先生が、「拝金主義」に毒された現代中国人の“心の闇”を解き明します―。
「世界三大宗教」とはご存知の通り、「キリスト教」「イスラム教」「仏教」の3つを指す。全世界に、キリスト教は20億人、イスラム教は13億人、仏教は3億6000万人の信者がいるとされている。
中国における三大宗教(「三(さん)教(ぎょう)」)とは、「儒教」「仏教」「道教」のことである。
「儒教」は、孔子(こうし)が体系化した思想で、周の時代の「礼」を理想としている。「仁・義・礼・智・信」という5つの徳性(五常)を磨けば、五倫(君臣の義、父子の親、夫婦の別、長幼の序、朋友の信)が保てると説き、この「五倫五常」が儒教の教えの基本となっている。
キリスト教やイスラム教には神が、仏教には仏という絶対的な存在が君臨しているが、儒教にはそれに値するような絶対的な存在はいない(必ずしも、仏は絶対的な存在とは言えないが)。
儒教の創設者である孔子は、「鬼神語らず」という言葉にもあるように、生涯に渡って神も、鬼も語ることはなかった。
また、儒教は死後の世界にもまったく関心がない。儒教には来世という概念がなく、人間は死んだらそれまで。弟子から「人間は死んだらどうなるのか?」と聞かれた孔子は、「生きることさえよくわからないのに、どうして死がわかるというのか」と答えたという。仏陀も死後の世界を語らなかったが、孔子とはそのニュアンスが微妙に違うように思う。
要するに、儒教にとって死や死後のことはどうでもよく、「現世をどう生きるか」が問題なのである。
「儒教は宗教ではない」とよく言われる所以(ゆえん)がここにある。儒教は宗教としての要素があまりにも欠けているのだ。

では、儒教は私たちに何を教えてくれているのか。儒教は「君子の理想」を説きながら、「理想的な人間はこうあるべき」ということを教えている。
孔子の『論語』では、様々な場面で「親孝行でなければならない」「穏やかでなくてはならない」「友達には誠実であるべきだ」といった、「人間のあるべき姿」について触れられている。
孔子の『論語』では、様々な場面で「親孝行でなければならない」「穏やかでなくてはならない」「友達には誠実であるべきだ」といった、「人間のあるべき姿」について触れられている。
礼儀正しく、智恵者で、円満な人格(信、義、礼、智の徳目)を持っている人。それが儒教の理想とする「君子」なのである。
儒教は「君子たるもの~」といった具合に、理想の人間像を描くことで道徳倫理の規範をつくってきた。
儒教は「君子たるもの~」といった具合に、理想の人間像を描くことで道徳倫理の規範をつくってきた。
だが、儒教には「教えを実践したらその後、どうなるのか」という「保証」が何もなかった。そうなると、「私は君子になんぞなれないし、なりたくもないから儒教の教えはどうでもいい」という人間が当然のことながら出てくる。古くから実利主義的傾向の強い中国の庶民に儒教はなかなか受け入れられなかった。
さらに儒教を庶民から遠ざけた大きな理由がもうひとつある。それは「科挙制度(一般から有能な人材を登用するシステム)」の登場である。
科挙制度が完成した宋の時代には、儒教の経典が官僚になるための試験に用いられはじめ、清王朝に至るまでの間、歴代王朝の知識人が勉強しているものといえば儒教であった。
科挙制度が完成した宋の時代には、儒教の経典が官僚になるための試験に用いられはじめ、清王朝に至るまでの間、歴代王朝の知識人が勉強しているものといえば儒教であった。
しかし、科挙制度が長引けば長引くほど、儒教は「試験に受かるためだけのもの」「知識人だけのもの」となり、「仁・義・礼・智・信」を説く儒教の理念も次第に形骸化し、庶民の間に儒教が浸透していくことはなかった。
<『中国人はなぜ「お金」しか信じないのか』(石平/著)より抜粋>