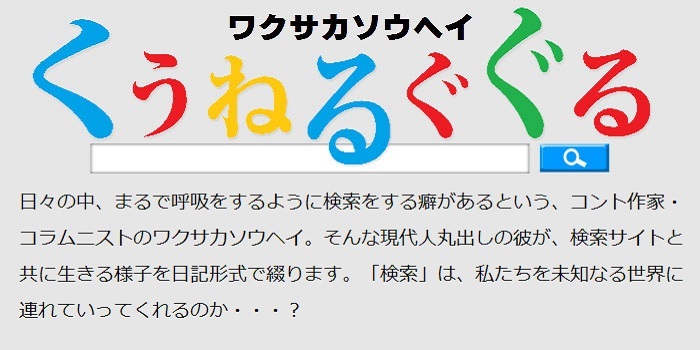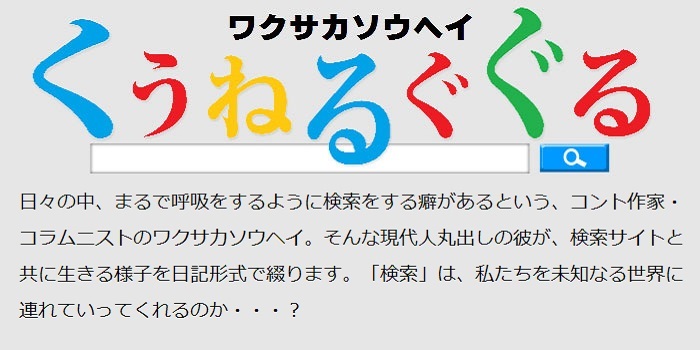第70回:「東京駅 おでん」
<第70回>
2月×日
【東京駅 おでん】
そんな感じでBARに連敗続きの日々を送ったわけだが、実は20代の頃、バーテンダーのバイトをしていたことがある。
といっても、カウンターの上に平気で少年マガジンが置いてあるようなBARだった。
仕事内容もひどかった。バイト初日にそこのマスターが「じゃあ、あとよろしく」と店の鍵だけを置いて、ひとつもカクテルの作り方を知らない僕にすべてを任せて帰ってしまったのだ。
ポツポツとくる客の注文に対して、右脳だけでカクテルを作った。意外となんとかなった。バイトを始めて2週間ほど経つと僕は完全にバーテンダーという仕事をナメ始めて、カルアミルクを水で割ったものや、ワインを水で割ったもの、挙げ句の果てにはお湯を水で割ったものなどを平然と提供するようになっていた。で、さすがに客から「とんでもないH2O原理主義のバーテンダーがいる」という苦情がマスターに入り、クビになった。
今日は東京駅で友人たちと食事をする約束をしていた。
駅に集まり、寒いしおでんでも食べるかと、「東京駅 おでん」で検索。近くの大丸の上階におでんを食べられる店がありそうということになり、移動する。
大丸を昇り、エレベーターの扉が開くとそこにあったのは、またしてもBARであった。
どこまで行っても、BARがついてくる!怖い!呪われてるんだと思う!
どうやら階を間違えたらしい。しかし友人たちは「まあ、ここでもいいか」などといって、いそいそと席に座り出すではないか。おい、こんなところに、がんもはないぞ。ちくわぶもないぞ。本当にいいのか。
かなり大きめのBARだった。黒人が店の隅のグランドピアノで小粋なジャズを弾いていた。友人たちは「へえ、いいじゃん」「オシャレじゃん」「モヒートをひとつ」などとすっかり悦に入っている。さっきまで練り物を食べたいと騒いでいた、東海林さだおのような瞳をしたキミたちはどこに行ってしまったの…?
腰が落ち着かず、タバコを吸いに席を立つ。BARの分煙ルームへと案内してもらう。
店のワインセラーの裏の、黒く重々しい自動ドアを開けたところにある、一畳ほどの狭いスペース。そこが分煙ルームだった。中に入り、自動ドアが閉まると、真っ暗である。こんなに喫煙者を嫌わなくても。なんだかナチスのガス室送りにされたような憂鬱な気分になりながら、タバコを吸う。ピアノの音が、うっすらと聴こえる。
一服終え、さて席に戻るかと立ち上がったのだが自動ドアが開かない。どこかに開閉ボタンがあるはずだと手探りするが、真っ暗なため、どこにあるのかわからない。
閉所、および暗所。僕は軽いパニックに襲われた。そうだ、ライターの火があるではないかと思いつき、着火し心もとない灯りを頼りにボタンを探すが、まったく見当たらない。副流煙が蔓延した部屋の中で、かすかな息苦しさを感じ始める。
「あれ?もしかして、ここで死ぬのかな?」
パニックもあいまって、大袈裟ではなく、そう思った。
落ち着け、自分。そうだ、助けを呼ぼう。僕はドアを叩いた。
その時、グランドピアノのメロディがひときわ大きく聴こえた。
「♪おめでとうございまーす!」
誰かの誕生日を祝っている。拍手が店内から湧いている。誰も僕に気づいていない。
半年後にBARの分煙ルームで白骨化した状態で発見される自分を想像し、僕は深い絶望感に襲われた。
これは、勘だけでバーテンダーをやっていた僕に対する、「BARの神様」からの罰だ。そう思った。
(※そのあと、なかなか分煙ルームから出てこない僕を怪しんだ店員さんによって救出された。店員さんは、ワラジ虫を見るような目をしていた)
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。お楽しみに!【バックナンバー】
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)