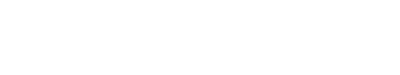執念なきものに発明はない…「チキンラーメン」が生まれた瞬間
【連載】「あの名言の裏側」 第7回 安藤百福編(2/4)「ひらめき」は身近なところにある
発明はひらめきから。
ひらめきは執念から。
執念なきものに発明はない。
──安藤百福
日清食品の創業者である安藤百福氏は、のちにインスタントラーメンの開発を手がける端緒となった体験のことを、自著『魔法のラーメン発明物語 私の履歴書』のなかで、次のように綴っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
太平洋戦争で、大阪の街は焦土と化した。食べるものがなく、スイトンや雑炊が食べられればいい方だった。芋のツルまで口にして飢えをしのいだ。阪急電鉄梅田駅の裏手、当時の鉄道省大阪鉄道局の東側は一面の焼け野原で、そこに闇市が立った。
冬の夜、偶然そこを通りかかると、二、三十メートルの長い行列ができていた。一軒の屋台があって薄明かりの中に温かい湯気が上がっている。同行の人に聞くとラーメンの屋台だという。粗末な衣服に身を包んだ人々が、寒さに震えながら順番が来るのを待っていた。一杯のラーメンのために人々はこんなに努力するものなのか。ラーメンという食べものに、初めて深い関心を持った。屋台の行列に、漠然とではあるが、大きな需要が暗示されているのを感じたのである。
(安藤百福『魔法のラーメン発明物語 私の履歴書』より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

同時期、政府はアメリカの余剰小麦を用いた粉食を奨励していました。ただ、そうした小麦の大半は、パンやビスケットにするばかり。そうした状況を見て、安藤氏は厚生省の担当者に「パン食はおかずがいるし、生活が洋風化してしまう。東洋には昔からめんの伝統がある。日本人が好むめん類をなぜ、粉食推奨に加えないのか」と意見したのだとか。
そのとき「それほど言うなら安藤さん、あなたが研究したらどうですか」と担当者に返され、麺類について深い知識もなかった安藤氏は引き下がるのですが、このやり取りとラーメン屋台の光景は、安藤氏の心に深く刻み込まれることになります。
前回説明したように、安藤氏は戦後、いわれのない脱税疑惑や理事長を務めた信用組合の倒産などを経て、ほぼすべての財産を失ってしまいます。事業の後始末を済ませたあと、自宅に引きこもる生活になった安藤氏。普通であれば、失意のなかで無為に時間をやり過ごすだけの暮らしになっても不思議ではありません。しかし、安藤氏はそうではありませんでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私は過ぎたことをいつまでも悔やまない。「失ったのは財産だけではないか。その分だけ経験が血や肉となって身についた」。ある日そう考えると、また新たな勇気がわいてきた。
(安藤百福『魔法のラーメン発明物語 私の履歴書』より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1957年(昭和32年)、安藤氏は「家庭でお湯があればすぐ食べられるラーメン」の開発に着手します。馴染みの大工に頼んで自宅の庭に10平米ほどの研究小屋を建て、中古の製麺機や直径1メートルの中華鍋を入手。それからは新しいラーメンの研究に生活のすべてを捧げることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まったく手探りの状態で研究を始めた私は、たった一つ天井からさがった四十ワットの裸電球の光の下で、チラシに思いついたことをメモしては壁に張った。朝五時に起きるとすぐに小屋にこもり、夜中の一時、二時になるまで研究に没頭した。睡眠は平均四時間しかなかった。こんな生活を丸一年の間、一日の休みもなく続けた。
(安藤百福『魔法のラーメン発明物語 私の履歴書』より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まさに鬼気迫る勢いで研究を続けた安藤氏ですが、その過程は失敗の連続でした。安藤氏は「作っては捨て、捨てては作るという気の遠くなるような作業だった」と振り返ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結局、食品とはバランスだということがわかった。食品の開発は、たった一つしかない絶妙なバランスを発見するまで、これでもかこれでもかと追求し続ける仕事なのである。
「チキンラーメンを発明した瞬間はどんな気持ちでしたか」とよく聞かれる。しかし、これという決定的な場面は思い浮かばない。失敗を繰り返しながら、しかし少しずつ前進していることはわかっていた。その先のわずかな光を頼りに、進み続けるしかなかったのである。
(安藤百福『魔法のラーメン発明物語 私の履歴書』より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
製麺や味付けで納得できるものをつくりあげたものの、それだけでインスタントラーメンの開発は終わりませんでした。商品化するには、長期保存の耐えうる保存性と、お湯を注ぐだけで食べられる簡便性を実現する必要があります。安藤氏が考えついたのは、麺を油で揚げることにより乾燥させる方法でした。
ひらめきは、身近なところにありました。あるとき、自宅の台所に入った安藤氏。台所では、夫人が天ぷらを揚げていました。油のなかで、衣が泡を立てながら水分をはじき出しています。さらに浮き上がってきた衣の表面には、ポツポツと無数の穴が開いています。「これだ! 天ぷらの原理を応用すればいいのだ」。安藤氏はそのときのことを「興奮した」と述懐しています。
- 1
- 2