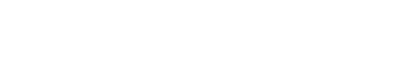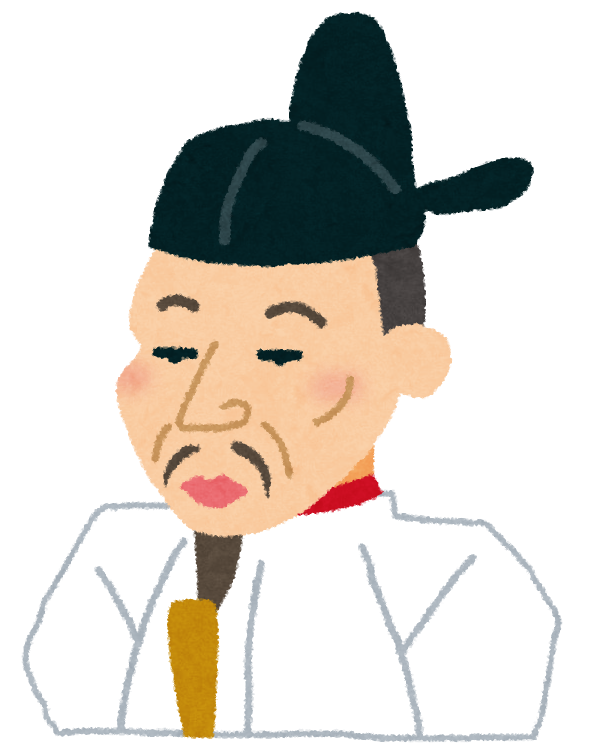銭湯と破風造りの意外な関係
外川淳の「城の搦め手」第5回
城を巡る旅は楽しい。ただし、城だけが旅を楽しくするアイテムではない。私の場合、鉄道、陶器収拾、麺類グルメなど、歴史とは離れたテーマに興味があることに加え、銭湯を巡りながら日本各地を旅している。
昔ながらの銭湯の外観は、城の櫓や天守を思わせるものがある。日本を代表する破風(はふ)造りの銭湯、足立区の大黒湯は、こんな外観である。

【詳細な情報は、東京都浴場組合のサイトを参照のこと。】
銭湯の世界では、大黒湯のような立派な破風を玄関とする建物を「社寺風」と表現する。だが、私は、神社の拝殿やお寺の本堂よりも、城好きなせいか、城の櫓や天守を想像する。逆の見方をすると、宇和島城の天守を見ていたら、ひと風呂浴びたくなってきた。

破風造りの銭湯を社寺風とするのは、中世において入浴の文化が社寺で発展したことに起因する。また、破風造りは寺社の建物にも多用されている。一例として、甲府の善光寺をあげてみよう。
比較してみると、たしかに宇和島城よりも、こちらの方が銭湯の外観としては、よく似ている。

「あそこの家はお城のようだ」というように、今でも、城は立派な建物の代名詞として利用される。
いずれにしても、立派な構えの銭湯は、利用者が自分の住居よりも豪華な空間に足を踏み入れることにより、ちょっとした観光気分を味わえるような空間的演出だった。また、同じ銭湯でも、大阪や神戸では、洋館風の構えが多く、地域によって豪華さの演出は異なる。

悲しむべきことは、銭湯の衰勢は、歯止めがかかることはない。築50年以上の「昔ながらの銭湯」だけでなく、マンションに併設されるような「今時の銭湯」さえも、閉店廃業に至る例も少なくない。
このブログを目にした方が「それじゃ、久しぶりに銭湯でひと風呂浴びてみるか」と思っていただければ、これに過ぎる喜びはない。
【お近くの銭湯については全国浴場組合のサイトを参照のこと。】
ただし関東では、東京都・神奈川県・埼玉県には銭湯組合作成のホームページがある一方、千葉県にはない。茨城県については、組合(公衆浴場業環境衛生同業組合)自体が消滅してしまった。お住まいの近くに銭湯が存在するのであれば、そのこと自体が幸運といえるのかもしれない。