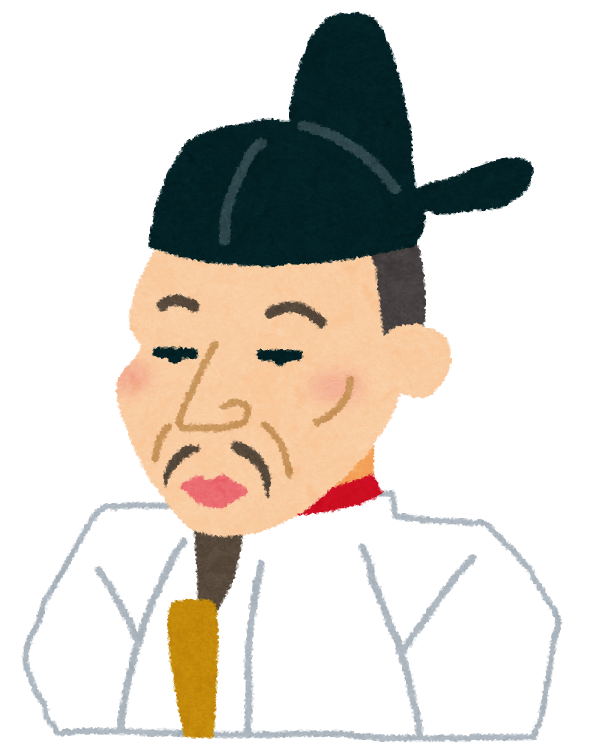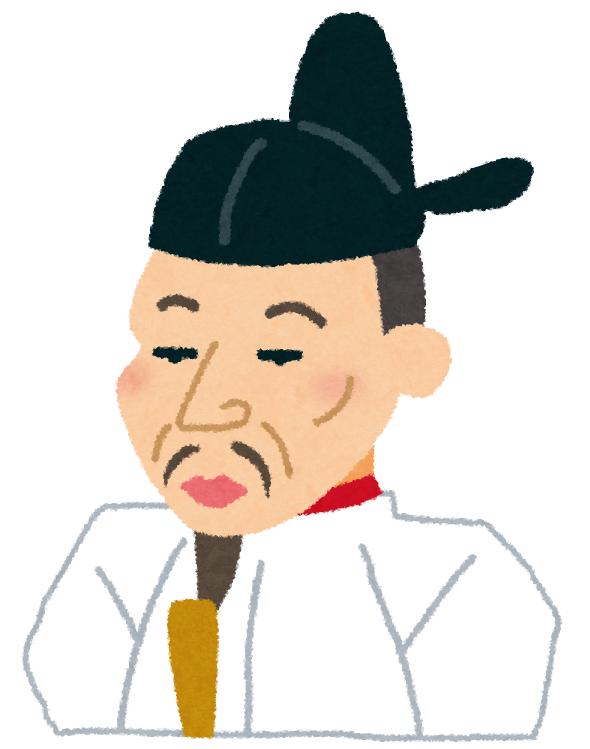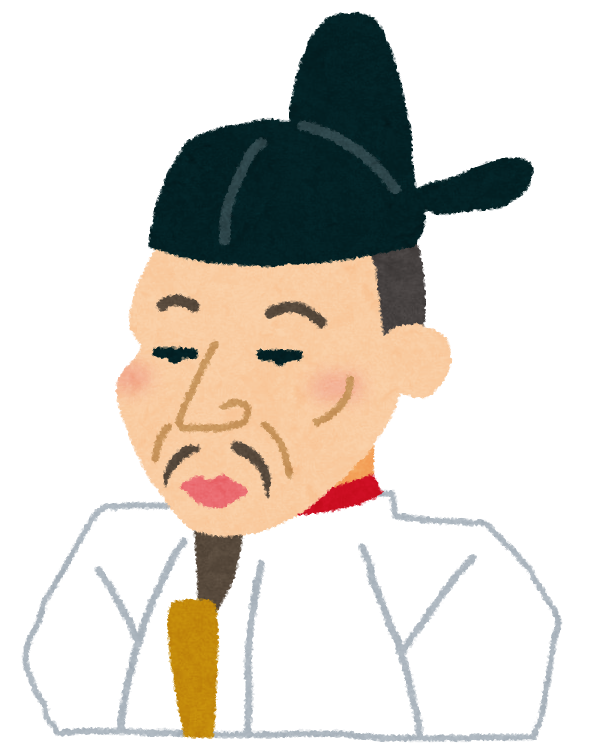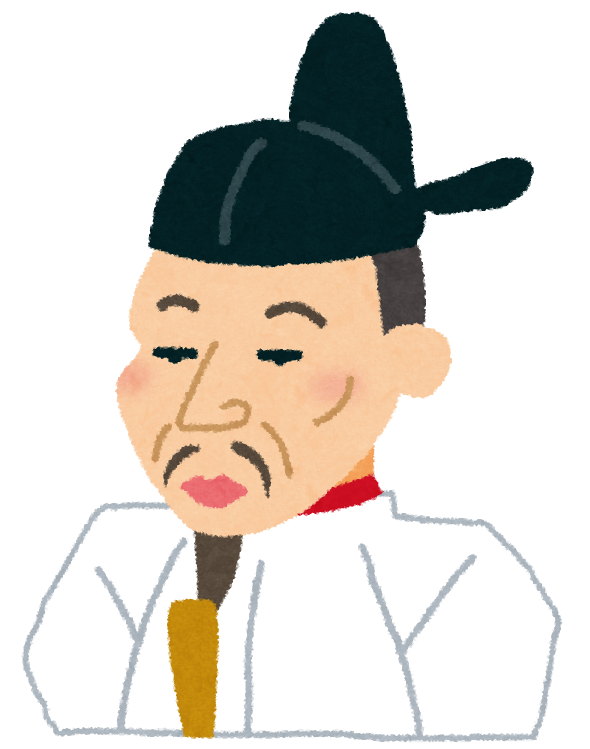「人間五十年」は諦めではない。限りある生命に執着した信長
覇王・織田信長の死生観 第2回
本能寺の変で突然の死を遂げた。
最期まで自ら槍を取り戦った信長の人生は
命知らずの破天荒なものだったのか?
信長は死をどのように捉えていたのか?
そして、ついに見つからなかった死体の行方は?
未だ謎多き信長の人生と死に迫る!

今川軍が味方の付城に攻めかかったという報せにすっくと立ち上がった信長やにわに幸若舞『敦盛』の一節を舞う。
「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。一度生を得て滅ぬ者のあるべきか」
(人間が生きる50年という歳月は、神のいる天と比べれば一瞬のことに過ぎない。ひとたび生を享け、死なない者はいない)
そして、出陣の法螺を吹け、具足を着けよと命令する。具足を着けると立ちながら食事を済ませ、清須城を飛び出した。5人の小姓衆のみがあわてて後を追った。
永禄3年(1560)、信長が桶狭間の戦いへと向かう有名なシーンである。あまりにも芝居じみていようだが、信長の側近太田牛一の手に成る『信長公記』にこのように書かれているのだから、おおむね信用してもよいだろう。
同じ『信長公記』には、次のような話も載っている。
信長の若い頃のことである。尾張の天永寺の住職の天沢という僧が、関東まで旅をした。その帰り道に甲府に寄り、武田信玄に会った。尾張の僧ということで信玄は、信長についていろいろと尋ねた。天沢は信玄の質問に応じて、信長の日常について語ったという話である
それによると信長は、先に引用した幸若舞『敦盛』の「人間五十年…」の一節のほかに、小唄も好んだという。特に繰り返し唄っていたのは、「死のふは一定、しのび草には何をしよぞ、一定かたりをこすよの」(人は必ず死ぬ。生前をしのぶたよりとして、生きている間に何をしておこうか。人はきっとそれを思い出して、語り草としてくれるであろう)
という一節だった。「人間五十年」「死のふは一定」。この歌詞を信長は、若い頃から愛唱していたのである。ふつうならば人生の諦観ととらえるべき歌詞なのだが、信長はもちろんそのようなとらえ方をしていなかった。彼の死生観は、常に能動的で通俗的なものだったのである。
<次稿に続く>