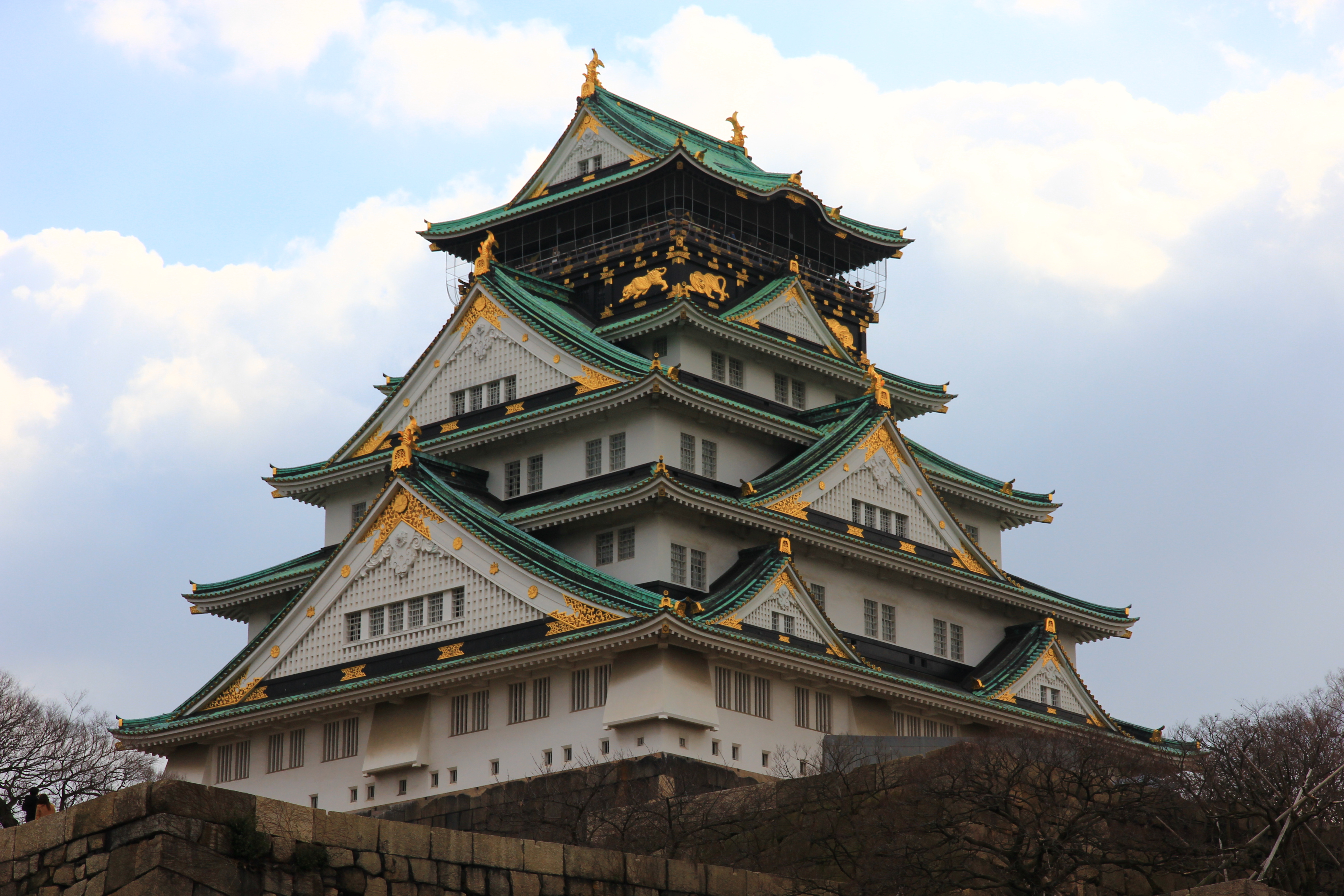主夫は室町時代からいた? 男性文化であった〇〇道
ニャンと室町時代に行ってみた 第1回
今でこそ、女性がたしなむ上品な習い事というイメージのある茶道ですが、女性の教養になるのは、明治維新の後、武家の庇護を失った各流派の家元が、茶道の再興を図るために女子の教養として普及させてからといわれています。
日本に茶がもたらされたのは古く、平安時代初頭、茶を煮出して飲む「煎茶法」が伝えられたのが始まりです。茶の栽培もほぼ同じ頃に始まり、平安京の大内裏の東北に茶園が造られ、朝廷の仏教儀礼などに使用されていました。一般に喫茶の習慣は広まるのは鎌倉時代以降です。日本臨済宗の開祖栄西が修業先の宋から、抹茶に湯を注ぎこんで飲む「点茶法」をもたらし、喫茶文化を日本に根付かせました。当初は薬用として珍重されていましたが、やがて寺院から武士、庶民へと普及していきます。
この普及の原動力となったのがマンガにも登場する闘茶です。「茶寄合【よりあい】」「飲茶勝負」とも呼ばれます。室町時代初頭、もっとも盛んだったのは「四種十服茶【ししゅじっぷくちゃ】」でした。4種類の茶のうち3種類は三服ずつ、1種類は一服して飲んだ茶の種類を当てるもので、単に言い当てるだけでなく、賭け物を競い合う賭博行為として行われることが多かったようです。バサラ大名として有名な佐々木道誉の屋敷ではしばしば闘茶が行われ、座敷には賭け物が山のように積み上がったと伝えられています。闘茶の後は酒宴が設けられるのが常で、猿楽や遊女の踊りに興じました。また、唐物趣味の流行もあって、この頃の茶席はテーブルを囲み椅子に座る異国風のスタイルで、椅子にはトラやヒョウの皮が好まれたといいますから、後世の茶室のイメージとはずいぶん異なっていたようです。

しかし、室町時代も半ばになると、茶道具を観賞しながら静かにお茶を楽しむ「書院茶」が流行する一方、簡素な茶を楽しむ庶民の「地下【じげ】茶の湯」も生まれ、これらが融合して深い精神性を重んじる「わび茶」に発展していきます。村田珠光【じゅこう】が創始し、千利休によって完成されたわび茶は、禅林風の簡素な茶料理としての懐石料理を生むなど、日本の食文化にも画期的な変化をもたらしました。やがて茶の湯は武家に広まり、「茶湯御政道」と称して茶の湯を許可制にして家臣統制に利用した織田信長、大規模な茶会を開いて権威を天下に誇示した豊臣秀吉など、大名によって政治に利用されるまでになります。
このように、朝廷の仏事から茶湯御政道まで、お茶は一貫して男性文化の中で発展してきました。歴史上、著名な女性茶人が現れなかったことにもそれが示されています。茶の湯と同じように女性のイメージが強い香道や立花【りっか】(生け花)も、男性の趣味・教養としてもてはやされました。香道は奈良・平安の昔から宮中でたしなまれてきましたが、鎌倉・室町時代になると香木の香りを鑑賞する「聞香【もんこう】」の作法が確立され、「四種十服茶」と同じように10包の香木を当てて賭物を競う「十炷香【じしゅこう】」という遊びも生まれました。香道は公家や武家の子女にも人気でしたが、様式が確立される過程では足利義政や京の文化人が積極的にかかわったといわれています。
「立花」と呼ばれた華道が確立されたのも室町時代です。座敷に飾る唐物の器に挿す花の姿かたちを工夫する中で洗練され、京都・六角堂の僧侶池坊専好【いけのぼうせんこう】によって大成されたといわれています。島津氏の重臣上井覚兼【うわいかくけん】は風雅の道に通じた教養人で、和歌や連歌に通じていましたが、立花にも造詣が深く専好が創始した池坊流に学んでいます。
そのほか芸能ではありませんが、中世の男性の教養として料理があげられます。現代でもたくさんの男性が家庭で料理を楽しみ、プロの料理人も多くが男性ですが、家事として見た場合、基本的には女性の仕事に位置づけられます。しかし、中世において料理は武士も含めた男性の教養の一つで、絵巻物にも男性が箸と包丁を持って調理している姿が描かれています。『宋五大草紙【そうごおおぞうし】』という書物にも、若者がたしなむべき教養として兵法・弓馬・和歌・蹴鞠などのほか「包丁(料理)」が挙げられています。そうした文化は外国人の目にも珍しく映ったらしく、宣教師ルイス・フロイスは「ヨーロッパでは普通女性が食事を作るが、日本では男性が行い立派なことだと思っている」と述べています。
<『おかしな猫がご案内 ニャンと室町時代に行ってみた』コラムより>