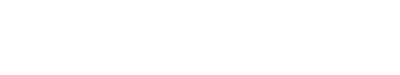「良くも悪くも常総・木内野球が野球人生の核」仁志敏久氏の回顧
仁志敏久氏が学んだ「常総・木内野球」の発想法。
独自の世界観を持って理想を学び、考える人へ聞く1週間集中インタビュー企画。U-12野球日本代表の監督を務める仁志敏久氏のキャリアから学んだ「子どもを育てる」うえで欠かせない視点(全三回・第一回)。
Q3.キャリアの中でもっとも大事と言われた常総時代。その理由とは?
――仁志さんは甲子園出場、大学、社会人を経験し、プロ野球選手になりました。さらにはアメリカの独立リーグでもプレーされています。キャリアの中で「核」と言えるのはいつでしょうか。
仁志 野球の核は高校ですよね。常総学院高校で木内(幸男)監督のもとで野球をしたこと。これがすべての始まりだったと思います。現役を引退してから気付くことなんですけど、野球に関しては木内さんから教わったことが、いつも軸にあって、良くも悪くも判断基準になっていたと思うんです。
――常総と同じだ、これは常総と違う、というふうにでしょうか。
仁志 「常総とは違う」とまではっきり感じるわけではないですけど、現役を引退するまでプレーをする中で「何かが違う」「なんでこうなるんだ?」というギャップはつねにありました。特にチームマネジメントや野球観の部分では、正しいと思っていたことが全然通用しなかったり、「考えたこともない」と言われたり……(笑)。その教えは考え方としてはすごく常識的なものだったと思うのですが。
――そのもっとも重要な考え方とはなんだったのでしょうか。
仁志 木内さんは言葉で諭すタイプの方ではなかったんですね。行動から何かを感じさせてくれる人――というよりも、感じ取らないと木内さんのもとではやっていけないんだと思います。ものすごくよく喋るんですけど、教えるべきことを言葉で教えようとしない方。例えば試合で「ここは送りバントだ」と誰もが思うシーンでそれをしなかったりするんですけど、つねにその場その場の判断を大事にされていたんです。だから世の中の常識でもケースによっては非常識になることもある、自分で考えて臨機応変にやらなければいけない、ということを学びましたね。
――野球で言えば「セオリーとは本当にセオリーなのか」といったことでしょうか。
仁志 「すべてはそれも一理ある」んだと思うんです。セオリーに一理あることがあれば、反対のことに一理あることもある。あまり考えすぎるといろんなことが頭に入りすぎて何が正しいのかわからなくなってしまうんですけど……でも答えが一つだと思ってしまうこと、これが一番の間違いだと思いますね。
――なるほど。
仁志 さっきの話に戻ると、木内さんは一対一で話すのが苦手な方で、みんなの前で話しをすることが多かったのですが、あるプレーについて話したとしても、それはそのプレーをした選手だけに伝えたいわけではなく、みんなに伝えたいという雰囲気がありました。一人を相手にするのではなく、部員全員を相手にしているという感覚です。

――人の心をつかむために計算してやられていたのでしょうか。
仁志 いや、感覚だったと思います(笑)。理由を後付けする形で話したりはされてましたけど、計画的にやっていたかと言われればそうではなかったなと思うんです。でも、やっていることは理にかなっていた。例えば、夏の大会前は一時間くらいしか練習しないんですね。レギュラー陣は4時に授業が終わったら5時には帰っていた。調整のためです。その代わりに大会一カ月前に、ものすごく追い詰められる時期があるんです。ものすごいきつい練習をして、厳しい言葉も投げかけられる。心身ともに落とす時期、というか。そこから大会に向かって徐々に上げていって、大会前は休養をしっかり取らせる。そういうことが感覚的にできる方でしたね。