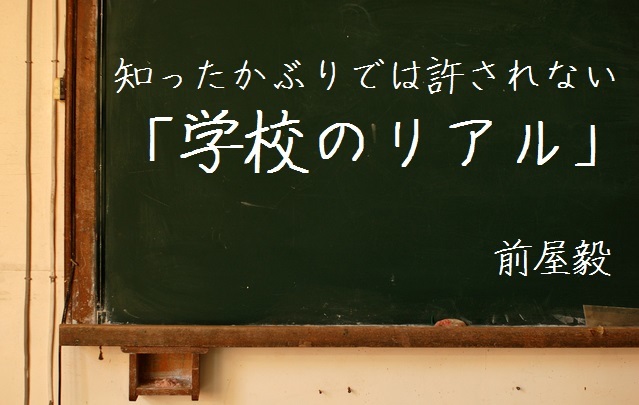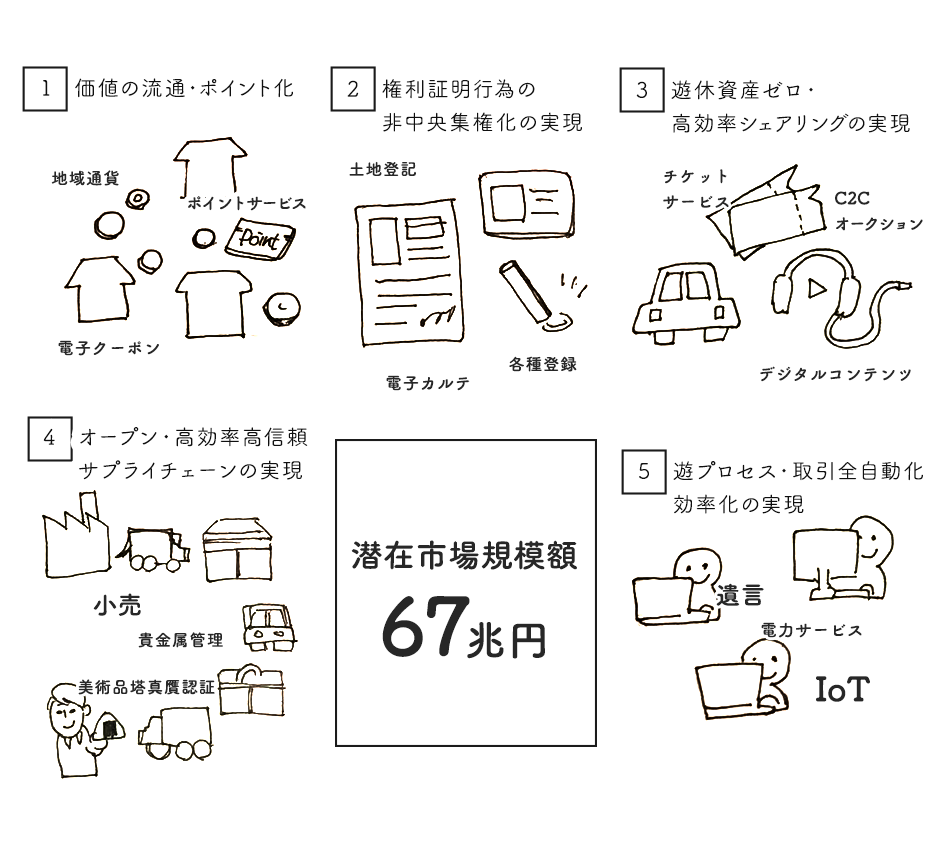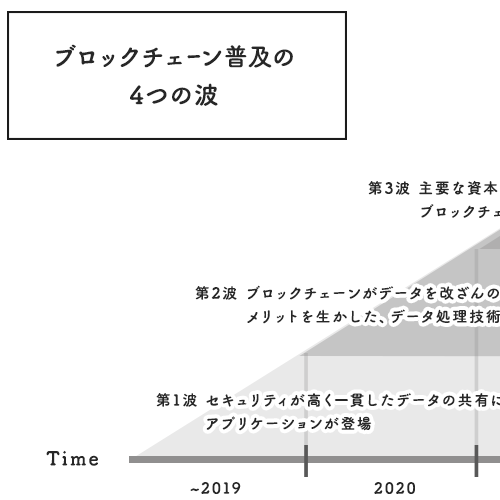中学教員の6割近くが「過労死ライン」に達している現状――なぜ教員の残業は無制限なのか?
知ったかぶりでは許されない「学校のリアル」 第1回
◆教員が無制限に残業させられる理由
そもそも、なぜ教員は無制限に残業をさせられてしまうのか。その残業に対して、なぜ一般の企業なら当然となっている残業代の支払いがないのか。その原因となっているのが、「給特法」という法律である。正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という長ったらしい名前で、1971年5月に成立し、翌年1月に施行された。
戦後には、教員も労働者の一員として労働基本法が適用され、8時間労働制が適用され、時間外労働には残業代が支払われることになっていた。ところが現実には、当時の文部省や労働省、人事院までが指導したにもかかわらず、残業代が支払われていなかったのだ。そのため訴訟が繰り返され、裁判所は法律に従って残業代の支払いを命じる判断を繰り返した。
この事態に危機感をもったのが文部省である。規定どおりに残業代を支払っていたのでは財布がパンクしてしまう、という理由にほかならない。そして考えだされたのが、給特法だった。
この法律によって、残業の平均的時間数に見合うものとして、基本給の4%を「教職調整額」という名の残業代として支払うことにしたのだ。ただし、当時の平均的時間数は「月間8時間程度」でしかない。
先述した文科省調査でも、中学教員の平均勤務時間は週に63時間18分である。給特法ができた当時と比べれば、残業時間は10倍以上にもなっているのだ。にもかかわらず、給特法が施行された当時と同じく教員の残業代は「基本給の4%」に止まっている。残業代は支払われていないに等しい。
そんな条件で、なぜ教員は残業時間を増やしつづけているのか。何人もの教員に質問してみたのだが、返ってくる返事は同じで、「子どものためとなると拒否できない」といったものだった。「子どものため」という前提があると、過労死ラインを超えてでも残業してしまうのだ。「教員の習性」と呼んでいいものかもしれない。
実際に、過労死してしまう教員は少なくない。にもかかわらず、それが大問題となって注目されないのは、過労死として認定されるケースが少なすぎるからだ。なぜ認定されないかというと、認定については「校長などに命令されての残業かどうか」が判断基準になるからである。
給特法では、「原則として時間外勤務は命じない」となっている。校長といえども教員に残業を強制してはならない、ことになっているのだ。例外として、生徒の実習、学校行事、教育実習の指導、教職員会議、非常災害時等やむを得ない場合についてのみ残業を命じることができるとなっている。そんなもので、週に60時間以上もの勤務にはならない。
つまり教員がやっている大半の残業は、「自発的」なものと判断されてしまう可能性が高い。自発的なものであって残業には該当しない、となってしまいがちなのだ。だから、明らかに働き過ぎが原因であっても、過労死とは認定されにくい、おかしなことになる。
◆最大の被害者は子どもたち
教員の残業は、単純に自発的なものではない。教員の趣味でやっているものではなく、「実質的な強制」でしかない。それが当然のことのように行われている原因は、「子どものために」という教員の思いであり、それを当然と思い込んでいる保護者や周囲の意識でしかない。そのために過労死も認められず、働き過ぎであっても多くの人が当然のことのように受けとってしまっている。
過労に陥っている教員も当然ながら被害者だが、最大の被害者は子どもたちにほかならない。過労で疲れ切った教員が、まともに子どもたちに向き合えるはずがないからだ。
この状況を変えるには、教員も保護者をはじめとする周囲も根本的に意識を変えるしかない。教員も生身の人間であり、一般の企業で働く人たちと同じ労働者であるという認識を取り戻すことが、どうしても必要である。給特法がつくりあげてきた「幻想」を、教員も保護者も捨てる必要がある。
それには、署名運動が重要な役割を果たすにちがいない。働き方改革で残業に上限が必要というなら、教員の残業にも上限を設けて働き方改革をすべきである。同時に、残業代が支払われる普通の環境を整えなくてはならない。
上限を設けることで残業問題のすべてが解決するわけではない。しかし、教員の働き方改革をすすめる第一歩になっていくはずだ。
- 1
- 2