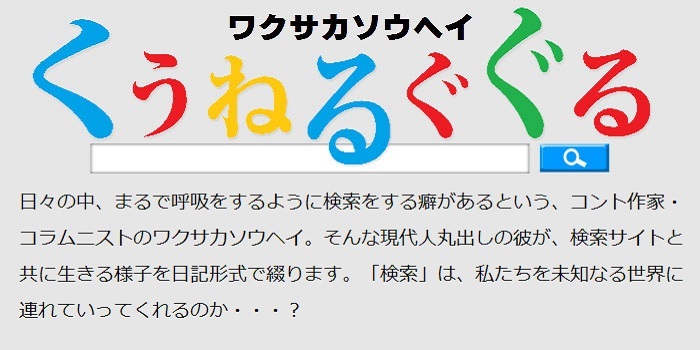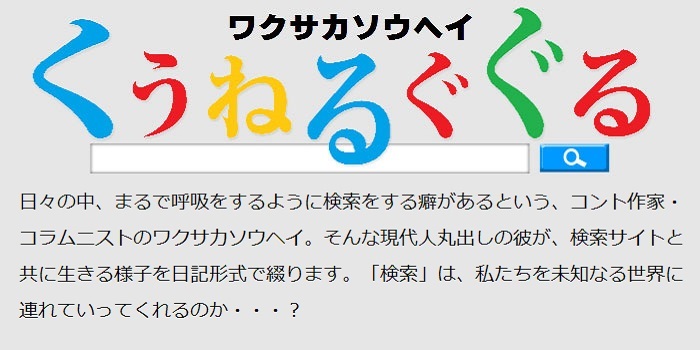第25回:「ノロケ話」
<第25回>
3月×日
【ノロケ話】
学校帰りのデートなのだろう、制服のままの高校生カップルが何組も僕の横を通りすがってゆく。
腕を組み、手をつなぐ彼らの表情は「原液の幸せ」をたたえており、なんというかこの笑顔をPhotoshopとかで反転させたらちょうど死刑囚の顔が表れるのではないのか、というほどに、それはもう皆一様に逃げも隠れもしない幸福な笑みを浮かべていた。
僕は、水族館にいた。東池袋のビル群の中にある、小さな水族館である。
最近、ひとりでいることが前にも増して多くなった。日中はいつもひとりで家の中で過ごし、夜はひとりで酒を飲む。慣れてしまえば、ひとりは、楽だ。それに孤独は悪いことではない。
しかし、慣れるということは、麻痺するということでもある。今日の昼過ぎ、おもむろに点けたテレビのワイドショーで、水族館特集をやっていた。「水族館」、無駄に分解するなら、水の族がいる館。もう何年、水族館に行っていないだろう。水族館は、基本的に家族や恋人と訪れるスポットである。
もしかしたら僕はこのまま、この先の人生、一度も水族館に訪れることなく、孤独死するのでは?そんな不安が頭をよぎり、気がつくと僕はひとりで水族館の入り口に立っていた。
「お前、イソギンチャクみたいな顔をしているな」と、高校時代、クラスメイトである増田くんに指摘されたことがある。なので、まあ水族館にひとりで佇んだとしても、水の族のみなさんに上手いこと馴染むことができるだろう、そんな自信もあった。
甘かった。
金曜夕方の水族館は、周りを見渡せば、カップルだらけであった。
その中でひとり、僕だけが「ビート板か」みたいな感じで、浮いていた。
水槽の向こうのマンボウに集中しようにも、高校生カップルたちの甘い囁き声が耳に入って心がかき乱される。
「やだ、もう、たっくんのエッチ」
「なんだよ、ちょっと触っただけじゃん」
「ちょっとでも、エッチだよ!」
「バカ、声が大きいって」
「もう、たっくんって、本当にエッチなんだから」
たっくん、エッチエッチ言われすぎである。この美しき地球の数限りあるエッチを無駄遣いしないでほしい。
こんなにもカップルという生き物は、人前でイチャつくものなのか。長らく東京ウォーカー的なスポットから足が遠のいていた僕は、その現実を前に愕然とした。
そして、とある気づきがよぎり、震えた。
もしかしたら、僕以外の全ての人類は、僕の見ていないところで、異性とイチャついているのではないか?僕が家でだらだらと「おたんこナース」とかを布団の中で読んでいるその裏で、他の全ての人類は恋人と愛を語り合っているのではないか?
思わず、手元のiPhoneで「ノロケ話」を検索した。
そして、驚いた。
ネット上には、信じられないくらい、大量のノロケ話が花を咲かせていた。
「寝る時も手をつないで寝ています♡」
「この前、彼が『あ、ゼクシィ買わなきゃ』って(。・ω・。)」
「いっつも可愛いよ、って言われちゃいましたw」
圧巻なのは「発言小町」で、「みなさん、ノロケ話をしましょう!」というスレッドのもと、小町たちがノロケ話を発言しまくっていた。
どのノロケ話も、甘い。甘すぎる。まるで、言葉の月餅である。
僕以外の人々は、この世界の裏側で、本当にみんな恋人とイチャついていたのであった。
iPhoneを片手に、僕は高校時代を思い出していた。
高校一年生。夏休みが終わった二学期の始業日。クラスのドアを開けると、ほとんどのクラスメイトが恋人と仲睦まじく談笑していた。夏休みの間、部活動の合宿などを経て、帰宅部である僕の知らぬところで、カップルがバシバシ誕生していたのだ。あの光景だけは、忘れることができない。僕に「イソギンチャクに似ている」と言い放った増田くんも、恋人の髪を人差し指と中指でなぞっていた。
まさか、30歳になって、またあの始業日のときと同じ寂寥感を抱くことになるとは。
誰でもいい。5秒だけでいい。誰か、僕にイチャつかせてくれないか。
周りを見渡した。カップルしかいない。
そのとき、誰かと目が合った。
アシカだった。
アシカは少しだけ僕の瞳を見つめて、口の端を歪めたのち、プールの底へと姿を消した。
人類どころか、水の族にまで相手にされていない自分に、引いた。
*ワクサカさんの新刊『夜の墓場で反省会』が好評発売中です!
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。