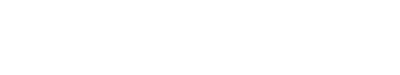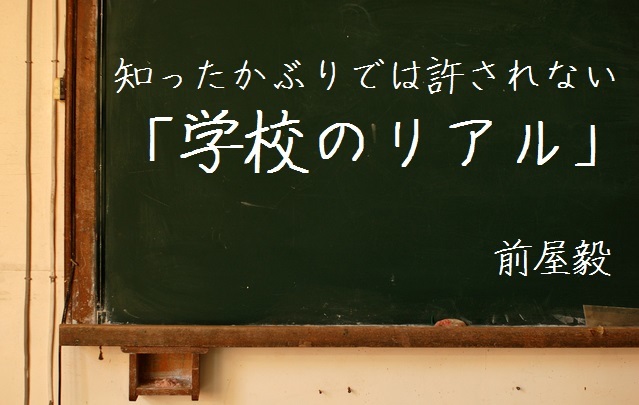教員は聖職者だから、残業代は少なくていいのか?
知ったかぶりでは許されない「学校のリアル」 第6回
◆教員自身が「教員聖職論」にとらわれていた
聖職を辞書(『大辞林』)で調べてみると、「神聖な職業」とある。そして「聖職者」として、「神官・僧侶・主教・司祭など」という職が並べられている。宗教上の職業、それも位の高い職業を指しているようだ。ただし辞書では、教員または教師を聖職にふくめてはいない。
戦後となった1952年、日本教職員組合(日教組)は教員の基本的性格と行動の基準として、10項目からなる「教師の倫理綱領」を決定した。その6項目目に、「教師は労働者である」と謳っている。
これにそって日教組は1960年代に残業代の支払いを求める訴訟を起こしていく。そして、教員への残業代支払いを命じる判決が相次ぎ、1967年、当時の文部省は残業代の予算を計上する事態となった。
その文部省の対応に対して、「教員は労働者ではなく聖職である」との理屈で反対したのが自民党文教族だった。教員は聖職者なのだからカネのことなどうるさく言うべきではない、というわけだ。
教員聖職論は、唐突に出てきたわけではない。それは現在に続く学校制度がつくられた明治時代から、意図的につくられてきたものである。教員を「先生」と呼ばせる慣習に、そのことが象徴されている。
それに、いちばんとらわれていたのは教員自身かもしれない。自民党文教族による教員聖職論に抗して労働者としての立場を主張し、正当な残業代の支払い要求を徹底できなかった。そして4%の一律手当で妥協し、残業時間が急速に増えるなかでも、残業代を求める声を大きくできなかったのだ。聖職という言葉は使わないにしても、「一般の労働者とは違うのだから、カネのことを口にするのはみっともない」という意識が邪魔しているからだろう。
教員だけでなく、保護者をはじめとする教員以外の人たちにも共有される意識に違いない。だから、教員の過重労働や正当な残業代が支払われていない現実を前にしても、「教員なんだから」で済ませてしまう。
教員聖職論を、教員も、それ以外の人たちも受け入れてしまっている。それを変えなければ、教員の過重労働問題は解決しない。なにより、教員自らが聖職論と向き合う必要があるのが現実だとおもえる。
- 1
- 2