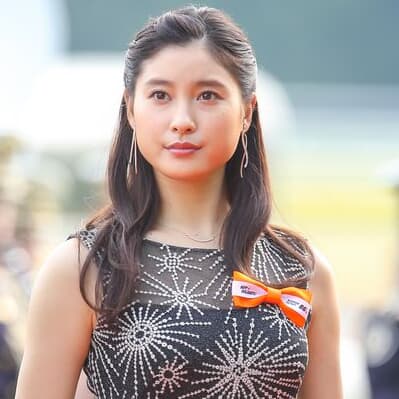「原爆、終戦、独裁者ヒトラー最期の40時間の安息」1945(昭和20)年 【連載:死の百年史1921-2020】第1回 (宝泉薫)
連載:死の百年史1921-2020 (作家・宝泉薫)
死のかたちから見えてくる人間と社会の実相。1921(大正10)年から2020(令和2年)までの日本と世界を、さまざまな命の終わり方を通して浮き彫りにする。作家・宝泉薫が「人と時代の死相」を見つめた連載「死の百年史 1921-2020」がスタート。第1回は「原爆、終戦、独裁者ヒトラー最期の40時間の安息」にフォーカスした1945(昭和20)年だ。

菅内閣発足後の国会で争点になったのが、学術会議任命問題だ。これが争点というのも、いかにものどかでしょぼい話だが、それを何より実感させたのが、日本学術会議の会員に任命されなかった教授のひとりから出たというこの発言である。
「ナチスのヒトラーでさえも全権を掌握するには特別の法律を必要としましたが、菅総理大臣は現行憲法を読み替えて自分がヒトラーのような独裁者になろうとしているのか」
これと似た発言は米山隆一や金平茂紀といった反権力気取りの論客からも出た。あたかも、菅はヒトラー(自民党はナチス)的な批判の合唱である。といっても、現実認識や歴史認識からズレまくった音痴の合唱なので、騒音でしかない。こういう批判がやりたければ、せめて北朝鮮や中国に行くべきだろう。
かと思えば、NHKの朝ドラ「エール」における第二次世界大戦の描き方が賛否両論を呼んだ。作曲家の主人公を戦地に行かせ、恩師がまさに戦死するところを目撃させるという過激な展開により、主人公の人生は劇的に変化する。それまで戦争に協力的だった主人公は、これを機に、深く落ち込み、命の大切さに目覚め、スランプを乗り越えて平和への祈りを奏でるようになるのだ。
そこにはやはり、一種の予定調和というか、戦争を絶対悪とする(したい)戦後日本の創作物にありがちな思い込みが感じられた。人間である以上、戦争はなかなか避けられるものではなく、また、そこには哀しみもあれば、怒り、喜び、楽しさもある。主人公の変化を通して、その多様性を表現したことは評価できても、平和に目覚めてからをとにかく善とするような姿勢には違和感を禁じえなかったものだ。
とはいえ、もちろん、自分が生まれる前の過去のことはよくわからない。残された資料などを手がかりに、想像するだけだ。ただ、その際、世間的な善悪、あるいは、たかだか数十年のあいだに形成された常識にはなるべく振り回されたくない。あくまで自分の感じたものを大事にしたいのである。そのついでに、筆者が感じて書いたものが誰かの想像の手がかりになれば幸いだ。
この連載は、さまざまな死のかたちを通して、人間や社会について考えていくものである。死は命の終わりというだけでなく、その人の本質をあらわにしたり、そこから別の人たちへの影響が始まったりもする。という意味で、格好の学びのテキストなのだ。
その第1回には、1945(昭和20)年を選んでみた。先の大戦が終結した年であり、多くの人間が死に近い場所で生きていた特別な年だ。