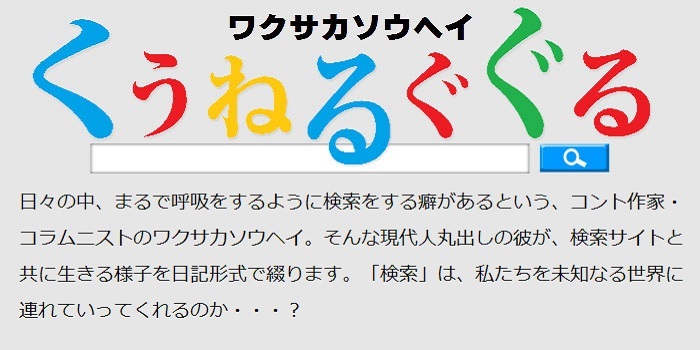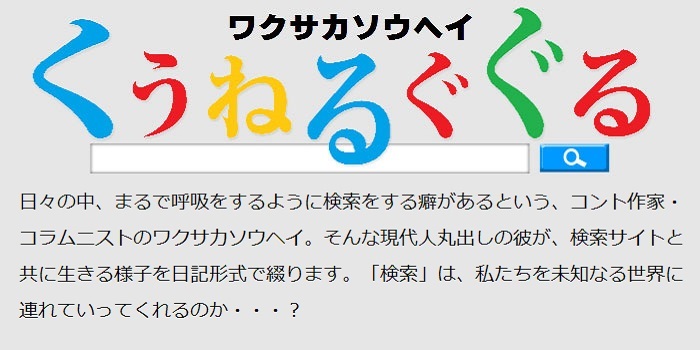第41回:「偉人 あだ名」
<第41回>
7月×日
【「偉人 あだ名」】
「ダンディ!」と、雑踏の中、誰かを呼びかける声がした。夏のはじめの、べたついた空気が街を染めていた。
え?と思い、振り返ると、そこに高校時代の旧友の顔があった。
果たして「ダンディ!」とは、僕のことを呼びかける声であった。
「久しぶりだなあ、ダンディ」
旧友は、屈託のない笑顔で卒業以来久々の再開を喜んでいる。僕は、うろたえた。
そうだった、僕の高校時代のあだ名は、「ダンディ」だった。
高校一年生、入学式の日。式を終えたその教室では、初めて顔を合わす者同士の、妙によそよそしい会話がポツポツと花咲いていた。僕は教室の隅の席で、その様子をボンヤリと眺めていた。人見知りと、自意識過剰とが邪魔をして、誰にも話しかけることができなかった。
すると突然、「よう、はじめまして!」と、前の席の男子が振り返り、話しかけてきた。
「僕は畑中!演劇部に入ろうと思ってるんだ!」と彼はストレートに自己紹介をした。
心の準備ができていないうちから話しかけられたことに、僕はひどく狼狽した。と同時に、やっとここから自分の花の高校時代が始まるのだという喜びと気恥ずかしさのようなものも湧き起こった。
とにかく、彼に返事しなくては。いそいで自分も自己紹介の弁を探した。
「やあ!こんにちは!僕は逆子で産まれたんだ!」
「はじめまして!もしかしたら僕とキミとは前世で会ってるかもしれないけど、はじめまして!」
「よろしくね!ところでヒットラーってまだ生きてるって知ってた?」
「おっす!高校初日って、疲れるよね!そんなときには、これ!肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に、アリナミンV!」
「はじめまして!もしかしたら僕とキミとは前世でナポレオンと従者の関係だったかもしれないけど、はじめまして!」
違う違う違う。
奇をてらう必要は、ない。
ここは普通に挨拶を述べるだけでいい。
僕は軽いパニックに陥っていた。落ち着け、落ち着くんだ、自分。
心の中で深呼吸をして、言葉を発した。
「こんにちは。はじめまして」
寺の朝食のごとき、ひどく薄い挨拶をしてしまった。慌てて取り繕おうとしたが、語彙が続かず、僕は口を閉ざした。
「ずいぶん、落ち着いてるなあ」と畑中くんは感嘆の声をあげた。そして、
「よし、キミのあだ名は、ダンディだ」
と藪から棒に言い放った。
それ以来、僕のあだ名は、「ダンディ」になった。
「ダンディ」という呼称は、あっと言う間に学年中に広まった。
「よう、ダンディ。次の授業、教室どこ?」
「ダンディ、昨日図書室で手塚治虫のマンガのHなシーンのところだけ読んでただろ」
「ダンディ、ワックス塗りたての廊下で、よくそこまではしゃげるな」
高校三年間、僕はずっとダンディだった。
一応説明しておくが、実際の僕にダンディ要素は、一切ない。錠剤はジュースと一緒じゃないと飲めないし、ジブリの新作映画は上映初日に観に行くし、回転鮨は5皿でお腹いっぱいになる。そんな虚弱な男が、「ダンディ」と呼ばれているのである。アンチテーゼにもほどがある。
「ダンディ」と呼ばれるたびに、相手の心の奥底の嘲を想像していた。
そして実際、みんな半笑いで「ダンディ」と呼んでいた。
高校初日に畑中くんの発した、たったの一言で、僕の青春ライフは方向付けられてしまったというわけだ。
高校を卒業して10余年が経った。まさか、まだ僕のことを「ダンディ」と呼ぶ人間がいるとは。
三十路の男が、三十路の男に、路上で「ダンディ」と呼びかけられているのである。異常事態でしかない。
旧友と別れ、家へと戻る道すがら、iPhoneで「偉人 あだ名」をグーグル検索した。
善良な一般市民である自分が、なぜあだ名ひとつでこんなにも苦しい呪縛に囚われなくてはならないのか。不公平である。何者でもない平凡な人生を歩む僕だけではなく、歴史上の偉人たちも変なあだ名で苦しんでいてもらわないと、バランスが取れないではないか。そんな歪んだ息を巻いていた。
中世のフランスの政治家に、シャルル=モーリス・ド・タレーラン=ペリゴールという人がいたらしい。なんちゅう長い名前だ。なんか数学の公式みたいになってるぞ。
この人に、ナポレオンが付けたあだ名が凄い。
「絹の靴下の中の糞」。
ひどすぎるだろ。
「糞」って。それを「絹の靴下の中の」などという、あまり必要性を感じない表現で修飾するだなんて。
「おい、絹の靴下の中の糞、クーラーボックスの中のアイス取ってきて」などとナポレオンになじられていたのだろうか。
平安時代の公卿に藤原顕隆という人がいたらしい。政治の裏舞台で暗躍していた彼に付けられたあだ名にも注目してほしい。
「夜の関白」。
完全に下ネタである。
いや、実際は政治のために秘密裏に動いていた時間帯が夜だったから、という理由らしいが、それにしても下ネタにしか見えない。
きっと「夜の関白」は、小バカにしてるニュアンスが含まれていたのだろう。
「お、夜の関白、夜にそなえて昼寝か?」
「なんだ、明るいところで会うと、ただの関白だな」
「夜の関白のくせに、モーニングセットなんて注文してんじゃねえよ」
周りからしてみれば、すごくいじりがいのあるあだ名だったに違いない。
ジュリアス・シーザー。「ブルータス、お前もか」でおなじみのあの人であり、なにをした人なのかよくわからないことでもおなじみのあの人である。このシーザーのあだ名も、実に味わい深い。
「ハゲの女たらし」。
果たして本当に、「ハゲの」のくだりは必要だったのか、という疑問が鋭く存在している。「女たらし」で十分なのに、「ハゲの」って。身体のことはあだ名にしちゃいけないって学校で習わなかったのか。同じハゲの民として、シーザーには同情したい。
想像していたよりも、偉人たちはひどいあだ名を付けられていた。
気づけば、気持ちが軽くなっていた。
「ダンディ」なんて、そんな悩むほどのあだ名ではない。
「絹の靴下の中の糞」に比べたら、全然「ダンディ」のほうがマシだ。
iPhoneをポケットにしまい、軽やかな足取りで家路を歩いた。
途中で、中学時代のあだ名が「アブラメガネ」だったことを思い出し、軽やかな足取りは再び重く沈んだ。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)